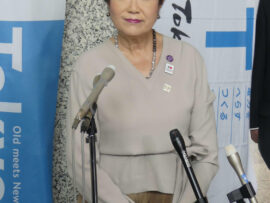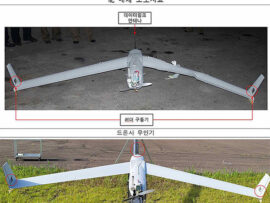なぜ、参政党が注目されているのか。同党は2022年の参院選で国政政党となり、その後の2024年衆院選では議席を伸ばし、日本政治の多党化の傾向の中で存在感を高めている。その支持拡大の背景には、従来の政党とは異なる独自の戦略があることが指摘されている。朝日新聞取材班は、参政党を「『右』に位置づけられるが、財政規律に目を向けないという点ではポピュリズム政党になる」と分析。財政出動に積極的な小政党の人気は、若年層から現役世代にかけて今後も高まる可能性があるとの見方を示している。
 参政党代表、神谷宗幣参院議員。
参政党代表、神谷宗幣参院議員。
参政党の選挙における伸長
参政党は2020年に小さな政治団体として発足したが、わずか2年後の2022年参院選で約170万票を獲得し、国会議員1名が誕生して国政政党となった。さらに、初の衆院選となった2024年では、公示前の1議席から比例区で3議席を獲得し、合計4名の国会議員を有する政党へと成長した。比例代表では南関東、近畿、九州の各ブロックで議席を得ている。この急速な伸長は、既存の政党支持層とは異なる新たな有権者層を取り込んでいることを示唆している。
独自のターゲット戦略:オーガニックとSNS
参政党の支持拡大の要因として、その巧妙なターゲティング戦略が挙げられる。ある政党の幹部経験者は、自身の妻がオーガニック食品に関心を持ち、Instagramで情報を調べている際に「参政党」の情報を頻繁に目にするようになったというエピソードを語っている。これは、党が特定の関心を持つ層、例えば化学合成農薬や肥料を使わない有機栽培に関心を持つ「オーガニック層」に対して、ソーシャルメディアを活用してピンポイントで情報を届けている実態を示唆している。
参政党は、保守的な政治メッセージだけでなく、ワクチン政策に対する懐疑的な見解や、食の安全・健康といったテーマを積極的に発信している。これらのテーマは、既存政党の枠組みでは十分に扱われてこなかった層、特に自然派志向を持つ層や、情報へのアクセスをソーシャルメディアに頼る若年・現役世代の関心を引きつけている。こうした層は一見ニッチに見えるが、潜在的なボリュームが多く、参政党は彼らの間で「自分たちの問題に関心を持つ政党」として支持を広げている。
注目度向上と今後の可能性
参政党の議員数が増加したことで、NHKの「日曜討論」のような主要なテレビ討論番組に出演する機会を得るようになった。これは、党の認知度と正当性を高める上で重要なターニングポイントとなった。かつては一部から「何だか変な宗教」のように見られることもあったが、メディア露出の増加により、より「きちんとした信仰(=政治的主張)」として受け止められる層が広がっている。
参政党代表の神谷宗幣参院議員の弁舌能力も、支持層を惹きつける要因の一つと見られている。これらの要素が相まって、党勢はさらに拡大する可能性を秘めている。前述の政党幹部経験者は、現在の勢いが続けば、参政党が将来的には共産党並みの議席数を獲得する可能性も十分にあると予言している。

参政党が自ら語る政党像
参政党の公式ホームページでは、自らを次のように紹介している。「『今の政治を変えなければ日本の未来が不安だ』と危機感を持った一般の人々が集まり『投票したい政党がないから、自分たちでゼロからつくる。』を合言葉に2020年に大企業や宗教団体などの支援のない小さな政治団体として発足」。そして、わずか2年での国政政党化、2024年衆院選での議席増を経て、現在では衆参合わせて4人の国会議員と140名の地方議員を擁し、全国の党員がボランティアで支える「小さいけれど力強い政党」であると説明している(2025年5月時点)。
この自己紹介は、既存の政治や政党に不満や不安を感じる人々が、自分たちの手で新しい選択肢を生み出したというストーリーを強調しており、無党派層や政治への関心が薄かった層にアピールする狙いがあると考えられる。大企業や団体に頼らない「草の根」の活動という側面も、既存政治への不信感を抱く層には魅力的に映る可能性がある。
まとめ
参政党の急速な台頭は、日本政治における新たな動きとして注目されている。その成功の鍵は、従来の政治的な左右対立の軸とは異なるテーマ(オーガニック、食の安全、ワクチンなど)を選び、ソーシャルメディアを巧みに活用して、これらのテーマに関心を持つ特定の層(若年層、オーガニック層、情報感度の高い層など)に深く浸透するターゲティング戦略にある。メディア露出の増加による認知度向上も追い風となり、その支持基盤は確実に広がりを見せている。今後、参政党が日本の政治情勢においてどのような役割を果たしていくのか、その動向が注視される。