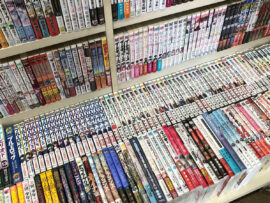昔から米の価格が急騰すると、庶民の間で一揆などが起き、時の政権が危機に瀕することは少なくなかった。江戸時代中期、特に老中・田沼意次の時代もまた、この問題に直面した。現代においても「令和の米騒動」と称される食料価格高騰が話題となる中、歴史における米価変動とその対策は、現代に通じる教訓を含んでいる。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、田沼意次が米価高騰に立ち向かう様子が描かれるが、その描写には史実との乖離があるという指摘がある。本稿では、江戸時代の米価高騰問題を、田沼意次とそれ以前の徳川吉宗の時代を中心に振り返り、現代の課題を読み解く一助とする。
大河ドラマが描く田沼意次と米価高騰
大河ドラマ「べらぼう」の予告編では、「米が、ない?」「おととしの米なら」といった台詞と共に、浅間山の大噴火による降灰と冷夏による不作が原因で米の値段が高騰する場面が描かれた。江戸幕府の要職にあった老中・田沼意次(渡辺謙)らは、この米価高騰への対策に追われる様子が描かれている。ドラマ内の意次は、商人たちに「米の値下げを命じよ」と指示するが、効果は薄く、有効な手立てを打てずに紀州徳川家の徳川治貞(高橋英樹)から叱責される。そして、ドラマでは最終的に、意次らは米問屋や仲買が売り惜しみをしないよう、米に関連する「株仲間」を廃止することで、この難局を乗り切ったとされる。しかし、筆者はこのドラマの描写、特に解決策とされる部分に大きな史実との乖離があると感じている。
「株仲間」とは何か? その公認の背景
この時代、幕府が米価対策や流通統制で重要な役割を担わせようとしたのが「株仲間」である。株仲間とは、端的に言えば商人や手工業者たちによる同業者の結合組織であり、幕府によって公認された特権的な団体を指す。同業者同士の集まり自体は古くから存在したが、これを株仲間として公式に認めたのは、8代将軍・徳川吉宗(1684〜1751年)による享保の改革期のことだった。幕府は株仲間を公認することで、特定の商工業者に対し営業の独占を認め、その代償として運上金・冥加金を徴収したり、物価統制や流通把握に利用しようとしたのである。
徳川吉宗時代の「米価安の諸色高」
徳川吉宗が株仲間を公認した享保期は、田沼意次の時代とは異なり、米の値段が非常に安い状態が続いていた。一方で、米以外の商品の価格は高く、「米価安の諸色高」と呼ばれる状況だった。幕府は年貢米を主な財源としていたため、米価が安いと年貢米を売却しても十分な収入が得られず、財政は苦境にあった。このため、「米将軍」として知られる吉宗は、新田開発や年貢増徴によって収入源である米を増やしつつ、米価を引き上げることに腐心したのである。現代から見れば信じがたいことだが、幕府財政のためには米価の上昇が必要だったのだ。幕府は物価全体を安定させ、特に奢侈品(しゃしひん)の流通を取り締まる目的もあり、株仲間を公認し、流通・商工業の統制を図ろうとしたのである。しかし、享保の飢饉が発生した1732〜33年の一時期を除けば、吉宗の努力にもかかわらず米価の安い傾向は続いた。
 米価高騰を象徴するイメージ画像
米価高騰を象徴するイメージ画像
田沼意次の直面した課題と歴史的な現実
徳川吉宗の時代とは異なり、田沼意次の時代には浅間山噴火などによる不作が重なり、深刻な米価高騰が発生した。ドラマでは意次が株仲間廃止によってこの危機を乗り越えたと描かれるが、これは史実を正確に反映しているとは言い難い。歴史上の田沼意次は、この米価高騰に対して有効な対策を打ち出すことができず、民衆の不満を高める一因ともなった。実際に株仲間が本格的に廃止されるのは、田沼時代が終わり、松平定信による寛政の改革期においてである。つまり、ドラマで描かれた「株仲間廃止による米価高騰解決」という筋書きは、田沼意次が行ったことではなく、また当時の危機を直接的に救った決定的な手立てでもなかった可能性が高い。「べらぼう」の予告編に見られるような米不足と価格高騰は、現実の田沼時代における厳しい状況の一端を捉えているものの、その解決策の描写は創作であると考えられる。田沼意次は、米価高騰だけでなく、当時の複雑な社会・経済情勢の中で、様々な改革を試みるも、多くの課題に直面し、有効な解決策を見いだせないまま失脚していくのである。
結論
江戸時代の米価高騰と、それに対する幕府の対応は、現代の食料価格変動問題を考える上で多くの示唆に富む。徳川吉宗が米価安に苦心し、株仲間を統制に利用しようとした一方で、田沼意次は米価高騰に対して決定的な手を打てなかった。大河ドラマが描く田沼意次の姿は、物語上の演出を含んでいる可能性が高い。歴史は、米という基幹作物の価格が、社会の安定にどれほど大きな影響を与えてきたかを物語っている。そして、為政者にとって、物価の安定がいかに難しく、常に直面する課題であったかを浮き彫りにしているのだ。現代の「令和の米騒動」もまた、歴史上の米価問題と同様に、気候変動、国際情勢、経済構造といった複雑な要因が絡み合って生じている。江戸時代の歴史から学ぶべきは、安易な対策では物価問題は解決しないという事実と、その困難さにどう向き合うかという姿勢なのかもしれない。
参考資料:
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7e3b4380138f692627332bb0d27259c4e5f9633