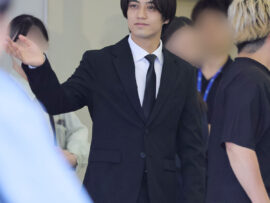朝食にソーセージ、昼は生姜焼き、夜は唐揚げ。気づけば毎食のように肉を食べている、そんな方は多いかもしれません。魚料理や野菜中心の食事も健康的と分かっていても、結局肉を選んでしまう。もし「肉がないとどうも物足りない」「満足できない」と感じるなら、それは「肉依存症」という状態に陥っているサインかもしれません。30万人以上の患者を診察した内科医、奥田昌子医師の新著『これをやめれば痩せられる』では、この肉依存症の危険性と、科学的根拠に基づいた対処法が解説されています。
 肉が食べられない時に物足りなさや強い欲求を感じる人のイメージ(肉依存症の可能性)
肉が食べられない時に物足りなさや強い欲求を感じる人のイメージ(肉依存症の可能性)
肉依存症とは?危険なサイン
数日間、肉を食べていないと、なぜかイライラしたり、落ち着かなくなったりする。どうしても肉が食べたくなり、深夜にコンビニでフライドチキンを買ってしまう、そんな経験はありませんか? 週に何度も焼肉に行く、食卓に肉がないと家族が不満そうにする、といった話は、程度の差こそあれ、身近な例かもしれません。これは、特定の食物に対して依存症に近い状態が発生している可能性を示唆しています。
脳内のメカニズム:なぜ肉がやめられないのか
私たちが何か嬉しい出来事を経験したり、期待以上の結果を得たりすると、脳からは「ドーパミン」という快感物質が分泌されます。「やった!」とガッツポーズが出そうになるのは、このドーパミンの働きによるものです。空腹時に血糖値が下がると、脳の奥にある「摂食中枢」が「食べろ」と指令を出します。通常、食事が進んで血糖値が上がれば摂食中枢の活動は落ち着きます。しかし、ここでドーパミンが分泌されていると、状況は一変します。ドーパミンは、摂食中枢をさらに無理やり刺激して食欲を異常に高めるだけでなく、食欲を抑制するホルモンである「レプチン」の働きを弱めてしまいます。さらに、「もう十分食べたからやめておこう」といった理性的な判断力までもが抑制されてしまうのです。これが、一度食べ始めると止まらなくなる、あるいは特定の食品(この場合は肉)への強い欲求が生まれるメカニズムの一つと考えられています。
健康への影響と「解毒」のヒント
このようなドーパミンによる食欲亢進メカニズムは、体重増加や肥満に繋がりやすいと考えられます。特に、肉類に多く含まれる動物性脂肪は、この依存的な食欲を助長する要因となり得ます。奥田医師の著作では、この動物性脂肪への依存に対する「解毒薬」となる食品についても触れられています。健康的なダイエットを目指す上で、自分の肉への欲求が依存症に近い状態かどうかを理解することは、最初の一歩となるでしょう。
結論として、もしあなたが肉を食べないと強い不満やイライラを感じるなら、それは単なる好みの問題ではなく、脳内のドーパミン分泌が関わる一種の依存状態かもしれません。このメカニズムを理解することは、健康的な食習慣を築き、特にダイエットを成功させる上で非常に重要です。自分の食欲と向き合い、科学的な知見に基づいたアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。