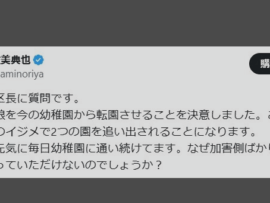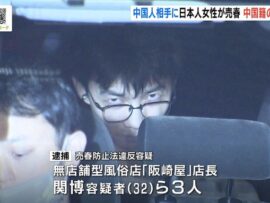今年の夏もプールシーズンが到来しました。しかし、多くの公立中学校で水泳の実技授業が行われず、「座学」に置き換えられるケースが増えています。これは、水泳が小学校から中学2年まで必修であるものの、必ずしもプールでの実習を伴う必要はないという現状を反映しています。この中学校での水泳授業の座学化には、いくつかの明確な理由があります。
 プールの脇で話を聞く生徒たち:中学校の水泳授業座学化を考える
プールの脇で話を聞く生徒たち:中学校の水泳授業座学化を考える
高額な維持コストが背景に
水泳授業が座学化される最大の理由は、学校プールの維持にかかる高額な費用です。使用期間は限られますが、水質管理などに年間数千万円単位のコストが必要となります。これは税金で賄われており、教育予算を圧迫しているとの声があります。例えば、バルセロナ五輪金メダリストの岩崎恭子氏の出身地である静岡県沼津市では、2025年度から市内18校中17校で実習を取りやめましたが、これも費用負担の大きさが主な理由です。
生徒・教員への負担とリスク
実技授業には、生徒の日焼けや熱中症リスクが伴い、最近では暑さ指数であるWBGTなどの指標による実施判断が必要です。また、プールの管理は教員の大きな負担となっています。地域によってはスイミングクラブを利用する学校もありますが、全国的に見るとまだ限定的です。
安全性への懸念と歴史的背景
そもそも水泳実習の必修化は、1955年に発生した紫雲丸沈没事故を教訓に、水難事故から身を守る能力習得のために始まりました。小中学生を含む168名もの尊い命が失われたこの事故を考えると、水に浮くなどの技術を座学だけで十分に習得できるのか、安全確保の観点から懸念の声があがっています。
1955年紫雲丸沈没事故:沈む船に助けを求める子供たち
「水泳ニッポン」の将来への影響
さらに、この流れは「水泳ニッポン」の将来にも影響を与えかねません。スポーツジャーナリストの折山淑美氏は、水泳は実体験が重要であり、座学だけでは未来のスイマーが育たないと指摘します。日本水泳連盟の鈴木大地会長は国民皆泳を目指すコメントを発表していますが、実技機会の減少は泳げない人(カナヅチ)増加に繋がる可能性が懸念されています。
このように、中学校での水泳授業の座学化は、財政的な問題や現場の負担軽減という側面から進められています。しかし、その一方で、国民の安全確保という水泳教育本来の目的や、将来的なスポーツ振興への影響など、重要な課題も浮き彫りになっています。今後の動向が注視されます。
出典:週刊新潮 2025年7月3日号, Yahoo!ニュース