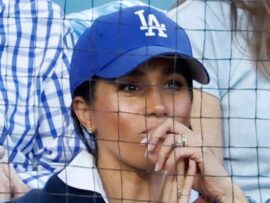クラウドコンピューティングの普及とAI技術の開発競争が激化する中、日本国内でもデータセンター(DC)の建設が急速に進んでいます。しかし、この際限ないDCの急拡大は、電力供給のひっ迫や、事業者と地域住民の間での新たな摩擦といった問題を引き起こしています。今、日本の各地域で何が起きているのでしょうか。現場の実態と課題を追います。
京都・精華町の「原則誘致しない」方針
京都、大阪、奈良の3府県にまたがり、数多くの研究機関や大学、文化施設などが集積する、関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)。緑豊かな丘陵地に位置するこの土地は、強固な地盤に加え、大規模な企業用地が存在していたことから、近年、関西地方におけるDC建設の適地として注目されてきました。
イギリスのColtデータセンターサービスが2023年に大規模DCを開設したほか、NTTグループ、関西電力とアメリカ企業の合弁会社などによる新たな巨大整備計画も複数判明しています。今年3月には、香港とアメリカの外資系プレイヤー同士が組む形でDCキャンパスの建設に着工しました。
とくに立地が集中しているとされるのが、京都府精華町内にある精華大通り周辺です。しかし、精華町としてはこのデータセンター建設ラッシュを歓迎していませんでした。
町は昨年9月、DC立地についての対応方針をまとめ、「今後、学研地区への新たな誘致は原則行わない」と宣言しました。「周辺環境との調和などを考えると、DCがたくさん集まるのは、学研都市としての街づくりの方向性とは異なる」(精華町の担当者)のが理由です。なお、街づくりへの大きな貢献が期待されるようなDCについては誘致できるとしています。

国内最大級の集積地、千葉・印西市の実情
データセンターをめぐる困惑やトラブルは、国内で最大規模のデジタルインフラ集積地も例外ではありません。約30棟のDCが稼働するとされる千葉県印西市です。
過去の印西におけるDCの立地状況を調べると、市内の土地が埋まりつつある状況がうかがえます。記者が市内各地を回って立地状況を確認したところ、DCの集積エリアは、大きく3カ所に分類することができます。
まずは、主に2010年代以降に整備が進んだとみられる大塚地域や、周辺の泉野地域。その北東部に位置する鹿黒南地域は、グーグルが2023年に開設した大型DCを筆頭に、外資系による開発が相次いでいます。
 千葉県印西市、千葉ニュータウン中央駅近くのデータセンター建設予定地と印西市長の見解を示す様子
千葉県印西市、千葉ニュータウン中央駅近くのデータセンター建設予定地と印西市長の見解を示す様子
3カ所目となる牧の台地域では、東京ドーム6個分に相当する広大な敷地で、大和ハウス工業による大規模DC拠点「DPDC印西パーク」の開発が進行中です。将来的に日本最大級のデータセンター拠点になると見込まれます。
まとめ
クラウドとAIの発展に伴うデータセンターの急増は、日本の各地域で電力や住民との摩擦といった具体的な問題を引き起こしています。京都府精華町のように新規誘致に原則歯止めをかける動きや、千葉県印西市のような既存の集積地での課題は、この技術インフラ拡大が持つ二面性を示しています。今後、国や地方自治体、事業者がいかにこれらの課題に向き合い、持続可能な発展を目指すかが問われています。
[参考] https://news.yahoo.co.jp/articles/ff0e980b520055b5aecc35e1d5ce7701f7c5da25