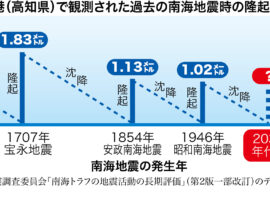2024年は統計開始以来、日本の観測史上最も暑い夏となりました。熱中症患者の急増に伴い、救急車への通報件数は過去最多を記録し、救急車不足が深刻な問題となっています。この「夏の悪夢」は、今後も繰り返される可能性が高い状況です。
救急車を巡っては、タクシー代わりに利用したり、税金の相談のために119番通報したりするなど、不要不急な通報の増加が社会問題化しています。東京大学医学部付属病院などで勤務していた医師である熊谷頼佳氏は、都市部で後期高齢者人口がさらに増加すれば、「無料で行われていた日本の救急搬送は破綻する」と警鐘を鳴らしています。日本は早晩、救急車の「限界」に直面すると考えられます。
救急車は「無料タクシー」ではない
マスコミは救急車のたらい回しを批判することが多いですが、本当に問題なのは、軽症であるにも関わらずタクシー代わりに救急車を利用したり、昼間に病院に行けないために救急外来を「コンビニ受診」のように利用したりする患者が多いことです。救急車は無料だと思っている人もいるかもしれませんが、その出動費用は税金によって賄われています。少し古いデータですが、東京都財務局が2004年7月に公表した資料によると、2002年度における救急車1回の出動にかかった費用は約4万5000円でした。20年以上前のデータであり、燃料費、人件費、物件費などが上昇していることを考慮すると、現在は7万~8万円程度かかっていてもおかしくありません。
膨らむ出動費用と悪質な利用例
東京消防庁には、夜中に50回も救急要請の電話をかけてきた高齢女性の記録が残っています。実際にコールセンターに残っていた録音テープを聞いた医師によると、その女性は明け方に最後の電話をかけた際、「もう眠くなったからいいよ」と言って電話を切ったそうです。このような事例は、救急システムが一部で深刻に誤解されている現実を示しています。
啓発活動の限界と増え続ける出動件数
総務省や厚生労働省は、救急車を呼ぶべきか迷った場合に、子どもは「#8000」、大人は「#7119」に電話で相談できることを啓発する活動を行っています。しかし、これらの相談窓口は十分に知られていないのか、救急車を呼ぶ人は増え続けています。総務省のデータによると、2022年度の全国の救急車の出動件数は約723万件に達し、前年と比較して約104万件(16.7%)以上の増加となりました。
 東京消防庁の救急車
東京消防庁の救急車
過去最長となった到着・搬送時間の実態
出動件数の増加に伴い、救急車が現場に到着するまでにかかる時間は平均10.3分となり、この20年間で過去最長を記録しました。また、搬送した患者を病院に収容するまでにかかった時間は平均47.2分で、この数値も過去最長となっています。
高齢者搬送の増加と病院受け入れの課題
2022年度中に救急搬送された人々の年齢構成を見ると、62.1%が高齢者(65歳以上)であり、そのうち24.4%は85歳以上の後期高齢者でした。高齢者が入院した場合、転院先が見つかりにくく長期入院になりやすいため、急性期病院は可能な限り受け入れを避けたいと考える傾向があります。病院に収容されるまでの時間が長くなっている背景には、このような事情も影響していると考えられます。
本当に緊急性の高い患者への影響
一刻を争うような緊急性の高い状況では、救急車の到着が10分以上かかることは命取りになる危険性があります。本当に緊急性の高い人々だけが救急車を適切に利用しているのなら、このような事態には陥らないはずです。現在の救急システムは、限界に近づいていると言えるでしょう。
結論
日本の救急医療システムは、不要不急な利用の増加、それに伴うコスト負担の増大、そして高齢者搬送の増加という複数の要因により、危機的な状況に瀕しています。出動件数は過去最多となり、現場への到着時間や病院への収容時間も過去最長を更新し続けています。このままでは、本当に救急車を必要とする命の危機に瀕した患者への対応が遅れる事態がさらに深刻化する恐れがあります。国民一人ひとりが救急車の適切な利用について再認識し、システムを持続可能なものとするための対策が喫緊の課題となっています。
参考文献
- Yahoo!ニュース (Source link)
- 熊谷頼佳 著『2030-2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』(中央公論新社)