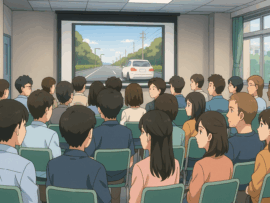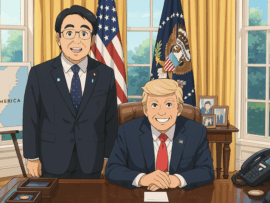歴史の授業で一度は耳にする「二・二六事件」。なぜ20〜30代の若き陸軍青年将校たちは「昭和維新」という過激な理想を掲げ、政府転覆を企図したクーデター計画を実行に移したのでしょうか。この事件は、単なる軍隊内部の騒動に留まらず、日本近代史における重大な転換点となりました。ここでは、その背景と事件の概略を見ていきます。
日本近代史の転換点:二・二六事件の概観
昭和11年(1936年)2月26日に発生した二・二六事件は、陸軍内で国家改造運動を推進していた一部の青年将校たちが起こした未遂のクーデターです。約20人の青年将校に率いられた下士官や兵約1500人が参加した、極めて大規模な行動でした。
近代日本の陸軍史において、これほど多数の兵士が参加したクーデター未遂事件は他に例がありません。明治11年(1878年)の竹橋騒動もクーデター未遂とされますが、その政治的影響や行動の徹底さという点では、二・二六事件とは比較になりません。この事件は、陸軍内部の抗争という枠を超え、日本の針路を決定づけるターニング・ポイントとなったのです。
 二・二六事件発生、半蔵門付近を行く決起部隊の兵士たち
二・二六事件発生、半蔵門付近を行く決起部隊の兵士たち
昭和11年2月26日の襲撃:要人たちの運命
昭和11年2月26日未明、東京は30年ぶりの大雪に見舞われました。その降り積もる雪の中、東京の麻布に駐屯する歩兵第一連隊と歩兵第三連隊、そして近衛師団歩兵第三連隊などに所属する約1500人の下士官・兵士たちが、20人ほどの青年将校に率いられ、午前5時を期して政府の要人宅を襲撃しました。
彼らが狙ったのは、岡田啓介首相官邸、鈴木貫太郎侍従長邸、斎藤実内大臣私邸、渡辺錠太郎陸軍教育総監私邸、高橋是清蔵相私邸、牧野伸顕前内大臣私邸といった、当時の政権中枢を担う人物たちでした。この襲撃により、斎藤実内大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監、高橋是清蔵相の三名が惨殺されました。
永田町の占拠と青年将校たちの要求
要人襲撃と並行して、決起部隊は永田町一帯も占拠下に置きました。決起将校の中核メンバーである香田清貞、丹生誠忠、村中孝次、磯部浅一、栗原安秀らは陸軍大臣官邸に集結し、川島義之陸軍大臣に対し「蹶起趣意書」(けっきしゅいしょ)を読み上げるとともに、自分たちの七項目にわたる要望事項を突きつけました。
要望の第一項では、陸軍大臣が事態を収拾し、昭和維新の実現に向けて邁進することを謳い、第二項以下では皇軍(こうぐん:天皇陛下の軍隊、つまり陸軍内部)同士の武力衝突を避けることなどを強く要求しました。彼らの目的は、これらの要望を受け入れる形で、軍主導による新内閣、特に青年将校たちに同情的な姿勢を示していた真崎甚三郎元教育総監や荒木貞夫元陸軍大臣を中心とする、いわゆる「天皇親政内閣」を樹立することだったのです。
彼らの「昭和維新」の理想は、一部の政府要人を排除し、天皇中心の軍事政権を樹立することで国家を刷新しようというものでしたが、結果としては日本の政治情勢を一層不安定化させ、軍部の台頭を決定的にする一歩となりました。
参考文献
- 保阪正康『昭和陸軍の研究 上』朝日文庫
- シリーズ20世紀の記憶『満洲国の幻影』(毎日新聞社 平成11年発行)