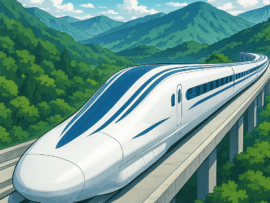[ad_1]
医療は日々進歩し続けているはずなのに、それでも「医療の未来はバラ色」とは言えそうにないのが日本の現状です。
患者が医師の説明に不安を抱えるケースは後を絶たず、さらには世界でも類を見ないほど手厚い日本の「高額療養費制度」も、今、制度の破綻が危ぶまれています。
こうしたことが起こってしまう背景には何があるのか。現場の医師として警鐘を鳴らしているのが、里見清一氏の『患者と目を合わせない医者たち』です。
同じく医師で作家の久坂部羊氏も、その内容に深く共感した一人。そこに書かれた「不都合な真実」と、患者側もそれを知らなければならない理由とは? 医療の現実を知るための「苦くて痛い良書」だという同書について、久坂部さんの書評をご紹介します。
がんの専門医だからこそ
本書のタイトルから思い浮かぶのは、診察室でパソコンに向き合い、CTや血液検査の結果ばかりに集中して、患者の身体に触れもしない現代の医者たちだろう。正しい診断を下すには、患者さんと目を合わすより、データをしっかり見るほうが重要というのが医者の言い分だが、患者さんはそれでは満足しない。患者さんは病気の不安を抱えていて、医者に人間的な救いを求めているからだ。
本書には、「医の中の蛙」というタイトルで、「週刊新潮」に2022年4月から2024年12月までに掲載されたエッセイの中から選ばれたものがまとめられている(連載は今も継続中)。
著者の里見清一氏は、現在、総合医療センターの化学療法科部長で、主に肺がんの治療を専門にしている。国立がんセンターでの勤務経験もあり、抗がん剤治療のエキスパートでもある。にもかかわらず、というか、だからこそ、医療の矛盾や不条理を描いた一般向けの著書も多い。それは医療を貶めたり、世間を不安に陥れたりするためではなく、医療を持続可能なものにするための警鐘として書かれたものだ。
従って本書にも、“不都合な真実”や“つらい現実”が、ふんだんに紹介されている。
[ad_2]
Source link