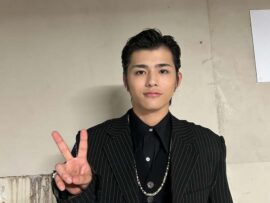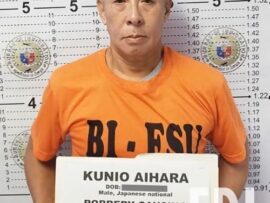心身ともに疲弊する親の介護。そして介護の後にしばしば待ち受けているのが、遺産相続をめぐる兄弟姉妹間の問題です。介護への貢献は往々にして特定の一人に偏りがちですが、中には介護に全く関わらなかった兄弟が、遺産相続だけはきっちり要求するというケースも少なくありません。「介護からの逃げ得は許せない」と感じる家族がいる一方で、実はこの「逃げ得」が法的に成立しやすい側面があるのが現実です。
介護「逃げ得」はなぜ容易なのか
親の介護からの「逃げ得」を法的に阻止するのは、実は非常に困難を伴います。むしろ、介護から逃れること自体は、現在の日本の法律や裁判所の実務の方向性から見て、比較的容易に行えてしまう傾向にあります。これは、介護への貢献、特に日常的な世話が、法的に「特別な寄与」(寄与分)として認められにくいことに起因しています。つまり、どれだけ尽くしてもそれが相続分に反映されるとは限らないため、「何もしない」という選択が法的な不利益に繋がりにくい構造があるのです。
巧妙な「逃げ得」のための具体的な行動
介護から巧みに逃れるためには、いくつかの具体的な行動パターンが見られます。これらは、責任を回避しつつ、将来の相続において自身の立場が悪くならないようにするための戦略と言えます。
一つは、親に介護が必要になった際に、参加できない理由を次々と並べ立てることです。仕事が多忙、自身の子供の世話が大変、夫婦関係の問題、健康上の不安など、本当であるかに関わらず、とにかく物理的・精神的に介護に関わる余裕がないと主張します。特に、介護保険の手続きやケアプラン決定におけるキーマン(中心となる家族)の打診があった場合も、強く拒否し続けます。キーマンになると無償で重い責任を負うため、「なりたくてもなれない」と主張することで、ケアマネージャーもそれ以上押し付けられなくなります。
 高齢者を介護する家族のイメージ。親の介護は肉体的精神的に負担が大きい。
高齢者を介護する家族のイメージ。親の介護は肉体的精神的に負担が大きい。
また、他の兄弟姉妹に対しては、「申し訳ない」「恩に着ます」といった言葉で口頭での謝罪やお礼を伝えます。しかし、後々証拠となるメールや書面でのやり取りは極力避けます。これにより、謝罪や感謝の意思は示したという建前を作りつつ、介護への不参加の証拠を残さないようにします。
さらに、時間がある際に、手土産を持って親の介護を引き受けている兄弟の元を訪れたり、親が入院したと聞けば見舞いの花を持って病院に行ったりといった行動をとります。こうした訪問や見舞いといった最低限の外形的な行動をとっておくことで、後々裁判になった場合に「介護を手伝う意思はあった」「全く無関心ではなかった」と申し開きをするためのアリバイ作りとすることができます。介護の具体的な貢献度を法的に立証するのは難しいため、このような形式的な行動が、100対0という評価を避ける上で有効となるのです。
死ぬ前の「相続放棄」の欺瞞
「逃げ得」を図る上での、より巧妙で、かつ法的な知識の隙間を突くような手段として、「自分は親の相続財産について全て放棄する」と他の兄弟姉妹に公言するというものがあります。これは口頭だけでなく、書面に署名捺印(実印を含む)をして他の兄弟姉妹に差し入れる場合もあります。このような書面を示すことで、「相続を放棄するとまで言っているのだから、介護を任せても仕方ない」と他の兄弟に受け止めさせ、自身は介護から完全に逃れるという狙いです。
しかし、日本の民法において、親が亡くなる前に行う「相続放棄」の意思表示には、いかなる形式であっても全く法的な効力はありません。たとえ厳かな書面を作成し、実印を押したとしても、法律上は単なる紙切れとして扱われます。相続放棄は、親が亡くなった後に、家庭裁判所に申述して初めて認められる法的手続きだからです。したがって、このような書面を差し入れて介護を逃れたとしても、親の死後には堂々と相続権を主張することが法的に可能となってしまうのです。道義的には大きな問題がありますが、法律的にはこの欺瞞が通じてしまうのが現状です。
結論
親の介護における「逃げ得」は、介護負担が偏在しやすい家族の現実と、貢献度を法的に厳密に評価しにくい現行制度の狭間で生じやすくなっています。最低限の外形的な行動でアリバイを作り、法的に無効な意思表示を巧みに利用するといった手法が存在することも、その背景にあります。介護を一身に引き受けた家族の貢献が報われにくいという、相続における不公平感は、多くの家庭で深刻な問題を引き起こしています。
出典:姉小路 祐『介護と相続、これでもめる!不公平・逃げ得を防ぐには』(光文社)