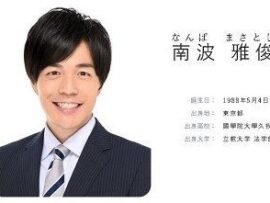参院選が迫り、「消費税減税」を巡る議論が活発化する中、その中身が一向に深まらないという指摘があります。これは、メディア、ジャーナリスト、さらには政治家に至るまで、消費税に対する基本的な理解が欠如しているためだと言われています。特に根強く、そして巧妙に広まっている誤解は、「消費税を減税すると社会保障費が減る」という言説です。この〝ウソ〟が30年近くもつき続けられているという事実は、日本の財政議論の深刻な課題を浮き彫りにしています。
「社会保障の重要な財源」という政治家の発言は誤りか?
参院選を控え、消費税減税を掲げる野党に対し、政府・自民党はこれを阻止しようとする姿勢が目立ちます。例えば、自民党の森山裕幹事長は「消費税は社会保障の重要な財源。命を懸けて守る」と述べ、石破茂氏も同様に「社会保障の財源なので減税はしない」と明言しています。テレビの情報番組などでも、元政治家コメンテーターが「消費税の減税は社会保障費の減少につながるから反対」と主張する光景がしばしば見られます。これらの発言は、あたかもポピュリズムに与しない「正論」として、一般的にマスメディアで好意的に受け止められがちです。
しかし、こうした数々のコメントは、消費税の本質的な理解不足を露呈しているに過ぎません。これまで、少なくとも政治家は真実を知っているはずだと考えられてきましたが、そうではない可能性も出てきています。石破茂氏は自民党全国幹事長会議で、消費税減税について「金持ちほど減税になるので、格差が広がる」と批判したと報じられました。このコメントに対し、東大大学院の政治学教授が「標準的な租税理論では、消費税は低所得者の負担が重い『逆進課税』とされる。したがって、消費税減税の恩恵は高所得者よりも低所得者のほうが大きい」と的確な指摘をしています。このような初歩的な誤解をしているようでは、消費税減税がそのまま社会保障費の減少に直結すると本気で考えていても不思議ではありません。
 石破茂氏、消費税の逆進性に関する議論で発言
石破茂氏、消費税の逆進性に関する議論で発言
消費税が「社会保障目的税」だと誤解される根深い理由
では、なぜ多くの人々が消費税減税によって年金、医療、介護、少子化対策といった社会保障費が減少すると考えてしまうのでしょうか。その理由は極めて単純で、消費税の税収がすべて社会保障費に充てられていると〝思い込んでいる〟からです。
この思い込みには、確かな根拠が存在します。2012年、当時の民主党政権下で、消費税率の引き上げと使途の明確化を目指した「税制抜本改革法」が成立しました。この法律により、国の歳入分である「国分」の消費税収の使途について、全額を社会保障4経費(年金、医療、介護の社会保障給付、および少子化対策費用)に充てることが決定されたのです。
これがいわゆる「社会保障と税の一体改革」であり、その内容は『消費税法1条2項』にも追記されています。これをもって、消費税が8%に引き上げられた2014年4月以降、消費税は「社会保障目的税化」され、使途が明確化されたとされています。この「社会保障目的税化」という表現が、消費税収が全額社会保障費に充てられているという強い印象を与え、誤解の最大の根拠となっていると言えるでしょう。
目的税と普通税:消費税が「正式な目的税」になれない構造的理由
一見すると、消費税収がすべて社会保障費に充てられていると考えることに問題はなさそうですが、これは巧妙に仕組まれた〝洗脳〟と捉えるべきです。
社会保障と税の一体改革で消費税が「社会保障目的税化」されたと述べましたが、これは消費税が「社会保障目的税」になったことと同義ではありません。「化」という一文字が付くか付かないか、字面上のわずかな差ですが、意味するところは大きく異なります。
この辺りの事情を正しく理解するためには、まず租税における「普通税」と「目的税」について説明が必要です。租税法の泰斗として知られる故金子宏氏の『租税法』には、「使途を特定せず一般経費に充てる目的で課される租税を普通税と呼び、最初から特定の経費に充てる目的で課される租税を目的税と呼ぶ」と記されています。
この定義に照らし合わせれば、消費税は社会保障目的税として適切であるように思えますが、実際には消費税は目的税とはなっていません。所得税や法人税、相続税、贈与税などと同じ「普通税」に分類されます。
もし本当に消費税収をすべて社会保障費に使うのであれば、正式な「社会保障目的税」にすれば、使途が明確になり、国民の理解も深まるはずです。しかし、「社会保障と税の一体改革」では、あくまで「社会保障目的税〝化〟」にとどまり、「社会保障の財源にする」という表現が用いられました。
なぜでしょうか?結論を先に言えば、消費税収は実際には一般財源として、国債の償還費や防衛費など、多岐にわたる他の経費にも使われているからです。この実状があるため、消費税を「目的税」としてその使途を特定・限定することができないというのが、現在の日本の財政における真実なのです。
結論:消費税の本質理解が健全な政策論争の鍵
これまで30年近くにわたり続いてきた消費税を巡る「誤解」は、その本質を正しく理解することで払拭できます。消費税は社会保障の財源の一部ではあるものの、その使途は国債償還費や防衛費など多岐にわたり、決して全額が社会保障に限定される「目的税」ではありません。国民一人ひとりがこの事実を認識し、政府や政治家も正しい情報に基づいて議論を深めることこそが、より健全で透明性の高い財政・社会保障政策の実現に不可欠と言えるでしょう。この理解こそが、感情論ではない建設的な未来志向の政策論争への第一歩となります。
参考文献:
- Yahoo!ニュース: 「30年近く続いている『ウソ』!?」 石破首相も「消費税」を理解していない!?, FRIDAYデジタル, 2024年7月17日掲載