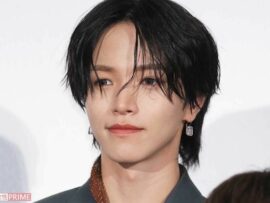北海道は、その広大な面積ゆえに、列車での移動距離も本州とは大きく異なります。特に都市間を結ぶ特急列車は、その走行距離の長さが際立っています。本記事では、北海道の主要な特急列車の走行距離を本州の特急列車や新幹線と比較し、そのスケール感を浮き彫りにします。日本の鉄道網における北海道特急列車の特異性について深く掘り下げていきましょう。
短距離特急:本州の主要路線に匹敵
北海道の定期特急列車の中で比較的走行距離が短いのは、札幌~旭川間を結ぶ「ライラック」と「カムイ」、そして札幌~室蘭間を結ぶ「すずらん」です。これらの走行距離は、「ライラック」および「カムイ」が136.8キロ(営業キロ)、「すずらん」が136.2キロとなっています。この距離は、本州の主要な特急列車と比較しても一般的な範囲内です。
具体的には、新宿~甲府間を走る「かいじ」(123.8キロ)、東京~安房鴨川間などの「わかしお」(132.5キロ)、大阪~敦賀間を走る「サンダーバード」(136.9キロ)などが、これに近い走行距離を有しています。新幹線で比較すると、東海道新幹線の東京~新富士間(135.0キロ、実キロ)がこの距離帯に相当し、北海道の短距離特急も都市間輸送の重要な役割を担っていることがわかります。
中距離特急:本州では「そこそこ長い」部類
次に、札幌~帯広間を結ぶ特急「とかち」は、走行距離が220.2キロです。北海道の特急列車の中では中程度の距離に位置しますが、本州の感覚からすると、かなりの長距離列車に匹敵します。
本州の特急列車で比較すると、新宿~松本間を走る「あずさ」(225.1キロ)、品川~いわき間を結ぶ「ひたち」(222.0キロ)、岡山~出雲市間を走る「やくも」(220.7キロ)などが、「とかち」と近い走行距離です。東海道新幹線の駅間でいえば、東京~掛川間(211.3キロ)に相当する距離であり、北海道内での移動距離の大きさが改めて浮き彫りになります。
北海道の誇る長距離特急:300キロ超えが常態
札幌駅を発着するその他の都市間特急列車は、いずれも走行距離が300キロを超え、その圧倒的なスケールを示しています。札幌~函館間の「北斗」は318.7キロ、札幌~釧路間の「おおぞら」は348.5キロ、札幌~網走間の「オホーツク」は374.5キロ、そして札幌~稚内間を結ぶ「宗谷」は驚異の396.2キロに達します。
2025年現在、日本国内を走る昼行在来線特急列車で走行距離が300キロを超えるものは8つ存在しますが、そのうち4つが北海道の列車であることは特筆すべき点です。これは、北海道の広大さと、鉄道が果たす役割の大きさを物語っています。
東海道新幹線と比較すると、東京~名古屋間が342.0キロであり、「宗谷」の走行距離はこれを上回ります。具体的には、396.2キロという距離は、東海道新幹線の岐阜羽島駅を超え、米原駅の手前にまで達する距離です。東海道新幹線「ひかり」が東京~米原間を2時間強で走破するのに対し、これに近い距離を走る特急「宗谷」は、札幌~稚内間を約5時間12分かけて走行しており、在来線ならではの所要時間の長さも特徴です。
 札幌駅を発車し旭川へ向かう特急「ライラック」の流線形の車両。北海道の広大な大地を走るJR北海道の特急列車の中でも、比較的走行距離が短い区間を結ぶ代表的な列車の一つ。
札幌駅を発車し旭川へ向かう特急「ライラック」の流線形の車両。北海道の広大な大地を走るJR北海道の特急列車の中でも、比較的走行距離が短い区間を結ぶ代表的な列車の一つ。
国内最長距離の在来線特急と新幹線
参考までに、国内を走る昼行在来線特急列車で最も走行距離が長いのは、博多~宮崎空港間を走る「にちりんシーガイア」で413.1キロです。在来線全体で見ると、寝台特急「サンライズ出雲」(東京~出雲市間、953.6キロ)が最も長い距離を走る旅客列車となります。さらに旅客列車全体で比較すると、東海道・山陽新幹線を直通する東京~博多間の「のぞみ」(1069.1キロ)が日本で最も長い距離を走る列車です。
これらの比較からも、北海道の特急列車がその地理的特性により、いかに長距離を運行しているかが明確になります。北海道の鉄道は、単なる移動手段としてだけでなく、その広大な大地を結びつける重要な動脈として機能していると言えるでしょう。