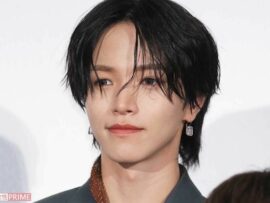2024年12月23日に経営統合協議の開始が発表されたホンダと日産。しかし、わずか2カ月足らずの今年2月13日には協議打ち切りが公表され、「世界3位の自動車会社」誕生の夢はあっけなく幻と消えました。しかし、両社の戦略的な連携は水面下で生き続け、ここへきて分野単位での提携、いわゆる“連合”への動きが加速しています。これは、経営統合破談後も、両社が直面する経営課題と急速に変化する外部環境への対応策を模索する中で、互いの弱点を補完し合う必要性が浮上しているためです。
統合協議破談の裏で加速する生産・開発の協業
ホンダと日産の間で具体化しつつあるのは、まず生産補完に関する協議です。例えば、米国におけるトランプ関税の逆風に対応するため、日産が米国キャントン工場で生産するピックアップトラックをホンダに供給する検討が進められています。これは、米国市場での足場固めを目指すホンダにとって、これまで弱点だったピックアップトラック分野を強化する上で重要な一手となります。また、日産にとっても、工場稼働率の低さという長年の課題を解決する一助となる可能性があります。
さらに、次世代車開発の基盤となるソフトウェア面での協業も前進しています。両社が基盤ソフトウェアを共通化する方針が報じられるなど、SDV(ソフトウェア定義車両)開発における協業のメリットは計り知れません。知能化が自動車産業の「本命」とされる中で、この分野での連携は、莫大な開発コストの分担だけでなく、技術的なシナジーを生み出し、競争力を高める上で極めて重要です。
 日産とホンダの経営統合協議発表記者会見での内田誠氏(左)と三部敏宏氏。戦略的提携の背景を示す象徴的な一枚。
日産とホンダの経営統合協議発表記者会見での内田誠氏(左)と三部敏宏氏。戦略的提携の背景を示す象徴的な一枚。
両社が抱える経営課題と連携の不可欠性
今回の戦略的連携強化の背景には、ホンダと日産それぞれが抱える深刻な経営課題があります。
日産は、現経営体制の下、背水の陣で大規模なリストラを断行できるかが喫緊の課題となっています。既に、追浜工場の2027年度末での生産終了や、日産車体・湘南工場の2026年までの生産終了が発表されており、これは経営再建に向けた苦渋の決断です。特に、国内工場の閉鎖は地元経済に不安を募らせていますが、日産が自力で経営再建を成し遂げられるかどうかは、ホンダとの連携の成否にも大きく影響します。日産の経営陣は、工場の稼働率改善に向けた北米市場での連携や生産効率化に関する協議を進めていることを示唆しており、その具体的な方策の一つがホンダへの車両供給というわけです。
一方、ホンダもまた、複数の課題を抱えています。八郷隆弘前社長体制下で英国・トルコの海外工場と国内の狭山工場などの閉鎖による再編を決断したものの、依然として低収益の四輪事業を、稼ぎ頭である二輪事業で支えるという構造的な弱点を抱えています。かつての稼ぎ頭であった中国事業が大きく後退する中、もう一つの主要収益源である米国市場も、トランプ関税の影響により安泰とは言えない状況です。
さらに、三部敏宏社長体制下では、米ゼネラル・モーターズ(GM)との戦略提携を推進したものの、量販EVの共同開発や自動運転での取り組みも断念するなど、期待された成果が出ていません。直近では、三部社長の片腕と目された青山真二前副社長がスキャンダルで失脚し、経営陣の立て直しも迫られています。ホンダにとって米国は、かつて「アメホン(米国ホンダ)一本足打法」と称されるほどの最大収益市場であり、中国市場の急速な回復が難しい現状において、ハイブリッド車(HV)の拡販などをはじめとする米国での足場固めは喫緊の課題です。その中で、ピックアップトラックの供給は、米国市場の強化に直結します。
戦略的パートナーシップの将来展望
ホンダと日産、両社のトップの思惑が一致したのは、「経営統合」は白紙にしたものの、昨年夏以来継続している「戦略的パートナーシップ」の連携を強化し、それぞれの経営上の“弱点”を克服して生き残りを図るという点にあります。急速に変化する自動車産業の外部環境と、各社が抱える内部的な課題を乗り越えるため、生産や開発といった具体的な分野での協業は、単なるコスト削減を超えた戦略的な意味合いを持ちます。
世界的な経済情勢の不確実性や技術革新の加速が続く中、両社がそれぞれの強みを持ち寄り、弱点を補完し合う形で協力関係を深めることは、持続的な成長に向けた不可欠なステップとなるでしょう。この戦略的連携が、日本の自動車産業、ひいては世界のモビリティの未来にどのような影響を与えるか、今後の動向が注目されます。