「日本人ファースト」を掲げ、今回の参議院選挙で一躍注目を集めた参政党。なぜ彼らはこれほどまでに票を伸ばすことができたのでしょうか。特に注目すべきは、意外なことに女性からの支持を集めた点です。
参院選で巻き起こったこの“参政党現象”は、その過激とも評される発言の数々が話題となりました。中でも神谷代表の発言は大きな波紋を呼びました。
神谷代表の「過激な発言」とその波紋
参政党の神谷代表は、選挙中に次のような発言をし、大きく賛否を分けました。
「今まで間違えたんですよ、男女共同参画とか。もちろん女性の社会進出はいいことです。どんどん働いてもらえば結構。けれども、子どもを産めるのも若い女性しかいない。これ言うと差別だという人がいますが違います、現実です。男性や、申し訳ないけど高齢の女性は子どもが産めない。だから、日本の人口を維持していこうと思ったら、若い女性に子どもを産みたいなとか、子どもを産んだほうが安心して暮らせるという社会状況を作らないといけないのに、働け、働けとやりすぎちゃった」
この発言は、女性の役割を「出産」に限定するような印象を与え、批判が集中しました。しかし、この選挙中の発言について「なぜ反発を招いたと思うか」と問われた神谷代表は、以下のように反論しています。
「それが正しいと思う人が結構いたからではないでしょうか。私は訂正する気も謝罪する気も一切なくて、当たり前のことをしっかり問題提起した。国会も引き続き同じテーマで訴えていきたい」
神谷代表は自身の発言が現実を述べたものであり、撤回や謝罪の必要はないとの立場を崩していません。
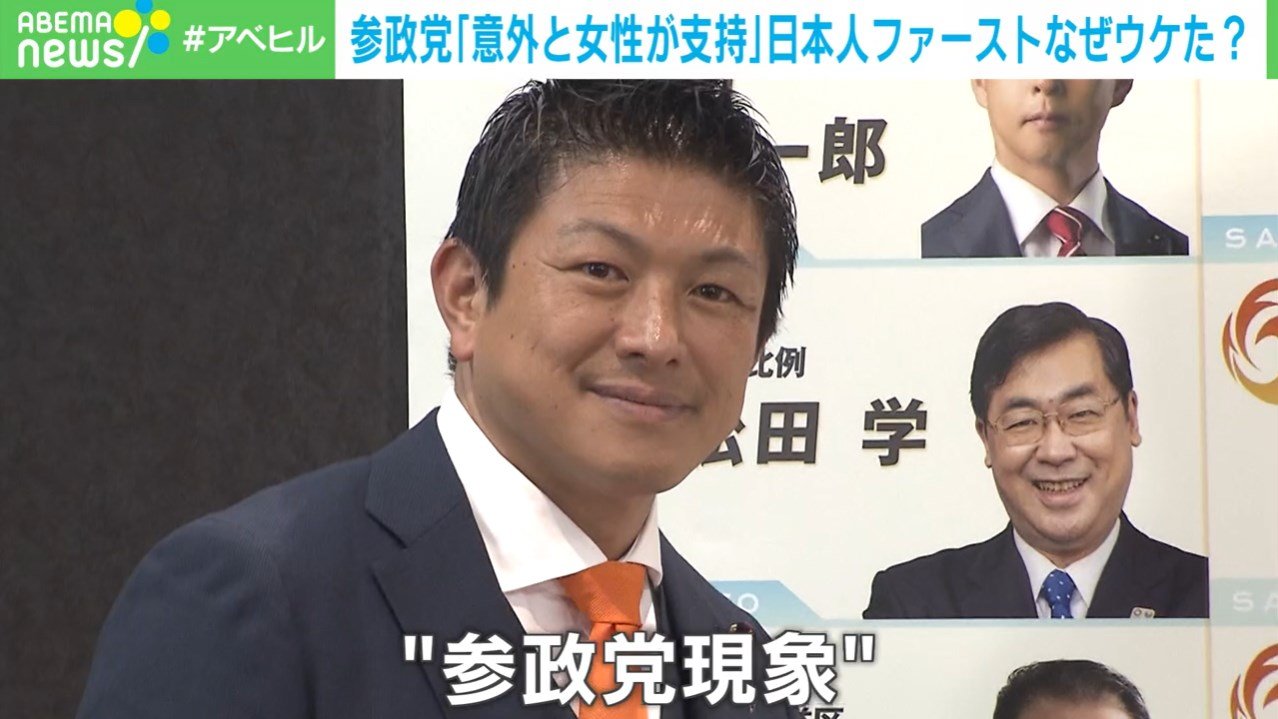 参議院選挙で躍進した参政党の神谷宗幣代表。その発言が注目を集めている。
参議院選挙で躍進した参政党の神谷宗幣代表。その発言が注目を集めている。
女性支持の「意外な」背景とは?ジャーナリストの分析
参政党の主張が性別役割分業を肯定的に捉える傾向にあることから、当初、女性からの支持は低いと予測されていました。しかし、比例区政党の投票先を男女別で見ると、参政党の女性割合は他の政党と比較して極端に低いわけではありません。国民民主党やれいわ新選組との差はわずか1ポイントに留まっています。
この結果に対し、ジャーナリストの浜田敬子氏は、意外な印象を受けたと語ります。
「参政党は男性が稼ぎ、女性が家事育児をするものという性別役割分業を固定化、強化するような発言をしているので、もっと女性からは支持されないと思っていたら、意外と女性が支持していた」(ジャーナリスト・浜田敬子氏)
浜田氏がそう感じたのは、選挙最終日の街頭演説の様子でした。神谷代表の芝公園での演説には、前回とほぼ同数の人が集まったものの、今回の特徴は女性が増えたことだと指摘します。実際に、参政党が擁立した55人の候補者のうち、女性が24人と、他の政党と比べても高い割合でした。
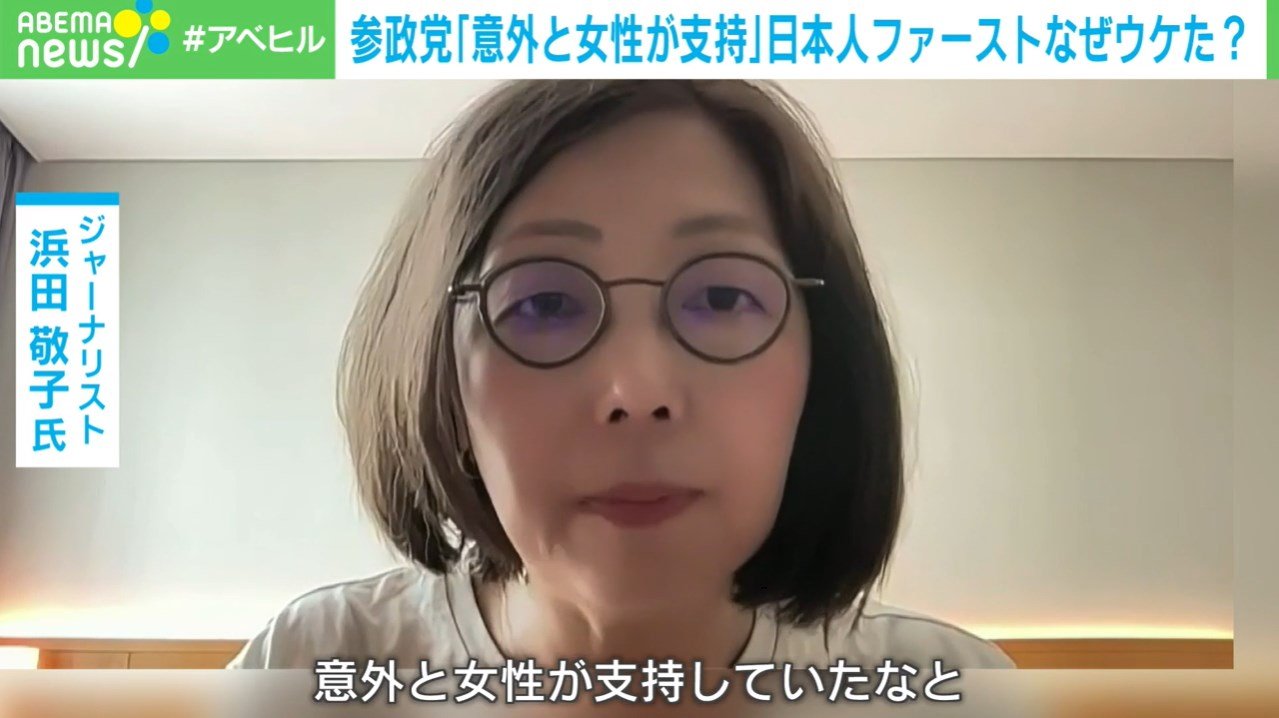 参政党への女性支持を分析するジャーナリストの浜田敬子氏。独自の視点からその背景を探る。
参政党への女性支持を分析するジャーナリストの浜田敬子氏。独自の視点からその背景を探る。
ジェンダー観の多様化:女性票の新たな様相
浜田氏はこれまで、女性政治家が増えることで選択的夫婦別姓などジェンダー平等に関する政策が推進されることを期待していました。しかし、今回の選挙で明らかになったのは、単純に男女という二元論で語れなくなったという現実です。
「女性でも極右的な思想を持っている人もいるし、選択的夫婦別姓などジェンダー平等政策に慎重、後ろ向きな人もいることが今回はっきりした。参政党は子育てに専念したい女性に一見寄り添うような姿勢を見せているが、女性の味方なのかということはちゃんと見極めたほうがいい。『高齢の女性は子どもが産めない』という言葉に象徴されるのは、結局女性は子どもを産むことが第一義的な役割だという考え方が、彼らには根強くある。彼らの思想は、基本的には性別役割分業、男性が稼ぎ、女性が家事・育児をするという、時代を逆行させる思想だと思う」
この分析は、現代の女性有権者が多様な価値観を持ち、必ずしも一方向の「ジェンダー平等」に賛同するわけではないという複雑な実態を示しています。参政党の「子育てに専念したい女性に寄り添う」姿勢が、一部の女性にとって魅力的に映る一方で、その根底にある性別役割分業の思想は、ジェンダー平等を推進する動きとは逆行するものです。
結論
参議院選挙における参政党の躍進、特に女性からの意外な支持は、日本の政治における有権者の意識、特にジェンダーに関する考え方の多様化を浮き彫りにしました。神谷代表の発言とその支持層の反応は、一見矛盾しているようにも見えますが、これは現代社会に潜む様々な価値観の存在を示唆しています。今後の日本の政治において、このような多様な視点を理解し、議論を深めていくことが求められるでしょう。
参考資料
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/2e528b690ab3524d6899dc0d8d987e2f231f5c15






