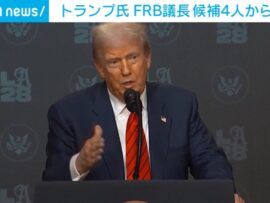医師であり作家の久坂部羊氏は、長年にわたり、自ら死を選ぼうとする人々の心の奥底にある葛藤と向き合ってきました。命をめぐる決断の背景にはどのような「思い」があるのか、生と死の狭間にある繊細な心理が丁寧に紐解かれます。特に、日常生活に支障をきたすほどの「死の恐怖」は、時に精神疾患と見なされることがあります。本稿では、その具体的な状態と、人が「死」にどう向き合うかについて深掘りします。
日常生活に影響を及ぼす「死恐怖症(タナトフォビア)」とは
死への恐怖が極度に高まり、それが日常生活に深刻な支障をきたすようになると、それは「死恐怖症(タナトフォビア)」という精神疾患として扱われ、治療が必要となる場合があります。「タナト」はギリシャ神話の死の神「タナトス」に由来し、「フォビア」は古代ギリシャ語で恐怖を意味する「ポボス」から来ています。
この死恐怖症は、元々繊細な人や神経質な傾向がある人が、身近な人の死に直面したり、事故や災害による大規模な死のニュース、あるいは現実感あふれる映画やドラマなどを通じて「死」を強烈に感じた際に発症しやすいとされています。
この状態に陥ると、今すぐ死ぬわけではないにもかかわらず、死の恐怖が頭から離れず、他のことに手がつかなくなります。強い不安、不穏、不快感によって心理状態が不安定になり、身体的にも動悸、発汗、口渇、震えといった症状が現れることがあります。子ども時代に夜布団の中で死について考え、漠然とした不安に襲われて叫びそうになった経験がある人もいるかもしれませんが、それが日常生活に恒常的な影響を及ぼすほどであれば、死恐怖症の可能性があります。
 「死の恐怖」や「生と死のはざまにある心理」を象徴するイメージ。人が深く思考している様子。
「死の恐怖」や「生と死のはざまにある心理」を象徴するイメージ。人が深く思考している様子。
死体への恐怖「ネクロフォビア」とメディアの役割
死恐怖症に似た概念として「死体恐怖症(ネクロフォビア)」があります。これは死体そのものや、墓、葬儀、棺など死を連想させるものに対して極度の恐怖を抱く状態で、これもまた死恐怖症と同様に日常生活に支障を来すことがあります。
日本のメディア、特に公共放送では、死体の映像は厳しく自主規制されており、鮮明に映し出されることはほとんどありません。歴史的な写真などで死体が映る場合でも、視聴者への事前警告が流れることが一般的です。死体は一般的に不快感を伴うため、ことさら映し出す必要はありませんが、あまりにも過剰に隠蔽しすぎると、死体に対する「免疫」が獲得できず、何かの拍子に死体そのものやその画像・映像を目にした際に、その衝撃が非常に大きくなる危険性があります。
死も死体も現実に存在するものですから、それをなかったことにするのではなく、段階的に「見せる」ことが、死や死体に対する耐性を築く上で有効だと考えられます。例えば、虫や魚の死体から始め、次に鳥や動物の死体、そして安らかに眠っているような人間のきれいな死体、さらに事故や災害の被害者といった現実的な人間の死体、最終的には事件や戦争の犠牲者のような悲惨な人間の死体へと、順を追って子どもから青年期にかけて、適切な機会を捉えて見せていくことが、心の準備を促す一助となるかもしれません。
人はいつ、どのように死の恐怖を感じるのか?
一部の死恐怖症の人を除き、四六時中ずっと死の恐怖を感じ続けている人は稀でしょう。では、人は具体的にどのような状況で死の恐怖を感じやすいのでしょうか。
最も多いのは、進行がんや重症化した新型コロナ肺炎といった、死の危険性が高い病気の診断を受けた時です。突然、死が目の前に突きつけられ、多くの人が驚愕と動揺とともに強い恐怖に駆られます。
しかし、この反応は全ての人に当てはまるわけではありません。死の危険性が高い診断を受けても、比較的冷静に受け止める人もいます。これには、すでに覚悟ができている人、運命を受け入れる心構えがある人、死の危険性を十分に理解できていない人、あるいは性格的に死の恐怖をあまり感じない人など、様々な要因が考えられます。
逆に、まだ死ぬと決まったわけではないのに、絶望して取り乱したり、自暴自棄になったりする人もいます。医療従事者は専門知識があるため、ある程度冷静に状況を受け止めることができますが、一般の人々は不安と疑心暗鬼に駆られ、悲観と楽観の間で揺れ動くのが常です。
しかし、この恐怖にも「慣れ」の効果が見られます。例えば、がんが再発した人でも、最初は大きく落ち込みますが、抗がん剤治療などを経て2度、3度と再発の告知を受けるうちに、「またか」といった感覚になり、あまり動揺しなくなることがあります。そのうちに徐々に死への心構えもできてきて、残り時間を有効に使いながら穏やかな最期を迎えるケースも少なくありません。
死は避けられない現実ですが、それに対する私たちの心の反応は様々であり、経験や時間の経過によって変化しうるのです。
結論
「死の恐怖」は人類普遍の感情ですが、その度合いが日常生活に支障をきたすほどになると「死恐怖症」という精神疾患として認識されます。これは、単なる漠然とした不安ではなく、具体的な症状を伴う病態です。また、死体への極端な恐怖である「死体恐怖症」も存在し、日本のメディアが死の映像を厳しく自主規制することで、かえって人々が死に対して「免疫」を持てなくなるという側面も指摘されています。
人は、重病の診断など、死が身近に迫る状況で強い恐怖を感じやすい一方で、その反応は個人差が大きく、経験を重ねることで「慣れ」が生じ、次第に冷静に、あるいは穏やかに死を受け入れることができるようになる場合もあります。死という避けられない現実に対し、その様々な側面を理解し、段階的に向き合うことが、心の安定につながる道なのかもしれません。
参考文献
久坂部羊『死が怖い人へ』(SBクリエイティブ)