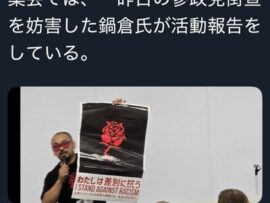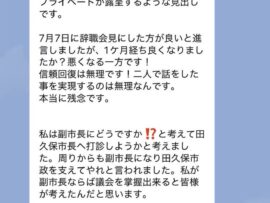民間機のパイロットとなることを夢見ていた野口剛は、太平洋戦争の激動の中、零式艦上戦闘機「ゼロ戦」の操縦士となり、やがて特攻隊「神雷部隊」への入隊を自ら志願しました。彼が自らの命を捧げてまで守ろうとしたのは、この国にいつか訪れるであろう、そう信じた未来の平和でした。戦後80年を迎える今、命を懸けて戦った兵士たちの声は、私たちに何を語りかけるのでしょうか。本稿では、光文社新書『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』から一部を抜粋し、特攻隊員として歩んだ野口剛の選択とその背景にある真実に迫ります。
 『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』の書影。零戦パイロット野口剛の特攻志願の物語を示す。
『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』の書影。零戦パイロット野口剛の特攻志願の物語を示す。
「桜花」開発と神雷部隊の創設
1944年(昭和19年)8月、戦局打開に苦慮していた日本海軍は、敵艦隊攻撃の新たな手段として特別攻撃機「桜花」の開発に着手しました。奇しくも、この月はB-29に対し「屠龍」が初の体当たり攻撃を行った時期と重なります。「桜花」の試作機は、開発着手からわずか約2カ月という驚異的な速さで完成に至りました。そして同年10月、「桜花」を運用する専門部隊として「第七二一海軍航空隊」、通称「神雷部隊」が極秘裏に創設されたのです。この部隊には、窮地に陥った戦況を覆す起死回生の任務が託されていました。

爆弾を抱えた特攻専門機「桜花」の全貌
「桜花」は、機首部に爆弾を搭載した全長約6メートルほどの小型航空機でした。機体の左右には小さな翼を持つものの、自力での離着陸を可能にするエンジンは搭載されていません。そのため、一式陸上攻撃機(一式陸攻)のような大型機に固定されて目的地の上空まで運ばれ、そこで切り離された後に固形ロケット燃料を噴射して加速。滑空しながら敵軍艦に体当たりすることを目的に開発・製造されました。一度上空で切り離されると、操縦者には機体もろとも特攻する以外の道は残されていない、まさに「片道切符」の航空機だったのです。第二次世界大戦末期に実戦投入され、終戦までに計755機が製造され、公式記録では操縦士55人が特攻で戦死したとされています。
志願への葛藤と決断:野口剛の選択
野口が予備学生を指導する操縦教官を務めて数カ月が経とうとしていた頃、「神雷部隊ができるらしい」という噂が耳に入ってきます。しばらくして、基地の上官に呼び出され、彼は一枚の志願書を渡されました。上官は「この中に志願者はいるか。行きたい者は、この紙に丸を書いて出しなさい」と告げたのです。この時点では、野口は神雷部隊が「桜花」を使った特攻隊であることまでは知らなかったと言います。
しかし、上官は続けました。「この部隊へ入ったら最後、もう戻ってはこれない……」。そして、「両親はそろっているか、兄弟はいるか、長男はだめだぞ」など、家族構成について詳細な確認が行われました。このような「ただ事ではない事態」を想像させる上官の言葉を受け、野口は志願することに迷いやためらいを感じなかったのでしょうか?
彼の答えは毅然としていました。「迷いはなかったです。私には両親もいましたし、長男でもないし……。同期の友人と相談し、『一緒に行こうか』と決めて志願書に『丸』を書いて提出しました。私にとって、それはごく自然の選択でした」。野口と彼の親友は、共に特攻隊への道を志願したのです。
結びに
野口剛の決断は、当時の切迫した戦況と、彼が信じた「未来の平和」への強い願いが交錯する中で生まれたものでした。民間機パイロットの夢を抱きながらも、一式陸攻から切り離されれば生還の道がない特攻兵器「桜花」を操る神雷部隊へと身を投じた彼の選択は、単なる歴史的事実を超え、極限状況下における人間の精神性、そして犠牲の上に築かれた平和の尊さを私たちに訴えかけます。戦後80年の節目に、彼の物語は、過去の記憶を呼び覚まし、未来へと繋ぐ貴重な教訓となるでしょう。
参考文献
- 『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』(光文社新書)より一部抜粋、再構成。