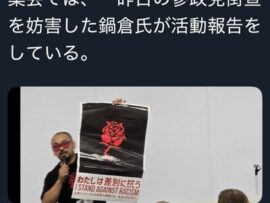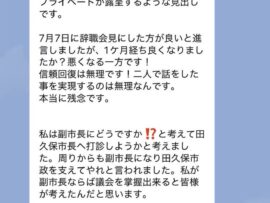海上自衛隊には、陸上自衛隊や航空自衛隊とは異なる独自の文化が深く根付いています。元海上自衛隊自衛艦隊司令官である香田洋二氏は、その文化が「艦艇での任務と生活を基本とした組織」によって形作られてきたと指摘します。指揮命令系統、人間関係、さらには日々の言葉遣いに至るまで、艦上での生活が海上自衛隊独自の慣習を築き上げてきたのです。
 マニラの埠頭に接近する海上自衛隊のヘリ搭載護衛艦いせ。海自の艦艇文化と航空部隊の重要性を象徴する一隻。
マニラの埠頭に接近する海上自衛隊のヘリ搭載護衛艦いせ。海自の艦艇文化と航空部隊の重要性を象徴する一隻。
海上自衛隊組織の特異性:航空部隊の比重
海上自衛隊の組織文化を理解する上で、その独特な組織構成は欠かせません。世界の海軍と比較しても、海上自衛隊は非常に珍しい存在です。戦闘を担う部隊はすべて自衛艦隊の下に統合されていますが、この自衛艦隊内で最も多くの人員を占めるのは、実は「艦乗り」ではありません。全体の5割強が、航空機の搭乗員や整備士、管制官など、航空任務に携わる隊員で構成されているのです。
このような構成の海軍は、広大な世界を見渡しても、海上自衛隊と米海軍の二つしかありません。米海軍の場合、空母からの発着艦を行う戦闘機パイロットや整備士など、航空任務に従事する海軍軍人が多いのは理解できます。しかし、海上自衛隊においては、敵の潜水艦を発見し追尾する哨戒機やヘリコプターが部隊構成の大きな比重を占めるため、航空部隊の人数が非常に大きな割合を占めているのが特徴です。
「艦乗り」文化の根源:明治以来の伝統
そのように航空部隊の比重が高いにもかかわらず、海上自衛隊はやはり「艦乗り」の組織であるという認識が強いです。これは、明治時代に日本の海軍が艦艇を操る軍として発足し、その文化が途切れることなく現代まで引き継がれているからです。陸上勤務の隊員であろうと、航空部隊の隊員であろうと、海上自衛隊の基本的な文化は艦艇での任務と生活によって形作られています。指揮命令系統から人間関係、そして日々の言葉遣いに至るまで、すべてが「艦の上の生活」を基盤として発展してきました。
独特な「海の世界」の言葉遣い
海上自衛隊の特殊な文化が特に顕著に表れるのは、その言葉遣いです。例えば、一般社会で言う「外出」は、海上自衛隊では「上陸」と表現されます。基地は陸上に存在するため、実際には陸上を移動するに過ぎませんが、船から岸に上がることを「上陸」と呼ぶ習わしが、基地外へ出る行為にも適用されるようになったと言われています。
また、「別法」という言葉を聞いて、何を意味するか理解できるでしょうか。海上自衛隊では、「本日の別法は1900から開始いたします」のように用いられ、これは「宴会」を意味します。この言葉は旧帝国海軍から引き継がれたものです。艦内には艦長以下の幹部が集まる「士官室」がありますが、ここは通常業務の報告や作戦会議が行われる場所です。旧海軍において艦内での飲酒が許されていた時代、士官室での宴会を通常の業務と区別するために「士官室別法」と呼ぶ習慣がありました。この「別法」という呼び方が海上自衛隊にも受け継がれ、現在では陸上の街での宴会も「別法」と表現されるようになったのです。
海上自衛隊の文化は、その独特な組織構成と、長きにわたる艦艇での生活によって培われた言葉遣いなどに象徴されています。航空部隊の重要性が増す現代においても、「艦乗り」としての伝統と精神が、組織の根幹を形成し続けているのです。
参考文献
- 香田洋二. (2025). 『自衛隊に告ぐ 元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』. 中央公論新社.