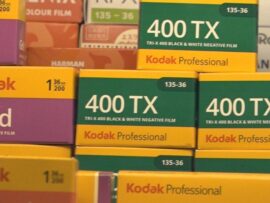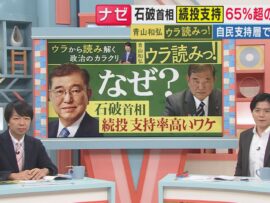戦後、サハリンに取り残され、日本への永住帰国を果たした人々がいる。彼らは海を隔てた故郷への複雑な思いを抱えながら、新たな生活を築いてきた。彼らが語るサハリンでの生活、日本への帰国の道のり、そして未来にわたる日露交流への願いとは何か。本稿では、その貴重な証言を通して、サハリン残留日本人の歴史と、国境を越えた人々の繋がりが持つ意味を深く探る。
 稚内港北防波堤ドームへの案内標識。ロシア語併記で樺太との歴史的つながりを示す。
稚内港北防波堤ドームへの案内標識。ロシア語併記で樺太との歴史的つながりを示す。
サハリン残留者の証言:故郷への想いと新たな生活
1947年、サハリンに生まれた私は、10人兄弟の7番目でした。もしサハリンにいたままだと、乳がんの転移手術も受けられなかっただろうと考えると、2005年に日本へ永住帰国できたことは命を救われたに等しい出来事でした。サハリンの山ではコケモモや行者ニンニクを採集し、サラダオイルがない時代には茹でて食べたものです。家では日本語、外ではロシア語を話し、学校では英語、ロシア語、朝鮮語など多岐にわたる言語を学びました。高校卒業後、46歳までサハリンで英語教師として勤務しましたが、子供たちの世話のために仕事が終わっても帰宅できないなど、苦労も多く経験しました。
私は戦後生まれであるため、国の支援による永住帰国は不可能だと考えていました。しかし、両親が日本人であることが証明できたため、日本への永住が叶いました。私たちの世代はまだ日本の文化を知る人々が周囲にいましたが、ペレストロイカ以降に生まれた世代は日本文化に馴染みが薄いと感じます。ソ連時代には日曜日に公園のゴミ拾いに動員されることもありましたが、ロシアとなってからはそうしたことはなくなり、「お金、お金」という声が聞かれるようになり、格差が顕著になりました。
ロシアに住む息子や妹たちと毎日テレビ電話で話すのが日課ですが、直行便がなくなったことで、直接会うことが非常に困難になりました。一日も早く、自由に往来できる日が来ることを願ってやみません。
次世代に繋ぐサハリンとの絆:異文化経験の価値
私がサハリン出身だと話すと、「なんでロシア出身なの?」と、世代を問わず繰り返し問われます。南樺太にいた祖母は、不運にも引き揚げ船に乗れず、サハリンに残留を余儀なくされました。祖母は常に「日本に帰りたい」と願っていたそうで、帰国できた際には心から喜んでいたと聞いています。
約30年前、私は7歳の時に両親、兄、祖母と共に永住帰国しました。日本に来て驚いたのは、エレベーターやエスカレーター、自動ドアといった設備が当たり前のように存在することでした。当初は日本語が全く理解できませんでしたが、周囲の助けを得て徐々に習得していきました。高校や大学では、幼少期から親しんだロシア語を専攻し、今では私の娘もロシア語に興味を持ち、一緒に勉強しています。
私は心から「サハリンに住んで良かった」と思っています。多くの日本人とは異なる言語や文化の中で育ったことで、日本を客観的に見つめる視点を得ることができたからです。
早くサハリンに住む親戚に会いに行き、お墓参りもしたいと切望しています。最近、サハリンのいとこに子供が生まれたのですが、輸出規制の影響で、おもちゃ一つ送ることさえままなりません。せめて個人間の交流だけでも自由にさせてほしい。将来的には、以前のように自由に往来できるようになることを願っています。北海道でもサハリンの歴史を知らない人が多く、このままでは家族に縁者がいても、サハリンとの繋がりが薄れてしまうかもしれません。サハリンに関わる人々との絆だけは、決して失いたくない。いつか、若い世代同士で交流イベントを開催したいと考えています。
結び:過去を未来へ繋ぐ日露交流の重要性
サハリン残留者たちの証言は、戦後の複雑な歴史と、その中で翻弄されながらもたくましく生きてきた人々の姿を浮き彫りにします。故郷への深い思い、異文化の中での適応、そして次世代へと伝えたい絆の重要性。彼らの言葉からは、個人レベルでの自由な交流が、国境を越えた相互理解といかに不可欠であるかが強く伝わってきます。現在の日露関係が困難な局面にある中、歴史を忘れず、草の根レベルでの交流を維持し、未来の世代へと継承していくことの意義は計り知れません。彼らの願いが実現し、再び自由に往来できる日が来ることを心から願うばかりです。