国内外から「後手に回っている」(ビハインド・ザ・カーブ)との指摘が相次ぐ中、日本銀行は現時点でのこの見方を否定し、物価指数の上昇率が今後縮小していくとの見通しを維持している。足元の実質国内総生産(GDP)が市場予想を上回ったものの、経済・物価のシナリオ変更は不要とし、米国経済の動向や国内経済に対する高関税政策の影響を慎重に見極める姿勢を示している。
「ビハインド・ザ・カーブではない」との主張
国内外の要人からは、日銀の金融政策運営が「後手に回っている」との批判が聞かれる。特に、13日にはベセント米財務長官が一部メディアに対し、個人的見解と断りながらも「日銀は後手に回っている」と発言し、金融市場に波紋を広げた。
しかし、日銀は現在の状況を「ビハインド・ザ・カーブ」には陥っていないと見ている。その主な理由として、コメ価格の前年比上昇率が今後大きく縮小すること、そして関税の影響による経済の減速が、結果的に物価指数の伸び率を抑制すると予測している点を挙げている。
1970年代の春闘で賃上げ率が30%を超えた時期と比較すれば、現在の2%台の賃金上昇率ははるかに低く、賃金と物価が螺旋的に上昇する局面にはないと判断している。現在の食品値上げは物流費や人件費の転嫁といった側面が強く、企業が賃金・価格設定行動をさらに積極化させるかどうかを注視しているものの、現時点では物価上振れのリスク要因に過ぎず、「ビハインド・ザ・カーブ」に陥っているわけではないというのが日銀の見解だ。
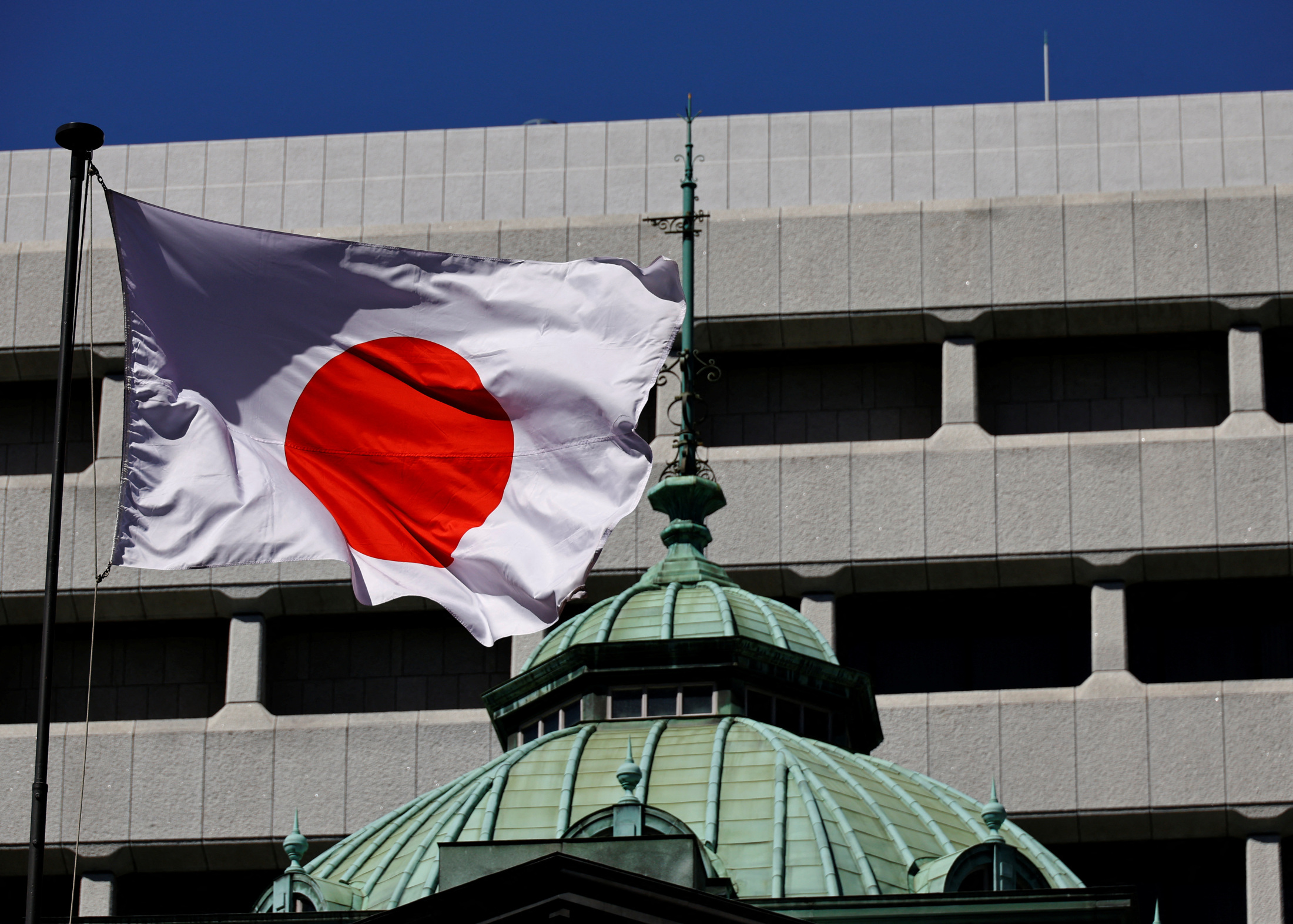 日本銀行本店前で撮影された日銀の建物。日本の金融政策の動向、特に物価と賃金上昇率に関する議論の中心にいる日銀の姿勢を象徴している。
日本銀行本店前で撮影された日銀の建物。日本の金融政策の動向、特に物価と賃金上昇率に関する議論の中心にいる日銀の姿勢を象徴している。
植田和男総裁も7月末の会見で、「現状ではビハインド・ザ・カーブに陥っているとは思っていないし、そうなるリスクが高いとまでは思っていない」と明言している。
GDP見通し維持と米国経済への警戒感
4―6月期の実質GDPが市場予想を上回る結果となったものの、日銀内では、高関税の影響で一時的に経済成長が鈍化し、その後再び伸び率を高めるという従来の想定を変更するほどではないとの受け止めが支配的だ。
日本の自動車メーカーは、米国による高関税政策の下でも競争力を維持するため、輸出価格を大幅に引き下げ、輸出数量を維持する戦略を採用してきた。日銀でも、この戦略によりGDPへの影響は軽微にとどまるとの予測があり、結果はその通りとなった形だ。
7月の展望リポートで「底堅く推移している」から下方修正された個人消費は0.2%増となり、物価高が続く中でも個人消費が底堅く推移しているとの見方が日銀内で聞かれる。
日銀は4―6月期GDPが関税の影響が比較的少なかった時期の指標であるとして、むしろ今後の経済動向、特に高関税政策の影響が本格化する時期を注視している。自動車メーカーが輸出価格を大幅に引き下げる戦略は、収益面で関税のダメージを吸収する形であり、長期的な継続は難しいとの見方もある。各メーカーが輸出価格を上げた際に米国市場での競争力を維持できるか、また収益への影響が賃上げにどう波及するかが今後の注目点となる。
それ以上に日銀内で関心が高まっているのは米国経済の動向だ。1日に発表された7月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数の増加が前月比7万3000人にとどまり、5月、6月分も大幅に下方改定された。この結果を受け、日銀の一部からは米国経済の下振れ懸念が浮上しており、秋にかけてその動向を慎重に見極める必要があるとの声が聞かれる。
結論
総じて、日本銀行は現在の金融政策運営が「後手に回っている」との外部からの指摘に対し、明確に否定する姿勢を維持している。物価上昇率の今後の縮小を見込み、国内経済の堅調さを確認しつつも、高関税政策の影響や特に不確実性の高まる米国経済の動向を今後も注視していく方針である。これは、日本経済の安定と物価目標の達成に向けた日銀の慎重かつ戦略的なアプローチを反映していると言える。






