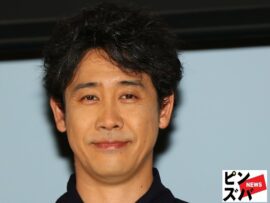戦後13年間にわたり、シベリア抑留者を含む約66万人もの引揚者たちを温かく迎え入れた京都府舞鶴市の港。この地にある「舞鶴引揚記念館」は、強制収容所「ラーゲリ」での過酷な日々や、故郷・家族への切なる思いを伝える重要な場所です。私たちはこの記念館を訪れ、改めて「戦後80年」という時間の持つ多様な意味と、その記憶が現代にどのように引き継がれるべきかを深く考えます。
舞鶴:引揚者たちが戦後の一歩を踏み出した場所
「舞鶴引揚記念館は、シベリア抑留を経験された方々が『自分たちが戦後の第一歩を踏み出した舞鶴』への深い思いから設立されたのです」。この学芸員の言葉は、私たちに軽い衝撃を与えました。日本海に面した京都府北部に位置する舞鶴港は、1945年(昭和20年)から1958年までの間に、まさに約66万人もの引揚者を迎え入れた歴史の舞台です。
 舞鶴引揚記念館に再現されたシベリア抑留者たちの過酷なラーゲリ生活体験室の様子
舞鶴引揚記念館に再現されたシベリア抑留者たちの過酷なラーゲリ生活体験室の様子
1945年8月15日、昭和天皇はラジオ放送を通じてポツダム宣言の受諾と終戦を国民に告げました。しかし、故国の土を初めて踏みしめて終戦を実感したシベリア抑留者にとって、その「戦後」は必ずしも80年に満たない多様な時間を意味します。ある人にとっては77年、またある人にとっては69年と、その始まりは人それぞれ異なっていたのです。13年もの長きにわたり、引揚者たちを「お帰りなさい!」「ご苦労様でした」と温かく歓迎し、お茶や蒸かし芋でもてなした舞鶴市民もまた、彼らが帰ってくるまでは真の意味での「戦後」を実感できなかったのかもしれません。
 2015年にリニューアルされ、引揚者の記憶を伝える舞鶴引揚記念館の外観
2015年にリニューアルされ、引揚者の記憶を伝える舞鶴引揚記念館の外観
1980年代に入ると、高齢化が進んだシベリア抑留者たちから「自分たちの戦後が始まった舞鶴に記念館を建てたい」「多くの人が訪れることで、温かく迎えてくれた舞鶴に恩返しができる」といった切実な声が上がり始めました。これに応え、全国の引揚者や舞鶴市民からの寄付は総額7400万円にも達しました。これに京都府の補助金2000万円が加わり、総工費2億4000万円を投じて舞鶴市が「舞鶴引揚記念館」を建設。1988年に開館し、現在では1万6000点を超える貴重な史料の中から、常時1000点以上が展示されています。
鎮守府から引揚港へ:舞鶴の地理的・歴史的背景
舞鶴市は、西舞鶴と東舞鶴の二つのエリアに大きく分かれています。西舞鶴がかつて丹後田辺藩の城下町として栄えた歴史を持つ一方、東舞鶴は日本海軍が戦略拠点として整備した軍港「鎮守府」として発展しました。
 シベリア抑留者がラーゲリで手作りした箸とスプーン。過酷な抑留生活における食事の重要性を示す貴重な史料
シベリア抑留者がラーゲリで手作りした箸とスプーン。過酷な抑留生活における食事の重要性を示す貴重な史料
既に設置されていた横須賀(神奈川県)、呉(広島県)、佐世保(長崎県)に続き、ロシアとの緊張が高まっていた1901年(明治34年)には、日本海側で唯一、最後の鎮守府として開庁しました。この地は、3年後に勃発した日露戦争(1904-05年)において、予想通り極めて重要な役割を果たすことになります。このような地理的、歴史的背景が、太平洋戦争後、舞鶴が数多くのシベリア抑留者を迎え入れる港となる運命を決定づけました。実際に、舞鶴に上陸した引揚者66万人の約7割にあたる46万人が、シベリアからの帰還者だったのです。
 五老岳から望む舞鶴湾の全景。軍港として栄えた東舞鶴と城下町であった西舞鶴の地理的特徴を示す
五老岳から望む舞鶴湾の全景。軍港として栄えた東舞鶴と城下町であった西舞鶴の地理的特徴を示す
シベリアに抑留されたのは、主に満州や樺太で武装解除した日本兵でした。ソ連軍は彼らに「ダモイ」(帰国、帰還を意味するロシア語)と呼びかけながら列車に詰め込みましたが、彼らが到着したのは、想像とはかけ離れたロシア北東部シベリアの強制収容所「ラーゲリ」だったのです。
記憶を継承し、平和を考える舞鶴
舞鶴引揚記念館は、単なる歴史的な事実を伝える場に留まりません。そこには、シベリア抑留という過酷な経験を乗り越え、故国への帰還を果たした引揚者たちの個人的な「戦後」と、彼らを支え続けた舞鶴市民の深い温かさが刻まれています。この記念館が提示する「戦後80年」という時間の多様な意味は、現代を生きる私たちに、歴史を多角的に捉え、平和の尊さを再認識する機会を与えてくれます。未来へこの記憶を継承していくことこそが、真の平和学習への道となるでしょう。