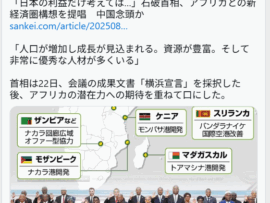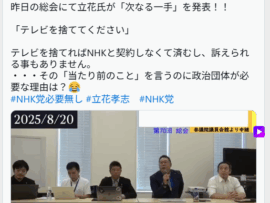お盆休み中も暗闘が続く永田町では、政治の混迷が深まっています。特に、与野党間の駆け引きや各党内部の複雑な事情は、有権者の政治不信を一層募らせるばかりです。憲政史研究家の倉山満氏は、このような状況に対し、日本政治の再生に向けた具体的な処方箋を提示しています。本稿では、自民党の現状、立憲民主党への有権者の視線、そして日本維新の会の課題を紐解き、倉山氏が国民民主党に寄せる期待と「総裁」への改称提言の意義を探ります。
 倉山満氏のネット放送局「チャンネルくらら」での国民民主党・玉木代表インタビュー風景。記事では総裁への改称が提言されている。
倉山満氏のネット放送局「チャンネルくらら」での国民民主党・玉木代表インタビュー風景。記事では総裁への改称が提言されている。
自民党の現状:党を割るエネルギーなき「居座り」の構図
現在の自民党は、衆議院選挙や参議院選挙での敗北にもかかわらず、その責任を取ろうとしない石破茂総裁(当時、総理大臣)の「居座り」が問題視されています。公約を掲げて信を問う選挙の意味が薄れてしまう事態に対し、「内外の難局が厳しい」という理由で居座る姿勢は、有権者の理解を得がたいものです。
さらに、今の自民党は、かつてのような「党を割るエネルギー」すら失っていると倉山氏は指摘します。例えば、保守勢力からの期待を集める高市早苗氏は、橋下徹氏から「党を割って出ろ」と促された際、SNSで猛反論を展開しました。一昔前の自民党政治家であれば、本気で党を割る意図がある時にこそ、それを否定することで本気度を示すものですが、高市氏のケースでは真に党を出たくないという意思が強く感じられます。このような状況では、高市氏も「オールド自民」の一部としか見られず、日本政治の展望が開けないと倉山氏は懸念しています。
有権者からの「立憲スルー」と連立の思惑
一方、野党第一党である立憲民主党も厳しい状況にあります。「自民党も嫌だが、立憲はもっと嫌」という有権者の声は根強く、今回の参議院選挙では「立憲スルー」と評されるほど、有権者からの退場勧告を突きつけられました。有権者は、オールド自民と立憲民主党のような「パヨク勢力」に対して、変化を求めているのです。
しかし、自民党は野党に多数派工作の触手を伸ばし、延命を図ろうとしています。立憲民主党との大連立も囁かれますが、両党は選挙区が最も競合するため利害調整が難しく、そもそも思想的な肌合いが合わないため、連立すれば双方が分裂する可能性すらあります。そこで本命視されているのが、日本維新の会との連立ですが、この党の内情もまた複雑です。
日本維新の会の「政党」としての課題
日本維新の会は、その躍進が注目される一方で、政党としての根本的な課題を抱えています。政党とは本来、「党首を総理大臣にして政策を実現する集団」であるはずですが、維新の場合、代表が吉村洋文大阪府知事です。吉村氏は有能な人物であるものの、憲法上、現職の知事では総理大臣になることはできません。倉山氏は、この点において、日本維新の会が「政党」ではなく「政治団体」に近い状態にあると厳しい見方を示しています。政党としての体制が整っていなければ、国民の期待に応え、日本政治を動かすのは困難です。
結論:日本政治再生への期待と「総裁」改称提言の意義
現在の日本政治は、自民党の停滞、立憲民主党への不信、そして日本維新の会の構造的課題が絡み合い、まさに混迷を極めています。このような状況下で、倉山満氏が提示する日本政治再生への処方箋は、国民民主党への期待と、党首の名称を「代表」から「総裁」へ改称する提言に集約されます。これは、単なる名称変更にとどまらず、政党としての責任感と「総理大臣を目指す集団」としての覚悟を明確にするための重要な一歩となるでしょう。国民民主党がこの提言を受け止め、その存在感を高めることが、閉塞感に満ちた日本政治に新たな風を吹き込む鍵となるかもしれません。