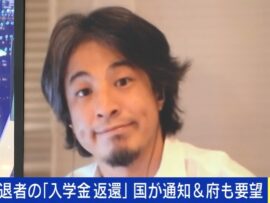吉本興業が2025年11月1日に開始すると発表したお笑いコンビ「ダウンタウン」によるコンテンツ配信サービス「ダウンタウンチャンネル(仮称)」は、芸能活動を休止中の松本人志氏の復帰の場となる可能性を巡り、大きな注目を集めています。ファンの間では「見たい人だけ見ればいい」との声が上がる一方、ネットメディア編集者の視点からは、この新サービスが世論の分断をより際立たせる可能性も指摘されています。本稿では、ダウンタウンチャンネルの構想から発表に至る経緯、松本氏の復帰を巡る賛否両論、そして「ペイウォール」戦略が果たす役割について、深く掘り下げて分析します。
松本人志氏の活動休止と新チャンネル構想の経緯
松本人志氏は、週刊誌による女性への性加害報道への対応を理由に、2024年1月より芸能活動を休止しています。以降、X(旧Twitter)での投稿はあったものの、表舞台での活動は芸能記者へのインタビュー記事を除いてほとんどありませんでした。
新たなコンテンツ配信サービスの構想が表面化したのは、2024年末に松本氏自身がインタビューで語ったことがきっかけです。当初は2025年春ごろの開始を目指しているとされていましたが、その後、スポーツ紙が今夏のスタートを報じ、最終的に吉本興業は2025年8月20日、同年11月1日からサービスを正式に開始すると発表しました。
吉本興業は発表の中で、本サービスのために「サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築した」とし、「ユーザーが参加できる機能も取り入れ、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できる」と詳細を説明しました。正式名称や料金、具体的なコンテンツ内容は改めて発表される予定です。この動きに先立つ8月18日には、同社がコンテンツの海外展開を目指すファンドを組成し、国内外から数十億円規模の資金調達を行うことも発表されており、ダウンタウンチャンネルが吉本興業のグローバル戦略の一翼を担う可能性も示唆されています。
 2017年、万博誘致式典で挨拶するダウンタウンの松本人志氏(左)と浜田雅功氏(右)。
2017年、万博誘致式典で挨拶するダウンタウンの松本人志氏(左)と浜田雅功氏(右)。
復帰への期待と「説明不足」批判の対立
ダウンタウンチャンネルでの松本氏の復帰については、現時点では吉本興業から明確な発表はありません。しかし、相方の浜田雅功氏の単独での活動であれば、コンビ名を冠した新たなプラットフォームを設けることは通常考えにくいでしょう。このため、松本氏の復帰が強く期待されており、ファンからは「約2年のブランクを経て、ようやく復帰する」と歓迎の声が多数寄せられています。
一方で、松本氏の復帰を快く思わない層からは、「説明不足なのではないか」という批判の声が根強く、依然として厳しい目が向けられています。インターネット上での「炎上ウォッチャー」として、数々のSNS風評事例を見てきたネットメディア編集者の視点から見ると、このチャンネルの成否は、こうした世論の対立をいかに乗り越えるかにかかっていると言えるでしょう。
「イヤなら見るな」論とペイウォールの役割
インターネット上では、しばしば「イヤなら見るな」という言葉が用いられます。これは、不快に感じるものや批判の対象となるものを、わざわざ見たり聞いたりする必要はない、というニュアンスで、擁護の文脈で使われることが多い表現です。しかし、ダウンタウンほどの人気と知名度を持つお笑いコンビの場合、テレビ番組やCMで見ない日はほとんどなく、視聴者には実質的な選択肢が少ないのが現状でした。この「意図せずとも受動的に触れてしまう」という点が、松本氏の復帰に対する慎重論の根幹にあったと考えられます。
しかし、ダウンタウンチャンネルのような会員制のコンテンツ配信サービスでは、状況は大きく変わります。「見たい人だけが見る環境」を構築することで、ある種の「ゾーニング」が効果的に行われます。これにより、「見たくなくても目に入ってしまう人」の数は大幅に減少し、ファンが自身の意思でコンテンツを選び、楽しむ環境が提供されます。
ネットメディア業界で普及している「ペイウォール(支払いの壁)」は、まさにこのような収益化の手段であり、購読料を支払わなければコンテンツを閲覧できない仕組みを指します。有名人のファンクラブなどが採用しているシステムと同様に、ダウンタウンチャンネルもこのモデルに準じると考えられます。ペイウォールは、批判的な意見を持つ層からの意図しない接触を避け、熱心なファン層に質の高いコンテンツを届けるための有効な手段となり得るのです。
結論
吉本興業が立ち上げる「ダウンタウンチャンネル」は、単なる新しい配信サービスに留まらず、松本人志氏の復帰を巡る社会的な議論、そして現代のコンテンツ消費モデルにおける「ゾーニング」と「ペイウォール」の役割を浮き彫りにしています。このプラットフォームは、熱心なファンにとっては待望の場所となる一方で、松本氏の活動休止の経緯に対する「説明不足」との批判の声が依然として存在する中で、その成功は吉本興業の透明性とコンテンツ戦略の手腕にかかっています。新チャンネルが、現代の多様な世論とどのように向き合い、新たなエンターテインメントの形を確立していくのか、その動向が注目されます。
参考文献
- 吉本興業、ダウンタウンチャンネル開設も「一件落着にはほど遠い」とネット編集者が指摘するワケ (PRESIDENT Online 配信、Yahoo!ニュース掲載)