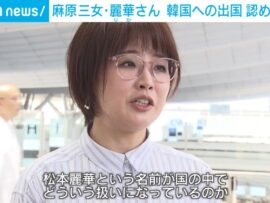急速に進む高齢化社会において、社員の介護問題は企業にとって喫緊の課題となっています。特に日本企業では、親の介護と仕事の両立に苦悩する社員が増加し、「介護離職」が社会問題化しています。こうした背景を受け、名古屋鉄道(名鉄)は社員の仕事と介護の両立を支援するため、新たな制度を導入しました。この取り組みは、人手不足が深刻化する中で、企業がどのように社員を支え、人材定着を図るかを示す好例と言えるでしょう。
長期化する社員の介護負担:名鉄の50代男性事例
名鉄に勤務する50代の男性社員は、2022年末から千葉県に住む父親(当時87歳)の介護の中心的な役割を担うことになりました。脳梗塞の後遺症で杖を使用していた父親は、腸閉塞で3ヶ月入院後、要介護5の車いす生活に。母親(87歳)が在宅で介護を行っていましたが、老老介護の限界に直面し、2023年夏には母親が介護疲れで体調を崩してしまいます。男性は公休に加え有給休暇を使い、名古屋と千葉を行き来して父親の移動や排泄の介助にあたりました。しかし、年間20日あった有給はすぐに底をつき、体調を崩しても休めない状況に陥り、休職や退職を考えるほど追い詰められていきました。
 名古屋鉄道が社員の介護離職を防ぐために導入した新しい支援制度のイメージ
名古屋鉄道が社員の介護離職を防ぐために導入した新しい支援制度のイメージ
導入された「介護短日数勤務制度」とその効果
追い詰められた男性が上司に相談したところ、2023年1月にスタートしたばかりの「介護短日数勤務制度」の利用を勧められました。この制度は、介護が必要な社員が期間の制限なく、公休(月約10日)に加えて最大で月8日間の無給休暇を取得できるというものです。男性はこの制度を2023年10月から利用し始め、「この制度を知らなければ、休職か退職を考えていたと思う」と振り返っています。現在、男性は父親を看取った後も、足腰が弱くなった一人暮らしの母親の通院付き添いなどでこの制度を活用し、仕事と介護の両立を実現しています。
高齢化する社員構成への対応と課題
名鉄がこの「介護短日数勤務制度」を導入した背景には、鉄道事業に従事する約4300人の社員のうち、50代が半数以上を占めるという高齢化した年齢構成があります。2023年8月に実施したアンケートでは、同居家族を介護する社員が約200人、2親等以内で要介護者がいる社員は1000人に上ることが判明しました。現在、50代の社員5人がこの制度を利用していますが、それでも2024年度には5人の社員が介護離職しています。同社人事戦略担当課長の岩田幹氏は「隠れ介護をしている社員は多く、介護と告げずに辞めた人もいると思う」と指摘しており、潜在的な課題の大きさをうかがわせます。名鉄は、新たに介護休業を取得した社員に対し最大1年間、月給の半分に相当する支援金を支給する制度や、要介護者が扶養の場合には月3万円の手当を支給する制度も導入し、多角的に社員の介護支援を強化しています。
結論
名鉄の介護支援策は、社員の「介護離職」を防ぎ、人材を定着させるための重要な企業戦略です。高齢化が加速する社会において、企業が社員のライフイベント、特に介護問題にどう向き合い、支援していくかは、持続可能な経営と社会貢献の両面でその真価が問われます。このような先進的な取り組みは、他の企業にとっても参考となり、より良い労働環境の実現に繋がるでしょう。
朝日新聞社
Source link