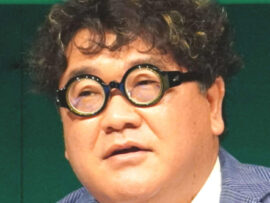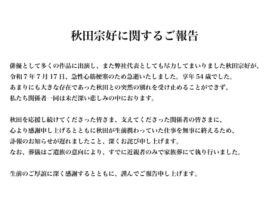若い頃、60歳といえば人生の終着駅を間近にした隠居生活を送るイメージが一般的でした。しかし、実際にその年齢に達するか、あるいは目前にすると、多くの人が自身がその年代になったという実感に乏しく、大きな戸惑いを覚えます。これからどのように生きていくべきか、深く考え込んでしまうのが現実です。心理学博士であるMP人間科学研究所代表の榎本博明氏は、人生の大きな転機であるこの時期をどう乗り切るべきかについて考察しています。本記事では、60代が直面する「喪失の時期」における不安と戸惑いの正体を深く掘り下げ、その感情がごく自然なものであることを解説します。
60代が「喪失の時期」と言われる理由
一般的に、60代以降は「喪失の時期」と表現されます。長年勤め上げてきた職場を失い、それに伴って職業上の役割や、これまで家庭内で担ってきた役割(子育てや家族の世話など)も変化します。さらに、自身の体力の衰えや記憶力の減退を実感することも少なくありません。こうした多岐にわたる「喪失」が、この年代に特有の不安や戸惑いの根源となるのです。60歳を目前にした人々からは、このような喪失を想定し、不安な心情を吐露する声が数多く聞かれます。
 熟年男性が窓の外を眺め、老後の生活や定年後の不安について考え込む様子
熟年男性が窓の外を眺め、老後の生活や定年後の不安について考え込む様子
職業生活からの解放がもたらす「空虚感」
これまで約40年間にわたり仕事に従事し、たとえ転勤や転職で職場が変わっても、毎日通う場所とやるべき仕事がありました。しかし定年退職を迎えると、その場所も役割も失われ、まるで自分が必要とされていない存在になったかのような、言いようのない寂しさや虚しさを感じる人が多くいます。特に職業生活に深く没頭してきた人ほど、この感情は強く表れる傾向にあります。
平日も家にこもりきりの生活を想像するとぞっとする、あるいは家で過ごす自分の姿が想像できないという声も聞かれます。若い頃から休日も極力外出していた男性などは、「家には自分の居場所がない気がするし、退職後に家でのんびり楽しく過ごすなんてあり得ない」と話します。一方で、「夫が退職後ずっと家にいるのは耐えられないから、自分は外に居場所を作る努力をしないと」と考えている女性も少なくありません。
仕事一筋で生きてきた人にとって、引退後の生活への不安は特に深刻です。定年退職後は自由に過ごして良いと言われても、何をすれば良いのか皆目見当がつかず、これまで無趣味だった自分が今さら新しい趣味を持とうとしてもどうしたら良いか分からず、ただ戸惑うばかりだと語る人もいます。また、仕事から引退しても何らかの役割がないと物足りなさを感じるものの、稼ぐために必死になる必要はないため、ボランティアでも良いから社会と繋がっていたいと願う人もいます。しかし、適当な活動が見つからず焦燥感を覚えるケースも散見されます。
心身の衰えに対する潜在的な恐れ
認知症を心配する年齢ではないと理解していても、自身の記憶力の衰えを実感することがあります。これまで当たり前のようにできていたことが将来的にできなくなっていくかもしれないと考えると、不安で仕方がないという声も聞かれます。体力的な衰えも同様に、老後の生活における自立への懸念へと繋がります。
結論
60歳という人生の大きな節目に直面し、多くの人が感じる戸惑いや不安、そして「喪失の時期」特有の感情は、避けられない現実であり、ごく自然な心の動きです。長年の職業生活からの解放、役割の変化、そして心身の衰えといった複数の「喪失」が重なることで、私たちは新たな自分と向き合うことを迫られます。これらの感情を認識し、受け入れることから、人生の次のフェーズへの準備が始まります。専門家の見解も踏まえ、こうした不安や喪失感は誰もが経験しうるものであると理解することで、読者の皆様が前向きにこれからの人生を歩むきっかけとなることを願います。