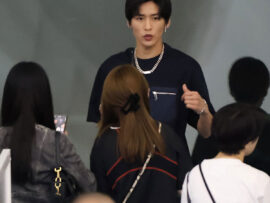国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソン氏は、昨今一部で囁かれる「右派ポピュリズムが日本の政治の中心に座る」という観測に対し、独自の視点から考察を深めている。新興右派政党の台頭や仮定上の政権の苦境が報じられる中、果たして日本はアメリカのようなポピュリスト主導の政治に移行するのだろうか。モーリー氏は、日本の政治、特に自民党の特異な性質を、あるアメリカ南部の都市文化になぞらえて分析する。
ニューオーリンズのクレオール文化とガンボに学ぶ政治の多様性
メキシコ湾に面するアメリカ南部ルイジアナ州ニューオーリンズは、17世紀末にフランス領として開拓され、奴隷貿易の拠点として繁栄した歴史を持つ。この地では、戦後のリベラリズムとは異なる文脈で、自由と奴隷、黒人と白人など、多様な人種と文化が入り混じる「クレオール文化」が独特の形で発展してきた。年に一度の謝肉祭「マルディグラ」では、仮面と羽根飾りの群衆が狂乱のパレードを繰り広げ、旧フランス人街にはジャズクラブやバーがひしめく。歴史的に売春や同性愛にも寛容で、"アメリカでも最も腐敗した享楽的な都市"というイメージが広く浸透している。モーリー氏自身も若い頃に訪れ、「ここにいたら抜け出せなくなる」と強く感じたという。
 モーリー・ロバートソン氏:日本の右派ポピュリズムを考察する国際ジャーナリスト
モーリー・ロバートソン氏:日本の右派ポピュリズムを考察する国際ジャーナリスト
ニューオーリンズを象徴する郷土料理「ガンボ」は、さまざまな食材をスパイスと共に長時間煮込み、素材の形も味も溶け合い、最終的に「ガンボの味」に収束していく特徴を持つ。モーリー氏はこのガンボに、日本の自民党政治を重ねて考察する。
自民党政治を「大鍋型包括政党」と捉える視点
自民党はまさに「大鍋型"包括政党"」であるとモーリー氏は指摘する。農政、道路、エネルギーといったあらゆる分野に複雑な利害調整構造が存在し、それぞれが「食材」を持ち寄り、妥協を重ねて「清濁あわせ呑んだ味」に仕上げるという伝統芸を持つ。この大鍋の中では、相反する要素すら共存しうる。例えば、安倍政権時代の対中国政策では、憲法改正を視野に入れ、日米同盟を強化しつつも、経済面では中国への深い依存関係を維持していた。これは一見"矛盾"に見えるが、自民党にとっては利害の均衡を取るための自然な振る舞いであり、その体質はしばしば「鵺(ぬえ)のような」と表現される。
新興勢力も「自民党味」に染まる構造
自民党のこのような包括的体質ゆえに、時代ごとの連立相手や新興勢力も、最終的には"自民党味"に染まり、元の個性はかき消されていく傾向がある。新興宗教団体である創価学会を母体とし、平和主義を掲げ続けてきた公明党が、安全保障法制の採決時に明確な反対を表明しなかった事例などは、その典型と言えるだろう。
だからこそ、一部で語られる「日本型の右派ポピュリズムが自民党を乗っ取る」というシナリオ、例えば新興右派政党がキャスティングボードを握り政策の主導権を握る、あるいは自民党内の右派政治家が離党して政権をジャックするといった事態は、まだ現実的ではないとモーリー氏は見ている。トランプ氏という「トリックスター」が共和党を事実上掌握したアメリカとは異なり、日本ではどんな勢力も政権に近づくとある程度"骨抜き"になる構造が、いまだに維持されているというのだ。
日本型ポピュリズムの「賞味期限」と国民の優先事項
このような背景から、モーリー氏は現在勢いづく日本型ポピュリズムの「賞味期限」を「最長3年」と予測する。仮に右派ポピュリストが政権入りし、経済面で大胆な減税や金融緩和を打ち出したとしても、国債格下げや市場の反発があれば、方針転換は避けられないだろう。外交においても、たとえ一議員としての対中姿勢が強硬であっても、経済的な依存関係の深さから、政府の実務段階では財界の圧力を受け、一定程度軟化せざるを得ないはずだ。
円安と物価高が暮らしを直撃する中で、減税や財政出動を訴えるポピュリズム、あるいは右派的な主張に熱狂した人々の多くは、それほど長く待ってはくれない。熱狂はやがて徒労感に変わり、「どうせ変わらない」という諦観が広がる可能性は高いとモーリー氏は指摘する。結局、日本人と"お上(かみ)"との契約の主条項は、イデオロギーではなく、経済や日々の暮らしである。右派ポピュリズムに飽きた頃には、今度は手のひらを返すように、経済を支える移民やインバウンドへの賛同の声が相当な勢いで広がる可能性すらあると、モーリー氏は予言している。