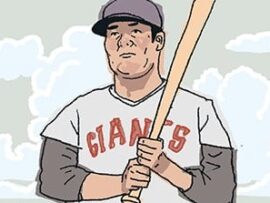生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」を持つ身長123cmの大学生、星来さん。彼女は低身長に加え、軽度白内障や側弯症といった合併症とも向き合いながら、障害者専門芸能事務所に所属し、モデルとしても活躍しています。社会に向けて自身の疾患に関する情報発信を行う星来さんに、日常生活で直面する誤解や社会の変化について詳しく話を伺いました。彼女の経験は、多様性への理解を深める貴重な示唆を与えます。
日常生活での「子ども扱い」と誤解
星来さんの身長123cmという特徴は、時に周囲からの予期せぬ反応を招くことがあります。例えば、レストランでは子どもと間違えられ、塗り絵を渡されるといった経験も。
「先日、レストランで塗り絵を渡された時はさすがに驚きましたね(笑)。私の後ろ姿しか見ていなかったり、親と一緒にいると、子どもに間違われやすいんです。年齢を重ねるごとに減ってきてはいますが、そうした経験はまだあります」と星来さんは語ります。
こうした誤解を避けるため、星来さんは外出時に工夫を凝らしています。特に、大人として認識されるようメイクを施すことは、彼女にとって日常の一部となっています。また、車の運転中も、周囲の誤解を防ぐための配慮が欠かせません。
 2型コラーゲン異常症と向き合う身長123cmの大学生、星来さんの写真。モデルとしても活動する彼女の笑顔が印象的。
2型コラーゲン異常症と向き合う身長123cmの大学生、星来さんの写真。モデルとしても活動する彼女の笑顔が印象的。
自動車運転における課題と工夫
星来さんにとって、自動車の運転は自由な移動手段である一方で、独特の課題を伴います。運転席に座る彼女を見て、周囲の人が驚くという経験は少なくありません。
「私が運転席に乗ると、皆さん本当にびっくりされるので、常に気を付けています」と星来さん。具体的には、自らが運転する際は必ず助手席から乗り込み、その後で運転席へと移動する、といった工夫をしています。
この習慣には、過去の経験が深く関係しています。「一度、普通に運転席から乗り込んで店の駐車場から出ようとした時、ものすごい視線を感じたことがあったんです。『あれ、私の車、何か変なのかな?』と思ったのですが、よくよく考えたら、私が運転席に乗ったから皆が心配して見ていたのか、と。それ以来、『ちっちゃい子が運転してる』と通報されないように、助手席から乗るようにしたんです」。
運転免許の取得自体も、星来さんにとっては容易な道のりではありませんでした。
「免許を取るのも大変でした。まず、試験場で、どのように車を改造すれば運転できるのかという検査を受けました。その結果、足のペダル延長と、背中とお尻にクッションを置けば問題ないという診断が出たんです」。
この診断結果を持って、特注のペダル延長を依頼するために車の工場へ向かいましたが、意外な展開があったと星来さんは続けます。「結局、私たちの軽自動車であればペダルの延長は不要だと、工場の方にお墨付きをもらえました。改造はしませんでしたが、そこに至るまでにかなりの手間がかかりましたね」。
社会の視線への向き合い方:保育の学びから
街中で周囲からの視線を感じることは、星来さんにとって日常の一部であり、同じ障害を持つ人々も同様に経験していることだと理解しています。特に子どもたちにじろじろ見られることには、毎回嫌な気持ちになるというのが正直な感情です。
しかし、現在保育の勉強をしている星来さんは、実習を通じて新たな気づきを得ました。
「今、私は保育の勉強をしているのですが、実習を通じてわかったのは、悪いのは子どもじゃない、ってことなんですね。子どもたちはただ純粋に、見たことのないものに興味を持っているだけなんです」。
この学びは、彼女が社会の視線と向き合う上での心の持ちように、大きな変化をもたらしました。
結論
星来さんの経験は、2型コラーゲン異常症を持つ人々が日常生活で直面する具体的な課題と、それらに対し彼女がいかに創意工夫で乗り越えているかを浮き彫りにします。低身長ゆえの誤解や、運転免許取得時の特別なプロセス、そして社会からの視線への複雑な感情は、障害を持つ人々の生活のリアリティを伝えるものです。特に、保育の学びを通じて「悪いのは子どもではない」と達観した彼女の言葉は、社会全体が多様性を受け入れ、より理解を深めることの重要性を強く示唆しています。星来さんの情報発信活動は、私たちの社会が真の意味で共生社会へと進化するための貴重な一歩となるでしょう。
参考文献
- 文春オンライン (2025年9月6日). 「ちっちゃい子が運転してます」と通報されないように…“身長123センチの大学生”が明かす、世間からの“視線”への向き合い方. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/7666d49a592e9b5794866983c2e08f7c5df84d70