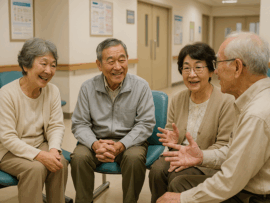2025年7月30日、カムチャッカ半島東方沖で発生した地震は、日本の太平洋沿岸広域に津波警報を発令し、多くの住民が避難を余儀なくされる事態を引き起こしました。幸いにも国内での最大津波高は岩手県久慈港で観測された1.4メートルに留まり、大きな被害は確認されませんでしたが、実は北海道の太平洋側では、近い将来、巨大地震とそれに伴う大津波の発生が強く予測されています。日本列島が地質学的に極めて活動的な地域であるという現実を改めて浮き彫りにする出来事であり、私たちは今、「大地変動の時代」のただ中にいます。
 日本列島が4つのプレート境界に位置する様子を示す地質図。地震多発地帯の理由を視覚的に解説。
日本列島が4つのプレート境界に位置する様子を示す地質図。地震多発地帯の理由を視覚的に解説。
世界有数の災害列島、日本:地震と自然災害の現状
日本は世界でも類を見ないほどの地震多発国です。過去を振り返ると、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、そして記憶に新しい2024年の能登半島地震など、多くの尊い命が失われ、甚大な被害をもたらした巨大地震が頻発しています。日本の国土面積は世界の陸地のわずか400分の1に過ぎないにもかかわらず、世界で発生する地震の約10%が日本で発生しているという事実は、その特異性を明確に示しています。
地震や津波だけでなく、2014年に63名の犠牲者を出した御嶽山の火山噴火、毎年繰り返される台風や豪雨による水害など、日本は多種多様な自然災害に常に見舞われています。なぜ、これほどまでに日本は自然災害が多いのでしょうか。この根源的な問いに対し、京都大学名誉教授であり、地震、噴火、台風といった自然災害の危険性を訴える「科学の伝道師」として活躍されている鎌田浩毅氏が、著書『災害列島の正体 ー地学で解き明かす日本列島の起源』を通じてその理由を解き明かしています。
東日本大震災が引き起こした「1000年ぶりの地殻変動」
鎌田教授は、現在の日本列島が置かれている状況について、次のように説明しています。「まず今の日本列島の状態から説明しましょう。日本列島は、2011年3月11日の東日本大震災(以降「3・11」)を境に、およそ1000年ぶりの『大地変動の時代』に突入しました」。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は、日本列島全体に極めて大きな地殻変動をもたらしたのです。
具体的には、日本列島は最大で5.3メートルも東、つまりアメリカ大陸の方向へと移動しました。同時に、列島の一部、特に東北地方から関東地方にかけての太平洋側では、最大1.6メートルもの沈降が観測されています。これは列島の東半分が東西に大きく引っ張られるような状態にあることを示しており、この途方もない地殻へのストレスが、西日本を含む列島全体の活断層を活性化させる主要な要因となりました。「3・11」の発生後、長野県や静岡県などの内陸部で大規模な直下型地震が相次いで発生したのは、この影響の典型的な事例です。海域で巨大地震が発生した後に、遠く離れた内陸部の活断層活動が活発化する現象は、過去の事例からも多数報告されており、現在の日本列島が地質学的に極めて不安定な状態にあることを裏付けています。
まとめ
日本列島は、四つの主要なプレートが複雑に隣接し、互いに影響し合うという、地球上で極めて稀な地質学的環境に位置しています。この「交差点」とも言える場所が、日本が頻繁に地震、津波、火山噴火といった自然災害に見舞われる根本的な理由です。特に2011年の東日本大震災以降、日本列島は「1000年ぶりの大地変動の時代」へと突入し、地殻の変動が活断層の活動を活発化させ、今後も大規模な地震や津波が発生するリスクが高まっています。北海道太平洋側での巨大地震予測のように、私たちは常に自然の猛威と隣り合わせに生きる宿命を背負っており、科学的知見に基づいた継続的な防災意識の向上と、具体的な備えが不可欠です。
参考文献
- 鎌田浩毅 (2025). 『災害列島の正体 ー地学で解き明かす日本列島の起源』. KADOKAWA.