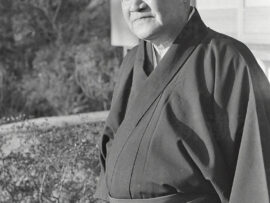三笠宮家を彬子女王が継承したことで、皇室における男女不平等構造が改めて注目されています。特に、皇族費の算定において、男性皇族と女性皇族、そして親王・内親王と王・女王の間で明確な格差が存在し、これが現代社会の価値観と乖離しているのではないかとの疑問が呈されています。彬子女王のケースは、この長年の制度的な課題を具体的に示唆するものと言えるでしょう。
皇族費の算定基準と男女間の格差
皇族費は、皇室経済法施行法に基づき定められた「定額」を基礎としています。この定額は1996年度以降、年額3050万円に設定されており、独立の生計を営む皇族に対して支給されます。しかし、その支給額には男女間で大きな差が設けられているのが現状です。
皇室経済法第6条第3項第1号によれば、「独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額」すなわち3050万円が支払われます。一方、同項第3号には、「独立の生計を営む内親王に対しては、定額の2分の1に相当する額の金額」として1525万円が支払われると明記されており、親王と内親王では支給額が異なります。
具体的な例として、常陸宮家では、夫である常陸宮に定額満額の3050万円、妻である華子妃には定額の半分の1525万円が毎年支払われ、合計で4575万円となります。これは、現行の皇室経済法に基づいた運用です。
彬子女王の事例が示す深刻な格差
今回、新たに独立の生計を営むこととなった彬子女王(43)の皇族費は、さらに減額された額となっています。皇室典範では、天皇の孫までは「親王・内親王」、曾孫以下は「王・女王」とされ、女王は内親王よりもさらに7割相当の額が定められています。その結果、彬子女王への皇族費は1067万5000円となりました。
もし彬子女王が男子(王)であったならば、その額は2倍の2135万円が支払われていたことになります。この差額は、皇室経済法に基づく男女不平等構造を如実に示しています。
将来的な例を挙げると、秋篠宮家から悠仁親王が独立して宮家を創設した場合、その皇族費は3050万円となるでしょう。しかし、佳子内親王が独立して宮家を創設した場合、その額は1525万円にとどまります。これは、皇位継承権を持つ男性皇族と持たない女性皇族という制度上の違いが背景にあるとされていますが、単に継承権の有無だけで割り切れる問題ではないという指摘も存在します。
公務の有無が前提となる皇室経済制度
皇族費における男女格差の問題は、単なる皇位継承権の有無に留まりません。皇室経済法が日本国憲法と同じ1947年5月に施行された際、この制度は「女性皇族は基本的に公務を担わない」という前提で構築されました。
実際に、皇室経済法が制定された当時の天皇家には、孝宮(のちの鷹司和子)、順宮(のちの池田厚子)、清宮(のちの島津貴子)という3人の内親王がいました。彼女たちは当時未成年でしたが、成年後結婚するまでの期間においても、現在のように公的団体の総裁を務めるなど、特定の公務を担うことはありませんでした。例えば裁判所見学などはありましたが、それは社会勉強の一環と見なされており、組織的な公務とは性格を異にしていました。
この歴史的な背景が、現代においても皇族費の男女格差に影響を与え続けていると見られます。しかし、現代では多くの女性皇族が精力的に公務をこなし、皇室の活動を支えています。
結論
彬子女王の皇族費を巡る議論は、皇室制度における男女不平等の根深さを浮き彫りにしています。皇族費の算定基準が、皇位継承権の有無だけでなく、「女性皇族は公務を担わない」という時代遅れの前提に立っていることは、現代社会の価値観との乖離を示唆しています。女性皇族が重要な公務を担う現状に鑑みれば、皇室経済制度がその役割と実態に見合うよう見直されるべき時期に来ているのかもしれません。