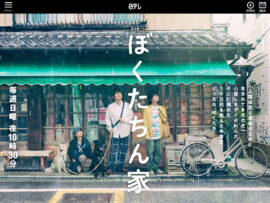近年、サービス業や小売店を中心に「カスタマーハラスメント」、通称「カスハラ」が深刻な社会問題として認識されています。かつて日本企業の間には「クレームは宝の山」という考え方が広く浸透していましたが、2021年に起きたある事件を境に、この認識は大きく変化しました。本記事では、カスハラ対策の専門家である能勢章弁護士の指摘を基に、27年前の「東芝クレーマー事件」と「キッチンDIVE事件」を比較し、カスハラに対する社会の視点がどのように変化してきたのかを深掘りします。
「クレームは宝の山」は過去の遺物か? – カスハラ認識の変化
カスハラに対する世の中の見方は、時代とともに大きく変化しています。この変化を明確に示す二つの象徴的な事件が、1998年の「東芝クレーマー事件」と2021年の「キッチンDIVE事件」です。これらの事例を比較することで、クレームや顧客からの不当な要求に対する社会の姿勢が、いかに変化したかが浮き彫りになります。
1998年「東芝クレーマー事件」に見る世間の反応
1998年12月に発生した「東芝クレーマー事件」は、インターネットが普及し始めた当時の社会情勢を色濃く反映していました。ある顧客が東芝製ビデオデッキの不具合を訴え、同社にクレームを入れたところ、電話対応でたらい回しにされた上、「お宅さんみたいのはね、お客さんじゃないんですよ。クレーマーっていうの」「お宅さん、業務妨害だからね」といった強い口調で応対されたとされています。このやり取りの音声ファイルが「これが東芝の対応」としてウェブ上で公開され、マスコミにも大々的に取り上げられました。
 カスハラ問題に悩むサービス業のイメージ、顧客と従業員の対立の構図
カスハラ問題に悩むサービス業のイメージ、顧客と従業員の対立の構図
結果として、東芝側は顧客のクレームに対し毅然とした態度を取ったものの、世間からは猛烈な批判を浴び、最終的には副社長が謝罪する事態に発展しました。当時の社会は「企業は顧客のクレームに誠実に対応すべき」という意識が強く、企業が顧客に対して強気な姿勢を見せることに対して非常に否定的でした。この事件は、企業が顧客対応でいかに世論に配慮すべきかを浮き彫りにしました。
2021年「キッチンDIVE事件」で転換点
しかし、2021年に起きた「キッチンDIVE事件」では、カスハラに対する社会の認識が劇的に変化していることが示されました。2021年5月、東京都内の弁当店「キッチンDIVE」に訪れた男性2人組が弁当の温め直しを要求しました。しかし、当時店舗では新型コロナウイルス感染防止対策として電子レンジを一時的に撤去しており、店側がこれを断ると、2人組は激高。「こんな店炎上させてやるからな」「なんやコラ、ガキ」などと暴言を吐き、小銭を投げつけるという行為に及びました。
この店舗は24時間店内の状況をYouTubeでライブ配信しており、これらの悪質な行為もすべて動画に残されていました。同店がこの動画をSNSに投稿したところ、瞬く間に拡散され、マスコミでも大きく報道されることになりました。東芝の事例とは対照的に、この事件では店側の対応に対してSNS上では好意的なコメントが殺到。「DIVEさんの従業員を守ろうという姿勢には好感しかない」といった称賛の声が多く寄せられました。動画配信が結果的に従業員を悪質なクレームから守る強力なツールとなったのです。
その後、加害者の一人は後日店舗を訪れて謝罪しましたが、そのまま警察署に連行され事情聴取を受けたとのことです。この事件は、企業や店舗が従業員をカスハラから守る姿勢を示すことに対し、社会が強い支持を与えるようになった転換点となりました。
東芝事件とキッチンDIVE事件から学ぶカスハラ対策の重要性
これら二つの事件を比較することで、カスハラ、ひいては顧客からの不当なクレームに対する社会の認識が大きく変化したことが明確に分かります。
| 項目 | 東芝クレーマー事件(1998年) | キッチンDIVE事件(2021年) |
|---|---|---|
| 社会の反応 | 企業(東芝)への批判、顧客への擁護 | 顧客(加害者)への批判、店舗・従業員への擁護 |
| 企業の対応 | 毅然とした対応が批判を招き、謝罪 | 毅然とした対応が賞賛され、警察が介入 |
| 背景 | インターネット黎明期、顧客が「神様」の風潮 | SNS・動画配信の普及、従業員保護の意識高まる |
| 教訓 | 顧客対応の失敗は企業イメージを損なう | 従業員を守る姿勢が企業イメージを向上させる |

東芝クレーマー事件が起きた1990年代後半は、「お客様は神様」という認識が強く、企業は顧客からのどんなクレームにも低姿勢で対応すべきだという風潮がありました。しかし、2020年代に入ると、社会全体でハラスメントに対する意識が高まり、従業員の保護が重要視されるようになりました。キッチンDIVE事件では、店側が毅然とした態度を取り、その様子を公開したことが、世論の強い支持を得る結果となりました。
この変化は、企業にとってカスハラ対策が単なる顧客対応の一部ではなく、従業員の安全確保と企業ブランド価値を守るための喫緊の課題であることを示しています。過剰なクレームに対して適切な対応を取ることは、今や社会から求められる企業の責任であり、従業員が安心して働ける環境を整備することが、持続可能な経営にとって不可欠となっています。
まとめ
本記事では、カスハラ対策の専門家である能勢章弁護士の見解を交え、1998年の「東芝クレーマー事件」と2021年の「キッチンDIVE事件」を比較することで、カスハラに対する日本社会の認識が劇的に変化したことを解説しました。かつて「クレームは宝の山」とされた時代は終わりを告げ、現代社会では従業員を悪質なカスハラから守る企業の姿勢が強く支持されるようになっています。企業は、この社会の変化を認識し、カスハラ対策を経営戦略の重要な柱として位置づけることが、信頼される企業であり続けるための鍵となるでしょう。
参考文献:
- 能勢章 著 『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』(日本実業出版社)
- 「朝日新聞」1999年7月10日付夕刊掲載記事
- President Online, 「『お宅さん、業務妨害だからね』副社長が謝罪した27年前の東芝クレーマー事件と2021年キッチンDIVE事件の決定的な違い」, 2025年11月9日配信.
https://president.jp/articles/-/104561 - Yahoo!ニュース, 「『お宅さん、業務妨害だからね』副社長が謝罪した27年前の東芝クレーマー事件と2021年キッチンDIVE事件の決定的な違い」, 2025年11月9日配信.
https://news.yahoo.co.jp/articles/20f953cf69ff31ae0a6487b36984ad0459d6f97f