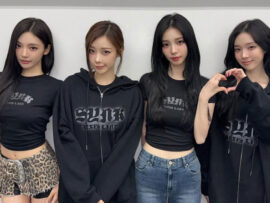NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第6週「ドコ、モ、ジゴク」では、異国の教師レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の女中となることを選んだ士族の娘トキ(髙石あかり)の苦渋の決断が描かれました。明治時代、貧困に苦しむ士族の家で育ったトキが、社会の偏見と家族の窮状の間で揺れ動く姿は、当時の日本社会における女性の立場と外国人との交流の複雑さを浮き彫りにしています。この記事では、ドラマの展開と、そのモデルとなった小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の史実との比較を通じて、彼らの出会いの真実に迫ります。
レフカダ・ヘブン、新たな住まいと女中を求める
松江中学の教壇に立つレフカダ・ヘブンは、宿泊先の花田旅館を後にし、新たな借家を探していました。片目に不自由を抱えるヘブンは、旅館の女中うめ(野内まる)の目の異常を放置する主人の花田平太(生瀬勝久)に憤りを感じ、自身も目の悪さゆえに身の回りの世話をしてくれる人間を求めていました。彼は、同じ中学の英語教師である錦織友一(吉沢亮)に借家探しと世話役の斡旋を依頼。独身の外国人が日本で一人暮らしをすることの難しさから、錦織は島根県知事の江藤安宗(佐野史郎)に相談し、了承を得ます。遊郭を出たがっていた、なみ(さとうほなみ)が名乗りを上げますが、出自を理由に断られ、代わりに士族の娘であるトキに白羽の矢が立てられました。
士族の娘トキへの「白羽の矢」と葛藤
錦織はトキに対し、「ヘブン先生の女中になってほしい」と依頼しました。侍に憧れるヘブンが武家の嗜みを身につけた士族の娘を望んでいること、そして月20円という当時の大金(現代の約40万円に相当)を提示します。これは貧しいトキの家にとって決して悪い話ではありませんでした。しかし、トキは激怒してこの申し出を拒絶します。当時の社会では、外国人の女中になることは一般に「妾」、蔑称では「ラシャメン」と見なされることが多かったためです。このことは、士族としての誇りを重んじるトキにとって到底受け入れられるものではありませんでした。
 士族の娘トキを演じる高石あかり。彼女の演技が当時の女性の葛藤を表現
士族の娘トキを演じる高石あかり。彼女の演技が当時の女性の葛藤を表現
運命を変えた母の姿と小泉セツの「真実」
トキの決意を固めさせたのは、信じがたい光景でした。松江藩の重臣の奥方であった実母の雨清水タエ(北川景子)が、道端で物乞いをしている姿を目撃したのです。さらに実弟の三之丞(板垣李光人)から雨清水家の窮状を聞かされ、トキはついにヘブンの女中になることを決意しました。
ドラマではこのように劇的な経緯が描かれますが、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーン(小泉八雲)とトキのモデルである小泉セツの出会いの経緯については、セツ自身はあまり多くを語っていません。ハーンのアシスタントだった三成重敬が聞き書きした『思い出の記』にも詳細な記述は見られません。セツが晩年に東京朝日新聞の記者に語った話では、明治23年(1890年)12月に八雲の許に嫁いだこと、そして故人の勤めていた中学の西田千太郎という人物が仲立ちをしたとされています。この「西田さん」こそが、『ばけばけ』の錦織友一のモデルです。『思い出の記』には、ハーンが教頭の西田に大変世話になり、二人が互いに親密であったことが記されています。
しかし、セツの談話にはいくつかの辻褄が合わない点があることも指摘されています。長谷川洋二著『八雲の妻 小泉セツの生涯』などの研究を参照すると、二人の「出会い」はドラマのような一本道ではなく、より複雑な事情が絡み合っていた可能性が示唆されています。ドラマはフィクションであるものの、当時の社会背景や個人の運命を深く考察する上で、貴重な視点を提供しています。
まとめ
朝ドラ『ばけばけ』は、士族の娘トキが貧困と社会的な偏見に直面しながらも、外国人教師レフカダ・ヘブン(ラフカディオ・ハーン)との出会いを通じて新たな人生を切り開いていく姿を描いています。ドラマの脚色と史実を比較することで、明治時代の女性が背負った重い運命と、異文化交流の裏にあった真実の一端が明らかになります。この物語は、単なる歴史ドラマに留まらず、現代社会にも通じる普遍的なテーマを私たちに問いかけています。