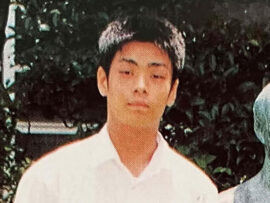高市早苗首相による台湾有事に関する「存立危機事態になりうる」との国会答弁に対し、中国政府は強く反発し、日本産水産物の輸入を停止する方針を表明しました。この外交・経済的な緊張に対し、日本政府はどのような対抗措置を講じるべきでしょうか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は、WTO提訴や環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の活用が有効であると指摘しています。
中国の日本産水産物輸入停止、その背景と日本の対抗手段
中国が、高市首相の台湾有事を巡る発言に対抗し、日本産水産物の輸入を停止した問題は、日本政府に喫緊の対応を迫っています。山下研究主幹は、日本が取り得る対抗措置として主に二つの道を示しています。
1. WTO提訴を通じた国際社会へのアピール
まず一つは、中国の輸入停止措置が国際ルールに則っていないとして、世界貿易機関(WTO)に提訴することです。現在、WTOの紛争処理手続きは、上級委員会の委員任命をアメリカが拒否しているため十分に機能していません。しかし、第一審にあたるパネル(紛争処理小委員会)への提訴は依然として可能です。
実際にパネルは、中国などからの提訴を受け、アメリカが鉄鋼・アルミ製品に課した関税がWTO協定に違反するとの報告を公表しています。パネルの決定は上級委員会が開かれないため確定はしませんが、提訴国は、ある国の行為がWTO協定に違反していることを国際社会に明確にアピールすることができます。
中国が今回、水産物の安全性を理由に輸入禁止措置を取ったことは注目に値します。関税などの輸入制限は原則として特定の国を標的にできませんが、動植物の検疫措置や食品の安全性に関する措置は、特定の国に存在する病気や危険を理由に、その国からの輸入をピンポイントで制限できる国際的な例外が存在します。中国は、この例外規定を政治的な手段として利用していると見られます。
 日中首脳会談を前に、中国の習近平国家主席(右)と握手を交わす高市首相=2025年10月31日、韓国・慶州 – 写真提供=共同通信社
日中首脳会談を前に、中国の習近平国家主席(右)と握手を交わす高市首相=2025年10月31日、韓国・慶州 – 写真提供=共同通信社
2. TPPを活用した中国への交渉圧力
もう一つの有効な手段として、山下研究主幹が提案するのはTPPの活用です。具体的には、中国がTPPへの加入を希望している現状を利用し、中国よりも台湾の加入を先に進めるよう「揺さぶりをかける」戦略です。
中国は「メンツ」を重んじる国家であり、台湾が先にTPPに加入する状況は、中国にとって非常に受け入れがたいものとなるでしょう。この状況を作り出すことで、中国を交渉のテーブルに引き出し、日本産水産物の輸入停止問題の解決に向けた話し合いを促すことができると考えられます。
「食の安全」が政治利用される国際問題
今回の中国による水産物輸入停止措置は、「食の安全」を名目に政治的なメッセージを発する典型的な例と言えます。過去にも、様々な国際紛争において、食品の安全性や検疫措置が貿易制限の口実として利用されてきました。日本政府は、国際法に基づかない一方的な措置に対しては毅然とした態度で臨む必要があります。
WTO提訴によって国際社会に問題提起を行い、さらにTPPという経済的枠組みを利用して中国との交渉に有利な状況を作り出すことは、今回の事態への効果的な対応策となり得ます。
結論
高市首相の台湾有事発言に対する中国の日本産水産物輸入停止は、国際政治における「食の安全」の政治利用を浮き彫りにしました。日本政府は、WTO提訴を通じて中国の措置が国際ルール違反であることを国際社会に訴え、同時にTPPへの台湾先行加入を検討することで、中国を交渉のテーブルに引き出す多角的なアプローチを取るべきです。これにより、単なる経済問題に留まらない、より広範な外交戦略を展開することが期待されます。