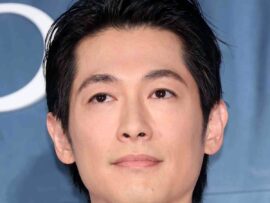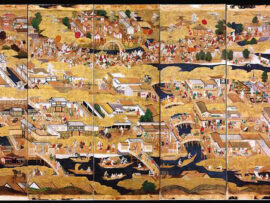石油化学産業では後発国企業の浮上で先進国が汎用(基礎)製品の競争力を失うサイクルが繰り返されている。中国発の物量攻勢の中で韓国も競争優位を守りにくいとの評価が出て久しい。韓国より先にこうした追撃戦を経験したドイツと日本の石油化学企業は電池や機能性素材など高付加価値製品を包括する総合化学企業に多角化する戦略を広げてきた。
世界1位の石油化学企業であるドイツのBASFは積極的な買収合併を通じて収益性が低い汎用事業を縮小し高付加価値製品中心に事業構造を改善した。1990年代から純粋石油化学製品の割合を減らす一方、電気自動車用二次電池などに事業領域を拡張してきた。その結果、汎用製品の割合は2005年の42%から2022年には17%まで低下した。
汎用製品を主力に生産したドイツのエボニックも高付加価値製品事業への転換に成功した代表事例だ。エボニックは1980年代後半から買収合併を通じて事業構造を再編し、2000年代初期からはバイオ技術の研究開発に集中して添加剤や化粧品など高付加価値製品中心に投資した。エボニックの昨年の売り上げは151億5700万ユーロ(約2兆4580億円)で、高付加価値製品事業部門は売り上げ全体の78%に当たる117億9200万ユーロを記録した。高付加価値製品売り上げの割合は2015年の68%よりも10ポイント高まった。
日本の石油化学産業も先制的な構造調整で体質を改善した。石油輸入国である日本は原価競争力で不利なことから石油化学企業間の自律的買収合併だけでは競争力確保に限界があった。これに対し政府主導で設備を縮小し高付加価値事業に転換する戦略を本格化した。1970年代に日本政府は石油化学産業に独占禁止法適用を一時的に猶予し買収合併しやすい環境を作り、1980年代からは本格的に汎用部門の統廃合とともに海外進出と輸出拡大戦略を推進した。IM証券の報告書によると、日本はタイ、マレーシア、インドネシアなど生産コストが安い東南アジアに投資し汎用生産基地を確保した。
同時に内需市場では電子素材、医療機器など高付加価値製品に集中する研究開発戦略を強化してきた。2001年から2023年まで三菱化学や東レなど日本の主要石油化学6社の平均売上額比の研究開発費の割合は3.9%だ。LG化学、ロッテケミカル、大韓油化、錦湖(クムホ)石油の韓国石油化学4社の平均は0.9%にとどまった。
長期間の不況に苦しめられた韓国石油化学企業も最近は高付加価値製品を前面に出して突破口確保に総力を挙げている。LG化学は電気自動車充電ケーブル用超高重合度ポリ塩化ビニール(PVC)、自動車用高付加価値合成樹脂(ABS)など高付加価値製品の市場化に努めている。超高重合度PVCは既存製品の限界だった低い耐熱性を克服した素材で、ABSは優れた耐熱性と衝撃抵抗性で加工しやすい高機能性プラスチックだ。
ロッテケミカルは現代自動車・起亜の基礎素材研究センターと協力してモビリティ用親環境プラスチック素材である親環境ポリメタクリル酸メチル(PMMA)開発を拡大している。親環境PMMAはプラスチックを化学的に分解した後に再融合する解重合方式が使われ、既存のプラスチックと同等な品質の実現が可能な製品だ。
成均館(ソンギュングァン)大学化学工学部のペ・ジニョン教授は「ナフサ分解設備(NCC)で基礎油類を生産する石油化学企業は中国との価格競争で押されるほかない。政府主導で果敢な統廃合を実施し、大規模研究開発投資と支援も後押ししなければならない」と強調した。