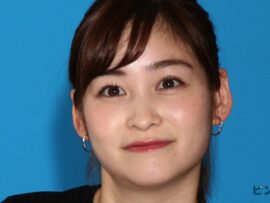長引く物価高が庶民の暮らしを直撃する中、特に家計を圧迫しているのがコメだ。コメと言えば、本来は手ごろな価格で安定的に手に入るべき「国民食」のはず。だが備蓄米放出を経てもなおコメ価格は高止まりしたままで、一向に本来あるべき水準まで下がる気配を見せない。ところがそうした状況の中、JA関係者から聞こえるのは「国民はわかっていない」と言わんばかりの傲慢で現実が見えていない声ばかりだ。コメ高騰は、消費者に責任転嫁するばかりで問題の本質に向き合おうとしないJAに責任の大きな一端があるのではないか。経済誌『プレジデント』の元編集長で作家の小倉健一氏が厳しく糾弾するーー。
国民は「わかってない」豪語する“上から目線”
国民の怒りと落胆を誘ったのは、JA(農業協同組合)グループの広報役とも言える日本農業新聞に寄稿されたJA松本ハイランドの田中均代表理事組合長の見解である。田中氏は2024年4月24日付の寄稿で、価格高騰に苦しむ消費者の視点をあざ笑うような姿勢を示し、まるで国民が「ごはん一杯の値段すらわかっていない」と決めつけた。「5kg4,000円としたら、1杯は50円、コンビニのサンドイッチは300~350円」と説くが、この主張には経済的現実への認識が著しく欠けている。
現実を見失ってしまっている主張に対して、どこから説明して差し上げればいいのかわからないが、家で炊いたお米の原価とコンビニのサンドイッチを比べても仕方がない。お米にサンドイッチ同様の具材をつめて、コンビニで並べたときの値段を比べるか、家で小麦から食パンを作ったときの小麦の原価と比べるべきである。
ちなみに、レンジで温めて食べる「ごはん」は一人前で、セブンイレブンで181円である(7プレミアム特別栽培米宮城県産ひとめぼれ)。サンドイッチと比べるためにはここに具材を加えるわけだが、どう考えてもお米の方が高くなりそうである。
また、価格の絶対値ではなく、問題は「相対的な価値」にある。所得が伸び悩み、他の食品価格が上昇する中で、なぜ国内米だけが高止まりするのか、その構造に対する問いに答えることなく、飲食店の「ご飯無料サービス」の例を持ち出して消費者を諭す姿勢は、支配的立場からの居丈高な論調に過ぎない。無料提供される米の原価は、多くの場合、業務用価格や販促費用に基づく戦略的価格設定の一環であり、それを個人消費の適正価格と混同することは経済論理のすり替えである。