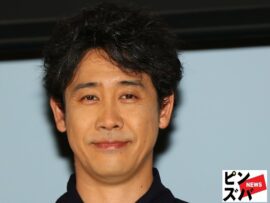■「女性宮家の創設を」「夫・子も皇族に」
読売新聞が5月15日、安定的な皇位継承の確保を求める、皇室典範の改正に関する提言を大きく報じた。内容は①皇統の存続を最優先に②象徴天皇制維持すべき③女性宮家の創設を④夫・子も皇族に――という4項目である。①②は国民のコンセンサスをほぼ得ている。③④は皇統を安定的に存続させるため、女性天皇・女系天皇の可能性を排除すべきではないとの現実的な方策を示したものだ。国民世論も女性天皇・女系天皇を概ね支持している。
【図表をみる】昭和22年10月に皇籍離脱をした旧皇族(11宮家51方)の系統
永田町では、自民党の保守系右派などによる男系継承維持論が根強く、2005年に小泉純一郎内閣が有識者会議の報告書に沿って策定した女系容認の皇室典範改正案は、悠仁さまご誕生もあって、お蔵入りしたままだ。
現在の衆参両院議長の下での与野党協議でも、女性天皇・女系天皇の議論は回避され、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する②旧宮家の男系男子を皇族との養子縁組で皇室に迎える――の2案が議論の対象となっている。2案は2021年12月の岸田文雄内閣の有識者会議の報告書が基になっているが、①では配偶者と子は皇族としない②では養子本人は皇位継承権を有しない、と付記している。
各党・会派による与野党協議を経て、額賀福志郎衆院議長が25年4月に衆参両院正副議長の取りまとめ案を7月の参院選前に提示すると各党・会派に伝え、最終調整は首相経験者である自民党の麻生太郎最高顧問と立憲民主党の野田佳彦代表の非公式協議に委ねられている。
両氏の見解は、女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるようにすることでは一致しているが、野田氏が女性宮家の創設を念頭に女性皇族の夫と子に皇族の身分を与えるよう求めているのに対し、麻生氏は戦後に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子と結婚するケースに限定すべきだと主張し、合意のメドは立っていない。
■宮内庁参与は皇統の存続に危機感を抱く
話は7年前に遡る。宮内庁参与だった渡辺允(まこと)氏に2018年1月9日夜、東京・九段北の中華料理店に呼び出された。読売新聞に17年12月16日に載った以下のコラムを読んで、社会部を通じて、話がしたいとのことだった。
渡辺氏は、外交官を経て、1996〜2007年、天皇陛下の側近No.1である宮内庁侍従長に就いた。退任後も12〜20年に宮内庁参与を務めるなど、上皇ご夫妻の信頼が厚かった。22年2月に85歳で死去している。
7年前の当時は上皇陛下の退位の期日が決定したばかりだった。そして男系による継承を重視する安倍晋三首相が権勢を振るっていた。渡辺氏は、皇統の存続に危機感を抱く。
———-
[補助線]皇位の安定継承のために
論説主幹 小田 尚
政府は8日の閣議で、天皇陛下の退位の期日を2019年4月30日と定める政令を決定した。改元は翌5月1日に行われる。
政府は、年明けから、光格天皇以来約200年ぶりとなる退位に向け、新元号選定や儀式のあり方を検討するという。
残る重要課題は、皇族の減少と高齢化が進む中、皇室制度をどう安定的に維持するかである。
———-