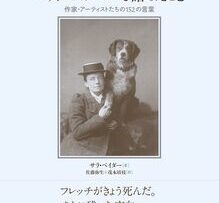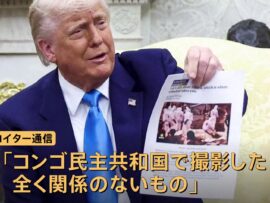太平洋戦争末期、劣勢に立った日本軍は反撃の手段として特攻作戦を開始する。ノンフィクション作家・早坂隆さんの『戦争の昭和史 令和に残すべき最後の証言』(ワニブックス【PLUS】新書)より、海軍が準備していた極秘部隊「伏龍隊」の元隊員の証言を紹介する――。(第2回)
■元隊員が語る「幻の特攻部隊」の正体
特殊な潜水服に身を包んだ隊員たちは、暗い海底でひたすら敵の船艇が接近して来るのを待つ。彼らは炸薬(さくやく)の付いた「棒機雷」を手に持っている。これで敵の船艇の船底を下から突き上げることが、彼らに託された軍務である。
当然、この攻撃を実行に移せば、その兵士の肉体は四散する。言わば「人間機雷」。海軍の中でも極秘中の極秘の扱いだった「伏龍隊(ふくりゅうたい)」の実態は、未だあまり知られていない。「幻の特攻部隊」とも称される。
*
伏龍隊の元隊員である片山惣次郎さんは昭和3(1928)年11月25日、長野県の吾妻村(現・南木曽町)で生まれた。父親は大工だったが、副業として養蚕や農業を営んでいた。片山さんは岐阜県の中津商業学校に進学したが、昭和19(1944)年の春から学徒動員となり、各務原にあった川崎航空機工業の工場で働くことになった。その後、片山さんは海軍飛行予科練習生(予科練)に志願した。
「すでに予科練に入っていた先輩が、学校に来たことがありましてね。その時、金ピカの『七つボタン』が、随分と格好良く見えました」
■胸元に輝く「七つボタン」
予科練の制服には、桜と錨の描かれたボタンが七つ付いていた。この「七つボタン」は「若鷲の歌」の歌詞の中にも見られるように、予科練生のシンボルとして多くの若者の憧憬を集めた。
同年9月、試験に合格した片山さんは、甲種飛行予科練習生(第十五期)として、土浦海軍航空隊に入隊。家を出る際、父親は、「男だでな」と、ぼそりと口にしたという。母親は部屋の隅で涙を拭(ふ)いていた。村の人たちは、軍歌を唄って盛大に送り出してくれた。
こうして始まった憧れの予科練での生活だったが、そこでの訓練は過酷なものだった。毎日のように教官からビンタされたが、革のスリッパで側頭部を殴られたこともある。その後遺症で、左耳は遠くなった。
モールス信号も学んだが、一字でも間違えると「バッター」と呼ばれる木製の棒で尻の辺りを叩かれた。「軍人精神注入棒」「精神棒」「入魂棒」などとも称されたこのバッターは、当時の海軍内で多用された。
■上官が発した「道具」の意味
それでも片山さんは辛抱と努力を重ね、12月に海軍上等飛行兵となった。
昭和20(1945)年6月10日には、基地が米軍の空襲に見舞われた。片山さんは幸運にも無事だったが、一人の戦友の身体は腹部が割け、腸が飛び出していた。腸の連なりは不気味に青く輝いて見えた。その戦友は日頃から真面目で実直、思いやりのある男だった。彼は程なくして、「頼むぞ」と言って絶命した。この空襲によって、8人の戦友が亡くなった。特攻隊への志願者が募られたのは、この空襲後のことである。
上官は「特攻隊としての任務」と告げたが、「飛行機には乗れない」「海でやる」というような曖昧な表現が多く、詳細はわからなかった。皆、不審に思いつつも手を挙げた。片山さんはこの時、まだ16歳であった。結局、約200人の同期生の内、特攻要員として100人の名前が発表された。片山さんは7人兄弟の長男だったが、その中に含まれていた。
総じて特攻隊には長男が選ばれることは少なかったが、伏龍隊の場合は例外であった。選ばれなかった者たちは、その不満を露わにした。彼らは血書をつくって直談判した。しかし、担当の上官は、「そんなに道具がない」と答えたという。
この「道具」という言葉が何を意味していたのか。片山さんたちはまだ知る由もなかった。すなわち、この単語が指し示していたのは「潜水具」だったのである。