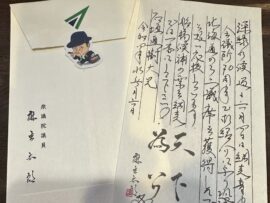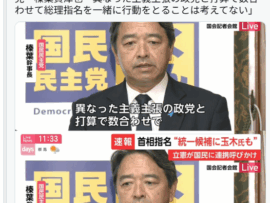近年、夏の記録的な猛暑は、日本の農業、特にコメの実質的な収穫量に深刻な影響を与えています。一方で、政府が発表する統計上の数字と、生産現場の農家が実感する状況との間に大きな乖離があることが指摘されています。この乖離の背景には、長年変わらない国の統計調査方法に隠された「カラクリ」が存在します。
厳しい暑さが続く中で、気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表し、猛暑が農作物へ与える影響が懸念されています。このような状況下、農林水産省が発表するコメの「作況指数」が示す「平年並み」や「豊作」という数字は、多くの農家の実感とはかけ離れています。
現場の農家が語る現実
千葉県匝瑳市にある栄営農組合の顧問、伊藤秀雄氏は、国の統計との隔たりについて疑問を呈します。「数字上は『豊作』に見えても、この辺りで『昨年は米がたくさん取れた』という農家は誰もいません。農水省の発表と、現場の実感がまるで合わないのです」と話します。例えば、2024年の千葉県の作況指数は105と「やや良」を示していましたが、これはあくまで統計上の数字に過ぎないという見方です。
「作況指数」とは?そして農水省の見解
作況指数は、10アール(1000平方メートル)当たりのコメの収量が、過去5年間の平均である「平年収量」(およそ600キログラム)に対してどの程度かを示す指標です。平年を100とし、105なら平年より5%多い、95なら5%少ないことを意味します。
全国の作況指数は、2023年、2024年ともに101と「平年並み」と発表され、2023年産米の収穫量は661万トン、2024年産米は679万2000トンとされています。農水省はこれらの数字を根拠に、「コメ不足は発生しておらず、問題は流通にある」との見解を一貫して示しています。
統計に潜む「カラクリ」:ふるい目の違い
伊藤氏が指摘するのは、この農水省の収量調査の方法に問題があるという点です。農水省は全国約8000カ所の水田を無作為に選び、各地点で3平方メートルのコメを実際に刈り取って収量を調査します(通称「坪刈り」)。この際、収穫した玄米を1.7ミリメートルの「ふるい目」で選別し、その重量を測定して10アール当たりの収量を算出します。

 日本の水田で育つ稲。近年の猛暑はコメの実質収量に影響を与えています。
日本の水田で育つ稲。近年の猛暑はコメの実質収量に影響を与えています。
しかし、ここがカラクリです。米の選別に使用するふるい目の大きさは、地域や品種によって異なります。例えば、千葉県では一般的に1.8ミリメートルのふるい目を使用しています。1.8ミリのふるい目を通る米は、1.7ミリよりも少ない粒になります。

当然のことながら、地域で実際に選別された収量は、国の1.7ミリ基準で算出された統計上の収量よりも少なくなるのです。この統計手法のずれが、現場の実感との乖離を生む主要因となっています。
統計の課題と実質収量への影響
このように、作況指数や収穫量の統計は、特定の測定基準に基づいているため、地域ごとの実情や、近年の異常気象(猛暑など)による品質低下(例:高温障害で粒が小さくなる、未熟粒が増える)を十分に反映しているとは言えません。結果として、統計上の数字だけを見ると「問題ない」ように見えても、農家が実際に販売できる「実質的な収穫量」は減少している可能性があるのです。
農水省は作況指数の発表方法の見直しを示唆していますが、コメに関しては、この統計手法そのものが現場の現実と合っていないという根本的な課題が残されています。正確な需給状況を把握し、適切な農業政策を進めるためには、実態に即した統計調査への改善が求められています。
参考資料:
Original article provided.