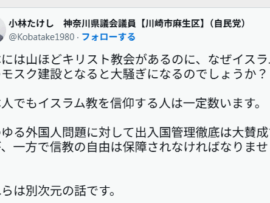「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる大阪・関西万博が、当初の“全面禁煙”方針を転換し、会場内に3カ所の喫煙所を設けることを決定しました。この方針変更は、「煙のない万博」を目指してきた万博協会の理念からの逸脱として、世間に大きな波紋を広げています。背景には、既存の制度の「抜け穴」と、政治の「本音」が透けて見えると指摘する専門家もいます。
会場内喫煙所設置の経緯と理由
万博協会は、開催約2カ月前の5月26日にこの方針転換を発表しました。従来、会場内は全面禁煙とされ、喫煙者は東ゲートに近い会場外の2カ所の喫煙所を利用するために、一度ゲートを出て再入場の手続きを行う必要がありました。特に会場西側からの利用には多大な時間がかかり、この不便さがパビリオン関係者や来場者による会場内での隠れての喫煙といったルール違反を招く結果となりました。このような状況を受け、万博協会は来場者や会場で働く喫煙者のニーズを考慮する必要があると判断し、喫煙所の設置に踏み切ったと説明しています。
 大阪・関西万博の大屋根リング西側に新設された喫煙所。EXPOメッセ隣接で、来場者とスタッフの喫煙ニーズに対応。
大阪・関西万博の大屋根リング西側に新設された喫煙所。EXPOメッセ隣接で、来場者とスタッフの喫煙ニーズに対応。
新設される喫煙所は、大屋根リングの北側と、催事施設「EXPOメッセ」の南側の計2カ所。加えて、既存の東ゲート外の1カ所も会場内から利用できるよう導線が変更され、最終的に会場内に3カ所、会場外に1カ所の喫煙所が整備されることになります。6月下旬から利用が開始される予定です。
禁煙推進団体からの反発と理念への疑問
この決定に対し、禁煙推進団体からは強い反発の声が上がっています。タバコ問題情報センター代表理事で日本禁煙学会理事の渡辺文学氏は、「公の場では吸わないのが当たり前の社会になっている。万博は全面禁煙がベストだ」と訴え、今回の変更が万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に完全に逆行していると批判しました。ルール違反があったからといって、ルールそのものを変更する協会の姿勢に疑問を呈する声も少なくありません。
「煙のない万博」理念と現実の乖離
万博会場は155ヘクタール(東京ドーム33個分)という広大な敷地を持ちます。当初のパンフレットには「会場内でタバコを吸うことはできません。タバコを吸う場合は、再入場の手続きを行った上で、東ゲート外側の喫煙所をご利用ください。」と明記されていました。しかし、この理念と現実との乖離が、今回の喫煙所設置の背景にあると見られます。喫煙者の不便を解消し、隠れた喫煙行為を防ぐという現実的な対応を求める声がある一方で、一度掲げた「煙のない万博」の理念を堅持すべきだという意見も根強く存在します。
タバコを巡る制度的背景と社会的議論
タバコは麻薬類とは異なり、禁止ではなく規制の対象です。高い税率(紙巻たばこ1本あたり52.6%が税金)により、年間約2兆円の税収をもたらしています。喫煙者からは「これほど税金を払っているのだから、喫煙所くらいはきちんと整備すべきだ」という主張も聞かれます。しかし、一方で厚生労働省の研究班や国立がん研究センターは、喫煙による社会的損失を年間4兆円から5.6兆円と推定しており、喫煙を社会的な経済損失と捉える立場からは、利便性を理由に禁煙の理念を捨てることは本末転倒であるとの見方が強いです。過去には東京オリンピックにおいても喫煙ルールが議論され、全面禁煙が原則とされた経緯があり、今回の万博の決定は、社会における喫煙問題の根深さと、利害が複雑に絡み合う現実を示唆していると言えるでしょう。
結論
大阪・関西万博における禁煙方針の転換は、理想的な理念と現実的な運用、健康推進と個人の自由、そして経済的側面が複雑に絡み合う現代社会の縮図と言えます。この決定は、単なるルール変更に留まらず、喫煙を巡る社会的な議論の根深さ、そして政策決定におけるさまざまな「本音」が露呈した事象として、今後も注目を集めるでしょう。