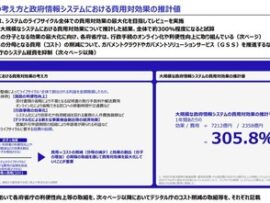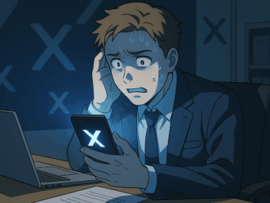米中貿易戦争の激化が続く中、米国はかつてレアアース問題で中国に「ひざまずいた」経験から学び、この重要な資源分野での「再起」を強く推し進めています。米国防総省が国内のレアアース企業に直接投資を行い大株主となる一方、ハイテク大手アップルも当該企業との取引を開始するなど、米国全体がレアアース産業の育成に総力を挙げています。これは、世界のサプライチェーンにおける中国への過度な依存を脱却し、経済安全保障を強化するための国家的な取り組みの一環です。
【背景】米中貿易戦争下のレアアース:米国の「アキレス腱」
ウォール・ストリート・ジャーナルなどが15日に報じたところによると、アップルはレアアースの採掘・加工企業であるMPマテリアルズとレアアース磁石の供給契約を締結しました。このMPマテリアルズは、実質的に国有企業と見なされる存在です。最近、米国防総省が約595億円相当の優先株を取得し、同社の大株主となったためです。MPマテリアルズは、米国で唯一のレアアース鉱山であるカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を保有しています。
レアアースは長らく米国の「アキレス腱」でした。トランプ政権時代に米中貿易戦争が本格化する中で、中国がレアアースの輸出規制に踏み切ると、米国は瞬く間に窮地に立たされ、優位性を失いました。世界のレアアース市場の約90%を掌握する中国は、2024年4月からレアアース磁石の購入者に対し、軍事用途と無関係であることの証明書提出を義務付けました。これにより、5月にはスポーツ用多目的車(SUV)を製造するフォードのシカゴ工場が1週間の稼働停止に追い込まれる事態も発生しました。
 中国内モンゴル地域のレアアース鉱山。中国が世界のレアアース市場の90%を掌握している現状を示す。
中国内モンゴル地域のレアアース鉱山。中国が世界のレアアース市場の90%を掌握している現状を示す。
さらに、F-35ステルス戦闘機をはじめとする米国の先端兵器の生産にも支障が出る可能性が浮上し、米国は最終的に予告していた関税措置を撤回せざるを得ませんでした。これは、中国がレアアースの輸出規制を解除する見返りとして、半導体設計ソフトウェアや石油化学製品の原料であるエタンなどを中国に輸出することに合意したものです。また、エヌビディアの人工知能(AI)半導体「H20」チップの中国への輸出も許可されました。
米国にレアアース資源が全くないわけではありません。ネオジムなど17種類のレアアース資源が地下に埋蔵されており、かつては世界有数のレアアース採掘地として知られていました。しかし、採掘・加工にかかる費用が中国と比較して高かったため、2000年代に入ると米国のレアアース関連企業は競争力を失い、次々と姿を消していきました。
【米国の挑戦】MPマテリアルズの復活と国防総省の戦略的投資
米国のレアアース「再起」の代表的企業として浮上したMPマテリアルズの成長は、開発途上国の企業成長史を彷彿とさせます。ヘッジファンド出身のジェームズ・リティンスキー氏は2017年、放棄されていたマウンテンパス鉱山を買い取り、レアアース事業に参入しました。当初は社員8人の賃金支払いにも苦労する状況でしたが、中国のレアアース企業からの投資を受け、レアアース磁石の製造に乗り出すことができました。その後、独自の処理施設を建設し、米国防総省から1億ドルの補助金を得て、事業を本格化させました。
しかし、2022年には中国の過剰生産によってレアアースの国際価格が急落し、西側の鉱山企業が軒並み苦境に立たされる中、MPマテリアルズもまた厳しい状況に陥りました。同社の株価は最高値から5分の1にまで下落しました。
この逆境の中にあっても、MPマテリアルズはレアアースの採掘・加工から脱却し、レアアース磁石の製造企業へと生まれ変わるため、世界中から専門家を招集し、生産設備の整備を進めました。この過程では、中国企業で働いた経験を持つ専門家や中国製の生産設備を意図的に排除したと報じられています。これは、中国からの牽制を懸念しての対応でした。
【未来への課題】サプライチェーン再構築の道のり
こうしたMPマテリアルズの努力の結果、現在ではテキサス州におけるレアアース磁石の生産量を以前の3倍にまで増強し、追加の工場建設も予定されています。アップルへの供給を見据え、カリフォルニア州にはレアアースのリサイクルラインを構築する方針も示しています。
しかし、米国のレアアースサプライチェーン再構築の道には、まだ多くの課題が残されています。追加のレアアース資源の確保が必要であること、そして大規模な新規施設の建設後も、その安定的な運営には困難が予想されます。ウォール・ストリート・ジャーナルは、「この会社の旅路は、米国の製造企業が産業を復興する際に直面する障害を如実に示している」と指摘しており、中国への依存を完全に脱却し、強靭なサプライチェーンを確立するには、長期的な国家戦略と継続的な投資が不可欠となるでしょう。