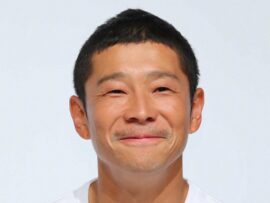高校時代、「数学は苦手だから、文系を選ぼう」と安易に進路を決めた記憶があるかもしれません。しかし、現代社会では“得意か不得意か”だけでなく、その分野への“興味”や“好き”という気持ちに基づいて進路を選択する若者が増えることが望まれています。そもそも、理系や文系といった従来の枠組み自体が、これからの社会で本当に必要なのか、という問いも投げかけられています。
このような時代背景の中で、2025年6月11日、東京都の「GovTech東京」オフィスでは、品川女子学院の生徒たちの明るい声が響き渡りました。これは「Girls Meet STEM in TOKYO」と題された企画の一環として、オフィスツアーと記者発表会が同時開催されたものです。23名の女子高校生たちが、STEM分野(科学、技術、工学、数学)で活躍する女性職員たちと直接対話し、その働き方やキャリアについて理解を深めました。このイベントには小池百合子都知事も駆けつけ、生徒たちに直接エールを送るなど、東京都がSTEM分野における女性の活躍推進に強くコミットしている姿勢が示されました。
日本のSTEM分野が抱える深刻な課題:学力トップでも活躍は最下位
記者発表会に登壇した東京都の松本明子副知事は、冒頭で「日本の女子学生の理科や数学の学力は世界でどのくらいだと思いますか?」と問いかけました。その答えは「世界トップレベル」。15歳時点の女子学生の科学・数学の学力は、OECD加盟国中1位を誇るという驚くべき事実が示されました。
しかし、その一方で、STEM分野で活躍する日本人女性の割合は、統計がある38カ国中、なんと最下位という厳しい現実が突きつけられました。この数字は、日本社会が抱える大きな課題を浮き彫りにしています。優れた能力を持つにもかかわらず、それが社会で十分に発揮されていないという現状は、日本の競争力や多様性の観点からも見過ごせません。
女性のSTEM分野進出を阻む二つの要因
松本副知事はこの深刻なギャップが生じる主な要因を二つ挙げました。一つ目は、身近にSTEM分野で活躍する女性の姿が見えにくいこと。ロールモデルの不足が、女子学生が自身の将来像を描く上での障壁となっています。
二つ目は、「理系は男子の世界」という根強い思い込みが社会に深く浸透していることです。このような固定観念が、女子学生のSTEM分野への興味や進学意欲を阻害しています。結果として、大学でSTEM分野を学ぶ女性が少なくなり、高校生は将来の具体的なキャリアパスをイメージできず、さらに理系を選ぶ女子学生が減少するという負の連鎖が何十年も続いているのが、日本の現状なのです。
 2025年6月11日、GovTech東京のオフィスでSTEM分野の女性職員と交流する品川女子学院の生徒たち
2025年6月11日、GovTech東京のオフィスでSTEM分野の女性職員と交流する品川女子学院の生徒たち
東京都による女性活躍推進の具体的な取り組み
このような状況を打開するため、東京都は2022年度から、女子中高生がSTEM分野の企業を訪れ、働く女性社員と交流したり、最新技術を体験したりする「オフィスツアー」を実施しています。この取り組みは、女子学生がSTEM分野をより身近に感じ、将来のキャリアについて具体的に考える機会を提供することを目的としています。過去3年間で合計定員844名に対し、約1万件もの応募があり、女子学生たちのSTEM分野への関心とニーズの高さが改めて示されました。
特筆すべきは、このオフィスツアーの参加企業数が急拡大していることです。開始当初の3年前はわずか1社だったのに対し、今年は50社を超える企業が協力するまでに成長しました。これは、東京都の積極的な働きかけと、企業側のSTEM分野における女性活躍推進への意識の高まりが合致した結果と言えるでしょう。
メルカリ山田D&I財団との連携強化で活動が加速
この取り組みの規模拡大に大きく貢献しているのが、メルカリの代表執行役CEOであり、山田進太郎D&I財団代表理事を務める山田進太郎氏です。山田氏は、「東京都とは、たまたま同じ方向を向いていたんです」と振り返り、連携の自然な流れを語っています。
同財団は、2035年までに大学入学者におけるSTEM学部の女性比率を28%まで引き上げるという具体的な目標を掲げ、活動しています。東京都の取り組みを知った財団側から声をかけ、今年1月に連携協定を締結しました。これにより、東京都が広報を、財団が企業への呼びかけと運営を担うことで、オフィスツアーの規模は一気に拡大し、より多くの女子学生に機会を提供できるようになりました。
まとめ
日本の女子学生は世界トップレベルのSTEM学力を有しながらも、STEM分野での女性の活躍率は国際的に見て最低水準という矛盾を抱えています。この課題に対し、東京都は「Girls Meet STEM in TOKYO」のような具体的なイベントや「オフィスツアー」を通じて、ロールモデルの提示と固定観念の打破に積極的に取り組んでいます。特に、山田進太郎D&I財団との連携は、これらの活動を加速させ、より広範囲に影響を及ぼす原動力となっています。これらの継続的な努力は、日本のSTEM分野における多様性を促進し、未来の社会をより豊かにするための不可欠なステップとなるでしょう。