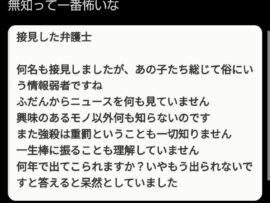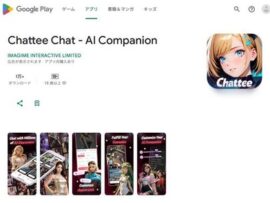世界自然遺産登録から20年を迎える知床では、近年、人とヒグマとの間に異常な距離が生まれています。屋外で飼育されている犬がヒグマに相次いで襲われる事態が発生するなど、野生動物との関係に変化が見られます。希少な自然を求めて多くの観光客が訪れる一方で、ヒグマによる人身事故が起こりかねない、深刻な状況に陥っているのです。
愛犬襲撃に見るヒグマの捕食行動の現実
2019年8月3日午後3時頃、知床半島の東側に位置する羅臼町の漁師、加瀬基敏さん(46)の自宅の庭先で、愛犬の「コロ」がヒグマに襲われるという痛ましい事件が発生しました。コロは加瀬さんが保健所から引き取ってきた犬で、以前には庭先からヒグマを追い払った経験もありました。家族がコロの悲鳴に近い声を聞き、探しに行くと、草むらの奥にはヒグマが歩いた跡が残されていました。その後、ハンターが周辺を調べたところ、ヒグマがコロを食べているところを発見しました。
コロを襲ったのは、地域で「RT」と呼ばれていたヒグマです。このRTは、2018年から2021年にかけて羅臼町内で屋外飼育されていた犬8匹を次々に襲撃し、そのほとんどを捕食していたことが確認されています。これは、ヒグマが家畜やペットを餌と認識し始めている可能性を示唆しており、人里での行動が変化している深刻な兆候です。
エスカレートする人間側の問題行動と潜在的危険
ヒグマとの距離が縮まる背景には、人間側の問題行動も指摘されています。知床国立公園では、カメラを手にヒグマへ無許可で接近するなど、公園利用者の危険な行為が原因となる事例が多発しています。2024年度には、このような危険事例が過去最多の70件も発生しており、観光客の安全意識の欠如が浮き彫りになっています。
また、知床では車にかみつくヒグマの個体も出現しており、これは通常の警戒心を持ったヒグマの行動とは異なる異常な行動パターンです。このような事例は、ヒグマが人間や人工物に対する警戒心を失いつつあることを示しており、偶発的な接触から人身事故に発展するリスクを高めています。
 知床でレンタカーの窓に鼻をつける母グマと2頭の子グマ。人とヒグマの接近を示す象徴的な光景。
知床でレンタカーの窓に鼻をつける母グマと2頭の子グマ。人とヒグマの接近を示す象徴的な光景。
専門家が警鐘を鳴らす深刻な現状
知床で長年ヒグマ対策に携わってきた専門家たちも、現在の状況に強い危機感を抱いています。知床財団で保護管理部長を務めた経験を持つ「野生動物被害対策クリニック北海道」の石名坂豪代表は、現在の知床の状況について、「一般住民や知床の訪問者のヒグマによる人身事故を覚悟しなければならない状況になってきている」と警鐘を鳴らしています。
これは、単なる注意喚起に留まらず、実際に人身事故が発生する可能性が非常に高まっているという強いメッセージです。世界遺産としての価値を保ちながら、人とヒグマが共存できる環境を維持するためには、観光客や地域住民一人ひとりがヒグマの生態やリスクを理解し、適切な行動をとることが不可欠です。
知床の豊かな自然を守りつつ、安全を確保するためには、人間側の意識改革と厳格なルール順守が喫緊の課題となっています。この美しい世界遺産で、悲劇が起こる前に、全ての関係者が協力し、具体的な対策を講じる必要があります。