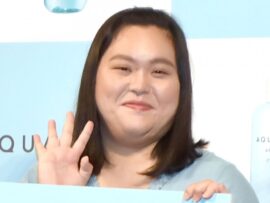気象庁は、今年の6月の日本国内平均気温が平年より2.34℃高く、1898年以降で「観測史上最高」を記録したと発表した。東京都心でも真夏日が過去最高の13日を数え、平均気温は24.6℃と平年比2.5℃高い。この猛烈な暑さは今後も続く可能性があり、東京の「灼熱化」はマンションの資産価値に影響を及ぼし始めている。都内マンション市場を定点観測する「マン点」氏が警鐘を鳴らす「酷暑マンション」の特徴と、その背景にある「熱帯夜」激増の実態を分析する。
 東京の酷暑マンションを見分けるポイントと資産価値への影響
東京の酷暑マンションを見分けるポイントと資産価値への影響
東京を襲う「夏」の常態化と暮らしへの影響
今年の東京は、連日の35℃超えの猛暑日や眠れないほどの熱帯夜が続き、もはや異常気象ではなく、日常の一部と化している。熱中症による悲しいニュースも珍しくなくなり、私たちの「暮らし」そのものがこの暑さに試される時代が訪れたと言えるだろう。このような状況下で「買ってはいけない」マンションとはどのようなものか。その「暑さの盲点」を図解も交えながら読み解くことは、住環境を考える上で極めて重要となる。
1995年頃から顕著になった東京の「熱帯夜」急増データ
東京で30℃を超える真夏日は、かつてはそれほど多くなかった。しかし、気象庁のデータは、東京の夏の過酷さが1995年頃から始まったことを明確に示している。この時期から猛暑日、真夏日ともに増加傾向が見られるが、中でも特に顕著なのが、夜間の最低気温が25℃を下回らない「熱帯夜」の激増である。この変化は、東京の夜間環境が大きく変化していることを物語っている。
「熱帯夜」増加の要因:地球温暖化と都市のヒートアイランド現象
では、なぜ東京でこれほどまでに「熱帯夜」が増え続けているのだろうか。第一に挙げられるのは、地球温暖化の影響である。しかし、都市特有の「ヒートアイランド現象」も見過ごせない主要因だ。都市部の建物や道路に大量に使われるコンクリートやアスファルトは、日中に太陽光の熱を大量に蓄え、夜間になってもその熱を放出し続ける。この「蓄熱」こそが、東京の夜を寝苦しいものにしている根本的な原因なのだ。この現象への対策としては、緑化の推進、保水性舗装や高反射率塗装の導入、そして建物や交通機関からの排熱削減などが考えられるが、いずれも短期間で劇的な改善をもたらすものではない。
東京の夏が年々過酷さを増し、特に「熱帯夜」の激増が示す都市の「灼熱化」は、もはや避けられない現実となっている。この状況は、私たちの日常生活に直接的な影響を与えるだけでなく、不動産、特にマンションの資産価値にも多大な影響を及ぼし得る。今後、住まいを選ぶ際には、単なる立地や設備だけでなく、この「酷暑」にいかに対応しているかという視点が、ますます重要になるだろう。
参考文献
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/eeec0638f2ee0a69fdf6f7ba56fa09fe1610af8b
- デイリー新潮: https://www.dailyshincho.jp/article/2025/07220600/
- 気象庁データに基づく