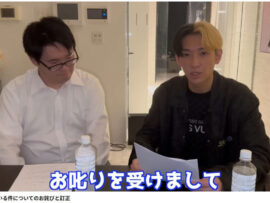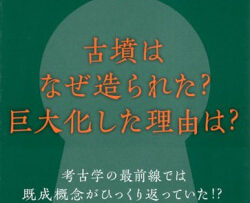30代になると、職場の同僚や友人との間で「貯金はどれくらいある?」といったお金の話題が増えるものです。特に、実家暮らしで家賃や食費などの負担が少ない人と、一人暮らしで全てを自己負担している人との貯蓄額に大きな差があるのは珍しくありません。もしあなたの周りに「貯金が1000万円ある」という同僚がいた場合、羨ましいと感じると同時に、「年収400万円で一人暮らしをしている自分の貯蓄額は果たして適正なのか?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。この記事では、30代単身者の平均的な貯蓄額と、年収400万円・一人暮らしの場合の適正な貯蓄目標について、具体的なデータに基づき解説します。
30代で貯蓄1000万円は「多い」のか?データで見る実態
金融経済教育推進機構が公表している「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、30代の単身世帯における金融資産保有額の平均は459万円です。この数字だけを見ると、「やはりみんな、自分よりも多く貯金しているのか」と焦りを感じるかもしれません。しかし、ここで注目すべきは「中央値」です。同じ調査の中央値は90万円となっており、平均値と中央値に大きな開きがあります。
この差が生じる主な理由は、一部の貯蓄が1000万円を超えるような富裕層が、全体の平均値を大きく引き上げているためです。つまり、実際のところは、貯蓄額が90万円程度の人が多数派であると読み取れます。このデータから、「貯金が1000万円ある同僚」は、30代単身世帯の中ではかなり稀な存在であることが分かります。彼らの貯蓄額が多いのは、家賃が不要、食費もほとんどかからないといった実家暮らしの生活環境が、貯蓄の差に直結している可能性が高いと言えるでしょう。
 30代一人暮らしの貯蓄に不安を感じる人が多い現状を表すイメージ
30代一人暮らしの貯蓄に不安を感じる人が多い現状を表すイメージ
年収400万円・一人暮らしの30代が目指す「適正貯蓄額」とは
それでは、年収400万円で一人暮らしをしている人が、35歳の時点でどのくらいの貯蓄があれば「適正」と言えるのでしょうか。具体的な試算を通じて見ていきましょう。
まず、年収400万円の場合、社会保険料や税金が差し引かれるため、手元に残る手取り額は年収の約8割程度と考えられます。つまり、年間の可処分所得は約320万円(400万円 × 80%)となります。
次に、総務省の家計調査によると、34歳以下の単身者の平均的な月間支出は約18万円です。これを年間で計算すると、約216万円(18万円 × 12ヶ月)が生活費として費やされることになります。
年間の可処分所得約320万円から、生活費約216万円を差し引くと、年間で貯蓄に回せる金額は約104万円となります。ただし、引っ越しや冠婚葬祭、家電の買い替えなど、予期せぬ突発的な支出も考慮に入れると、実際に毎年貯蓄できる額は50万円から80万円程度が現実的と考えられます。
仮に22歳で社会人となり、35歳までの約13年間でコツコツと貯蓄を積み重ねたとすると、貯蓄総額は以下のようになります。
- 毎年50万円を貯蓄した場合:650万円(50万円 × 13年)
- 毎年80万円を貯蓄した場合:1040万円(80万円 × 13年)
この試算から、生活に大きな支障をきたさない範囲で計画的に貯蓄を進めれば、数百万から一千万円程度の貯蓄も不可能ではないことがわかります。しかし、この収入と支出のシミュレーションはあくまで「平均」に基づいたものです。実際の収入は、20代前半ではもっと低い場合が多く、また居住地によって家賃などの支出が大きく異なるため、個々の状況によって貯蓄可能額は変動します。
自身の貯蓄額が適正かどうかを判断するには、平均値に一喜一憂するのではなく、ご自身の具体的な収入と支出を正確に把握し、それに基づいて計算してみることが最も重要です。
まとめ
30代単身者の貯蓄額に関する一般的な不安は、データを見ると平均値と中央値のギャップに起因することが理解できます。同僚が1000万円の貯蓄を持つことは稀であり、多くの場合、実家暮らしなどの生活環境が大きく影響しています。年収400万円で一人暮らしの場合でも、年間50万円から80万円程度の貯蓄を目標にすることで、着実に資産形成を進めることが可能です。自身の経済状況に合わせた適切な貯蓄目標を設定し、未来に向けた資産形成を計画的に進めることが大切です。
参照元:
- 金融経済教育推進機構: 家計の金融行動に関する世論調査(2024年)
- 総務省: 家計調査報告(家計収支編)