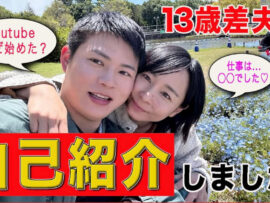2025年7月31日、日本赤十字社名誉総裁の皇后雅子さまは、東京都港区で開催された第50回フローレンス・ナイチンゲール記章授与式にご出席されました。この日の注目は、御料車のフロントに鮮やかに翻る「十六葉八重表菊」が金糸で織り込まれた紅色の「皇后旗」でした。天皇陛下や皇族方の存在を示す旗章は、それぞれの身位と公務の場によって厳格に定められています。今回、皇后雅子さまのお出ましを彩った「皇后旗」の意義とその奥深い歴史について、旗章学の専門家に話を伺いました。
滅多に見られない「皇后旗」の希少性
午後1時45分、白バイに先導された御料車の車列が式典会場に到着。その黒塗りの車のフロントには、皇后雅子さまが乗車されていることを示す紅色の「皇后旗」がはためいていました。車窓から笑顔で手を振られる雅子さまの胸元には、日本赤十字社名誉総裁の記章が輝き、皇后旗の紅色と美しい調和を見せていました。
 フローレンス・ナイチンゲール記章授与式会場に到着し、御料車から手を振る皇后雅子さまと、車窓に翻る紅色の皇后旗
フローレンス・ナイチンゲール記章授与式会場に到着し、御料車から手を振る皇后雅子さまと、車窓に翻る紅色の皇后旗
日本旗章学協会事務局の西浦和孝さんは、「『皇后旗』は、実はなかなか目にする機会が少ない貴重な旗なのです」と語ります。天皇陛下お一人、または両陛下揃って御料車で移動される際に掲げられるのは「天皇旗」であり、私たちが奉迎の機会などで目にするのは主にこちらです。「皇后旗」が掲げられるのは、皇后さまが単独で公的行事にご臨席される際のみに限られています。皇后さまの単独での公務は、毎年春の「全国赤十字大会」や、2年に一度行われる「フローレンス・ナイチンゲール記章」授与式など、特定の機会に限定されるため、「皇后旗」の出番は極めて稀なのです。
「燕尾旗」が示す女性皇族の象徴
この希少な「皇后旗」のデザインは、紅色の生地に十六葉八重表菊という点で「天皇旗」と共通しています。しかし、宮内庁や国立公文書館の資料を詳細に調査している西浦さんによると、一点だけ明確な違いがあると言います。「ひと目でわかる違いは、皇后旗の形が燕の尾のように三角型に切れ目が入った『燕尾旗』であることです。令和に入って新しく設けられた『上皇后旗』や『皇嗣妃旗』も同じように燕尾形で、これは女性皇族特有の形状として区別されています」。皇室の身位を示す旗章の歴史は古く、明治期まで遡ります。1889年(明治22年)の帝国憲法発布の際、「天皇旗」をはじめ、「皇后旗」、「皇太子旗」、「親王旗」が定められ、現在の紅地や白地に菊花紋章というデザインの基礎が築かれました。
皇室の旗章の変遷と令和の新設
元号が平成から令和へと移った2019年、旗研究者の間では皇室の旗章が大きな話題となりました。西浦さんは、「大正15年(1926年)に摂政旗が新設されて以来、およそ100年ぶりに皇室の旗章が増えたのです」と述べます。この時新たに定められたのは、「上皇旗」と「上皇后旗」、そして「皇嗣旗」と「皇嗣妃旗」でした。上皇上皇后両陛下は基本的に公的行事へのご出席が想定されていないため、これらの旗章が用いられる機会はさらに限られます。初めて「上皇旗」が公の場で用いられたのは、上皇さまが退位された2019年でした。上皇ご夫妻が退位を報告する「親謁の儀」に臨むため、東京・八王子市の武蔵陵墓地や京都の孝明・明治両天皇陵へご参拝された際、御料車のフロントに「上皇旗」が掲げられました。「上皇旗」と「天皇旗」はどちらも金糸で十六葉八重表菊が織り込まれた旗ですが、「天皇旗」が紅色であるのに対し、「上皇旗」の生地は深紅となっています。宮内庁によると、この色の違いは、天皇の色である黄櫨染(こうろぜん)に対し、上皇が濃い色を用いたという歴史に基づき、紅色の「天皇旗」よりも濃い深紅の色に定められたとのことです。
まとめ
皇后雅子さまのご公務で掲げられた「皇后旗」は、その美しいデザインと登場する機会の希少性から、多くの人々の関心を集めました。この「皇后旗」をはじめとする皇室の旗章は、単なる装飾品ではなく、それぞれの身位と歴史、そして日本の文化を象徴する重要な意味を持っています。特に「燕尾旗」という形や、色合いの微妙な違いは、皇室の伝統と格式を現代に伝える貴重な手がかりと言えるでしょう。これらの旗章に込められた奥深い物語を知ることで、私たちは皇室の歴史と文化への理解をより一層深めることができます。