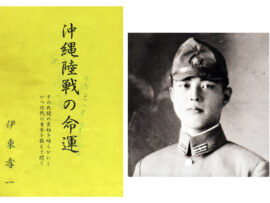小説『女の子たち風船爆弾をつくる』は、第二次世界大戦下で「風船爆弾」の製造に従事した若い女学生たちの姿に光を当てる作品です。著者である小林エリカ氏が、その執筆の背景と、現代に伝えたい真実を語ります。これは、日本の戦時史におけるあまり知られていない一面であり、平和と記憶の重要性を問いかけるものです。
風船爆弾とは?知られざる歴史とその影響
「風船爆弾」は、太平洋戦争末期の1944年11月から1945年4月にかけて、日本の太平洋沿岸(千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来など)からアメリカ大陸へ向けて約9300発が放たれた兵器です。そのうち約1000発がアメリカ本土に到達したとされています。この爆弾は、和紙で作られた巨大な風船に爆弾を吊り下げ、偏西風に乗せて飛ばすというものでした。
その影響は甚大でした。一発はワシントン州ハンフォードサイト近くの送電線に落下し、アメリカの原子爆弾開発「マンハッタン計画」において、長崎に投下されることになるプルトニウムを精製する原子炉の電源を一時的に遮断しました。この復旧作業により、原爆製造が3日間遅れたともいわれています。また、もう一発はオレゴン州ブライに到達し、教会の日曜学校のピクニックに参加していた子ども5人と妊婦1人の計6人が死亡する悲劇を引き起こしました。これは、第二次世界大戦中、アメリカ本土で唯一の敵による犠牲者となりました。
動員された「少女たち」の真実

 第二次世界大戦中、風船爆弾製造に動員された女学生の左手を描いた作品。作者の小林エリカ氏提供。
第二次世界大戦中、風船爆弾製造に動員された女学生の左手を描いた作品。作者の小林エリカ氏提供。
この風船爆弾の製造を担ったのは、満州を含む日本全国の女学生たちでした。「手先の柔らかい若い女学生が和紙の貼り合わせに適している」という理由から、まだ少女である彼女たちが選ばれ、学徒動員として兵器製造に駆り出されたのです。
例えば、小倉造兵廠に動員された女学生たちは「学徒特攻隊」と名付けられ、1日2交替制で、食事をとる時間さえなく昼夜12時間、時には15時間も働き続けました。彼女たちは白い2粒の錠剤を飲まされていたといいますが、これはおそらく覚醒剤であったと推測されています。
東京の街でも風船爆弾づくりは行われ、その場所の一つが東京宝塚劇場でした。直径10メートルの風船を膨らませるには、秘密兵器であることから外から見えない天井の高い場所が必要であり、劇場が選ばれました。戦時下では「不要不急」とされた劇場は閉鎖され、軍の施設となっていたのです。かつてそこで公演していた宝塚歌劇団の少女たちは劇場を追い出され、慰問公演のために前線に送られるか、女子挺身隊として工場で働くことになりました。そして、兵器工場と化した東京宝塚劇場には、雙葉、跡見、麹町の高等女学校の2年生と4年生、現在の感覚でいう中学2年生と高校1年生にあたる10代の女学生たちが動員されました。
作家・小林エリカが風船爆弾に迫った理由
小林エリカ氏が風船爆弾に興味を持ったのには、二つの大きなきっかけがあったといいます。
一つは、長年「核の歴史」をテーマに漫画『光の子ども』を執筆してきた経験です。アメリカのマンハッタン計画を調べる中で、風船爆弾という兵器が原爆製造を遅らせたという話にたどり着きました。さらに、ドイツで放射能研究を行っていた科学者たちが参加していた毒ガス開発について調べる過程で、日本でも毒ガスが製造されていた大久野島を訪れ、そこで風船爆弾づくりが行われていたことを知ったのです。
もう一つは、小林氏が小学校から高校までカトリック系の学校に通っていた際、母親が保護者会で聞いてきた話が記憶に残っていたことです。それは、同じくカトリック校である雙葉高等女学校の生徒として、かつて風船爆弾をつくったというシスターの証言でした。
これらの二つの情報が小林氏の中で結びついたとき、風船爆弾という存在に対し、俄然として深い興味が湧き上がったのです。
風船爆弾の物語は、単なる歴史的事件にとどまらず、戦争がいかに無垢な人々、特に子どもたちの生活を翻弄し、その未来を奪ったかを静かに語りかけています。小林エリカ氏の作品は、忘れ去られがちな過去の断片を拾い上げ、現代に生きる私たちに戦争の記憶とその意味を問い直す貴重な機会を提供しています。
参考文献
- 小林エリカ「風船爆弾をつくった少女たちの抵抗」『文藝春秋PLUS』月刊文藝春秋 2025年8月号掲載記事より