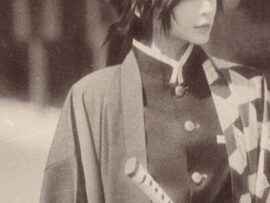京都大学の吉田キャンパス周辺における「立て看板(タテカン)」設置を巡る訴訟で、京都地裁(齋藤聡裁判長)は6月26日、京都市の条例を根拠に京大が設置を禁じたのは憲法で保障された「表現の自由」に違反するなどとして、京大と京都市に損害賠償を求めた京大職員組合の請求を棄却する判決を下しました。これに対し、組合側は「自由の学風とタテカン文化を取り戻したい」と述べ、控訴する意向を表明しており、この判決は日本における大学の自治と表現の自由に関する議論に新たな局面をもたらしています。
京大タテカン文化の歴史と規制の背景
京都大学におけるタテカンは、1960年代の学生運動が盛んだった時代から学生たちによって目立つ形で設置されるようになりました。その内容は、催し物の告知、サークル活動の紹介、そして政治的な主張に至るまで多岐にわたり、時にはユーモアに富んだタテカンが京大名物として市民に親しまれてきました。しかし、2017年10月、京都市は学外に向けて設置されたタテカンが市の屋外広告物条例に抵触すると判断し、京大に対し撤去するよう行政指導を行いました。これを受け、京大は2018年5月にタテカンの一斉撤去に踏み切り、キャンパス内に代替の設置場所を設けました。この際、京大職員組合が活動紹介のために設置していた看板も撤去の対象となり、組合活動への影響も懸念されました。
組合提訴の経緯と地裁の判断
京大職員組合は、タテカンの一斉撤去が「表現の自由を侵害された」ものだとして、2021年4月に京大と京都市に対し、慰謝料など550万円の支払いを求める訴訟を京都地裁に提起しました。組合側は、大学の敷地内におけるタテカン設置は、学問の自由と表現の自由の重要な一部であると主張してきました。
しかし、この日の判決で地裁は、大学には敷地管理権が存在することを認め、組合側がタテカン設置を求める権利までは有さないと指摘しました。また、京都市が定めた屋外広告物条例についても一定の合理性があるとし、組合側の請求を全面的に棄却する判断を示しました。この判決は、大学の施設管理権と表現の自由、そして地方自治体の条例運用という複数の法的・社会的問題が絡み合う複雑な事案において、大学側の管理権と行政の合理性を重視する姿勢を示した形となりました。
 京大タテカン訴訟の判決後、京都地裁前で会見する原告団と弁護団。表現の自由を訴え控訴の意向を示す。
京大タテカン訴訟の判決後、京都地裁前で会見する原告団と弁護団。表現の自由を訴え控訴の意向を示す。
判決後の反応と今後の展望
判決後に行われた報告集会で、京大職員組合と弁護団は、今回の地裁判決を「京大や市の主張を鵜呑みにした不当極まりない判決」と厳しく批判しました。集会では、タテカン文化がいかに学生や近隣住民に親しまれてきたかについて、好意的な意見が相次ぎ、タテカンが単なる広告物ではなく、京大の象徴的な表現の場であったことが改めて浮き彫りになりました。
組合側は、控訴を通じて「自由の学風」を掲げる京都大学本来の精神と、長年にわたり培われてきたタテカン文化を取り戻すことを目指しています。この訴訟は、大学における表現の自由のあり方、学生自治の範囲、そして公共空間における表現活動の規制の妥当性について、社会全体で再考を促す契機となるでしょう。今後の控訴審での展開が注目されます。
参考文献
- 土岐直彦・ジャーナリスト
- Yahoo!ニュース