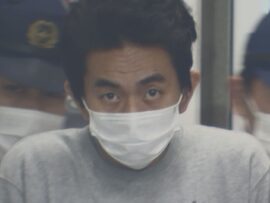終戦から80年を迎える中、戦争と平和について深く考えることは不可欠です。しかし、ここでは少し異なる視点から、占領下の東京がどのようにして現在の発展を遂げたのか、特に道路インフラに焦点を当てて考察します。マッカーサー元帥率いる占領軍が日本の戦争遂行能力を削ぐため、首都東京の復興を否定したにもかかわらず、なぜ東京は目覚ましい発展を遂げたのでしょうか。この記事では、その背景と主要な転換点を深掘りします。
占領下の東京:復興への困難と制約
第二次世界大戦後、東京のほぼ全域は焼け野原と化し、都市再生の絶好の機会に見えました。しかし、「東京百年史」(1972年、東京都)や「東京都政五十年史」(1994年、東京都)といった文献を読むと、当時の都の担当者たちが直面した厳しい現実に歯ぎしりする思いが伝わってきます。占領下の首都という特殊な立場が、大規模な都市計画の実行を阻んだのです。
当時、日本の地方中心都市は空襲後の焼け跡を活用し、幅員100メートル級の広い道路を次々と建設していました。ところが、最も甚大な被害を受けた東京都に対しては、占領軍が「厚木、横田、入間の米軍基地を結ぶ国道16号と五日市街道を整備せよ」と具体的な命令文書を残しているほどでした。
 戦後の東京駅八重洲口、占領下の復興制約を象徴
戦後の東京駅八重洲口、占領下の復興制約を象徴
さらに、占領軍司令部はドッジ・ラインによる緊縮財政方針や、シャウプ勧告による都市計画税の廃止を指示したため、都には道路や鉄道を整備する資金すらありませんでした。当時の都の幹部は、地下鉄建設について占領軍から「安上がりにするならつくってもよい」と言われ、丸の内線を時々地上に出したり編成を短くしたりするなどして経費を節減し、ようやく建設が認められたという逸話が残されています。こうして経済は目覚ましく復興したものの、道路は狭いままで、低層住宅がびっしり建ち並ぶ東京の都市構造がこの時期に形成されました。皇居を中心に市街地が同心円的にスプロール(無秩序に拡大)していき、都市基盤整備は常に後追いとなる結果となったのです。
1964年東京オリンピック:都市開発の起爆剤
占領下で蓄積された都市開発への無念の思いは、1959年に5年後の東京オリンピック開催が決定した時、関係者の間で都市計画実行にかける大きな情熱へと一気に転化しました。長らく抑制されてきたエネルギーが、このオリンピックを契機にほとばしったのです。
この時期の道路整備のキーワードは「拡幅と立体交差」でした。東京では、1959年の自動車登録台数約50万件が、1964年には約170万件へと急増し、マイカーやモータリゼーションといった言葉が流行語となるほどでした。道路の絶対量を増やすことが喫緊の課題となり、オリンピック開催に伴い緊急に整備された「オリンピック道路」は、22路線52キロメートルに及びました。
この時建設された環状7号線は、主要幹線道路や鉄道との交差部分を原則として立体交差としました。皇居を中心に放射状に延びる道路に、同じく皇居を中心に8本の同心円環状道路を組み合わせる東京の都市構造は、これらの立体交差によって機能的な都市を形づくります。環状道路は、周辺部のある地域から別の周辺地域へ移動する車が、放射道路を通って無用に都心に集中するのを防ぐ役割を担っています。
今日、東京の道路率は約17%(1961年には9.8%)と、ニューヨークやロンドン、パリなど世界主要都市の20%程度に比べて著しく低いにもかかわらず、交通渋滞が格段に深刻ということがないのは、この環状道路構造が大きく寄与していると考えられています。北京もこの東京の成功を知っており、2008年オリンピック開催を機に環状道路を整備しました。
首都高速道路:世界に類を見ない立体交差の極致
環状7号線と並んで、東京の環状道路の代表格が首都高速道路都心環状線です。この構想の原型には、戦後、運河に戦災瓦礫を埋め立ててつくられた汐留と京橋を結ぶ「東京高速道路」、いわゆるKK線があります。これは、高架下をテナントビルとして店舗賃貸収入を得て、高架道路を無料とするというユニークな発想で実現されました。
首都高速道路公団の発足はオリンピック開催が決まった1959年で、オリンピック開催の1964年には羽田空港と都心を結ぶ1号線を始め、31キロメートル余りが開通しました。首都高速道路は、交差点部分のみを立体化した環状7号線とは異なり、道路全体を立体化した未来的な設計であり、「立体交差の極致」とも言えるでしょう。
都心部の連続立体交差道路網は世界に類を見ないものです。その後、構想され事業が開始された首都高速中央環状線は、山手通りの地下を走る新宿線が2010年に開通しました。
戦後、占領下の厳しい制約に直面しながらも、東京は独自の都市開発戦略によって奇跡的な発展を遂げました。特に1964年の東京オリンピックは、道路インフラ整備の大きな転換点となり、「拡幅と立体交差」をキーワードに環状道路や首都高速道路が整備されたことは、今日の東京の機能的な交通網を築く上で不可欠でした。これらの工夫と先見の明が、低い道路率にもかかわらず交通渋滞を抑制し、世界有数の大都市としての機能維持に貢献しているのです。東京の道路は、単なる移動手段に留まらず、困難を乗り越え発展してきた歴史の証とも言えるでしょう。
参考文献
- 東京都 編 (1972)『東京百年史』東京都.
- 東京都 編 (1994)『東京都政五十年史』東京都.