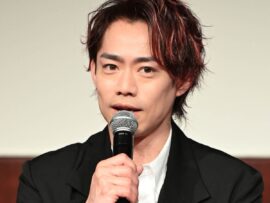日本における外国人に関する議論は、近年、その複雑さを増しています。一部で報じられる外国人によるマナー違反や犯罪行為は、「日本人ファースト」という主張に共感を呼ぶことも少なくありません。しかし、この問題を感情的な議論に留めず、客観的なデータに基づき多角的に分析することが、日本社会全体の利益にとって不可欠です。外国人人口が過去最高を更新する中で、「外国人排除」が日本にとって最善の道なのか、それとも共生の中に新たな価値を見出すべきなのか、その真偽を深く掘り下げていきます。
 日本の街を歩く多様な外国人観光客や労働者たち、共生社会の現状を象徴
日本の街を歩く多様な外国人観光客や労働者たち、共生社会の現状を象徴
増加する外国人:見過ごせないマナー問題と衝撃的な事件
外国人観光客によるマナー違反は、確かに目立つようになりました。大阪城の石垣によじ登る行為や、京都市の伏見稲荷大社周辺の踏切で、混雑の中にもかかわらず線路に立ち入って写真を撮るといった行為は、社会的な懸念材料となっています。さらに深刻なのは、今年7月26日に佐賀県伊万里市で発生した、ベトナム国籍の技能実習生による殺傷事件です。これは外国人による犯罪として、社会に大きな衝撃を与えました。
日本政府観光局(JNTO)の推計によれば、今年6月の訪日外国人旅行者数は337万7,800人と、前年同月比7.6%増を記録し、6月としては過去最高となりました。また、今年1月から6月までの上半期の総数は、2,151万8,100人に達し、過去最速で2,000万人を突破しました。総務省が8月6日に発表した今年1月1日現在の人口動態調査でも、外国人人口は前年比10.65%増の367万7,463人と過去最多を更新しています。このような外国人の急増が、社会に様々な影響を及ぼし、懸念の声が上がるのは当然のことかもしれません。
「外国人増加=治安悪化」論の検証:データが示す実態
「外国人が増えると治安が悪化する」という主張は広く聞かれますが、これは単純な図式ではありません。警察庁の「警察白書(2025年版)」によると、来日外国人(定着居住者や在日米軍関係者を除く)による刑法犯の検挙数は、2024年に前年の1万40件から1万3,405件へと若干増加しました。
しかし、警察庁の説明では、この増加の主な原因は、換金目的の窃盗を繰り返すベトナム人やカンボジア人の組織的犯罪グループによるものであり、彼らが検挙数全体の24.8%を占めていると指摘しています。これは、特定の国籍の組織的犯罪に起因するものであり、一般的な訪日外国人旅行者、すなわちインバウンド全体を治安悪化と結びつけるのは適切ではありません。無関係な大半の外国人旅行者までを一括りに白眼視することは、本質を見誤る行為と言えるでしょう。
さらに、長期的な視点で見ると、来日外国人による刑法犯の検挙数は、ピークであった2013年から2018年の2万~3万件台と比較して、大幅に減少傾向にあります。この期間、来日外国人の総数は大きく増加しているにもかかわらず、検挙件数が減少している事実は、外国人全体の犯罪率が低下していることを示唆しています。外国人居住者についても同様の傾向が確認されており、「外国人の増加=治安悪化」という短絡的な見方がデータと一致しないことが明らかです。
むしろ、少子高齢化が進む日本社会は、労働力不足という深刻な課題に直面しており、経済活動や社会インフラの維持において外国人の存在が不可欠となっています。医療、介護、農業、建設業といった分野では、すでに多くの外国人が日本の社会を支える重要な役割を担っています。もし「日本人ファースト」という名のもとに外国人を一律に排除する方向に進めば、短期的な感情的な満足感は得られるかもしれませんが、長期的には日本の経済成長を阻害し、日常生活が立ち行かなくなるリスクを抱えることになります。
多様な視点で未来を築く:真の共生社会を目指して
日本社会が直面する外国人問題は、「受け入れるか、排除するか」という二元論で解決できるほど単純ではありません。一部の外国人による問題行動や犯罪に対しては、法と秩序に基づいた厳格な対応が求められる一方で、日本経済や社会の維持に貢献する多数の外国人に対しては、適切な環境整備と共生の促進が必要です。客観的なデータに基づいて冷静に分析し、個々の事例を全体に敷衍しない姿勢が求められます。外国人との共生は、日本がグローバル社会で持続的に発展し、より豊かで多様な未来を築くための重要な鍵となるでしょう。
参考文献
- 日本政府観光局(JNTO)発表データ
- 総務省人口動態調査
- 警察庁「警察白書(2025年版)」