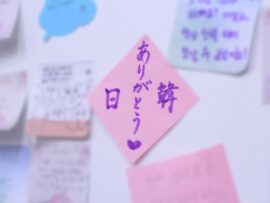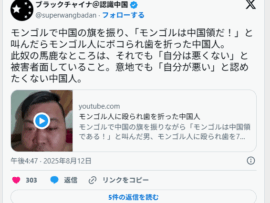日本の都道府県とその県庁所在地を学ぶのは、多くの人にとって小学校の記憶だろう。基本的には暗記科目であり、特に疑問を抱くことなく「こういうもの」として覚えることがほとんどだ。しかし、中には県名と県庁所在地の都市名が一致しない例があり、その理由に興味を持つ人もいるかもしれない。この不一致はそれほど多くはないものの、例えば茨城県(水戸市)、栃木県(宇都宮市)、群馬県(前橋市)といった北関東三県や、神奈川県(横浜市)、兵庫県(神戸市)といった大都市圏を抱える県で見られる。
こうした地理的な知識を改めて見つめ直す中で、一つの奇妙な事実に気づかされることがある。それは、神奈川県の県庁所在地である横浜市の主要ターミナル・横浜駅のすぐ隣に、「神奈川駅」という駅が存在する点だ。県名を冠する駅が、なぜか県庁所在地の中心駅からわずか1kmほどの距離に、しかも「京急線で一番少ない乗客数」を記録する小さな駅として存在しているのか。この状況は、まるで「神奈川県神奈川市」が存在したかもしれない別の歴史線を想像させるような、小学生以来の難問として頭をもたげる。
県庁所在地と県名の一致・不一致:日本の地理的常識
日本の都道府県とその中心都市の関係は、大まかに二つのパターンに分けられる。一つは、東京都(東京)、大阪府(大阪市)のように、県名と県庁所在地の都市名が一致するケース。これは理解しやすく、多くの県がこのパターンに該当する。もう一つは、県名と県庁所在地が異なるケースであり、これが興味深い考察の対象となる。例えば、前述の北関東三県や、大都市圏を代表する神奈川県(県庁所在地:横浜市)、兵庫県(県庁所在地:神戸市)などが挙げられる。これらの不一致は、多くの場合、歴史的な経緯や地域の発展過程に深く根ざしている。かつての中心地が時代とともに変遷したり、合併や行政区画の再編によって現在の形になったりすることがその背景にある。しかし、神奈川県の場合、県名を冠する駅が県庁所在地の中心駅に極めて近接しているという特殊な状況が、さらなる疑問を投げかけるのだ。
横浜駅隣接の「神奈川駅」が抱える疑問
横浜の中心部と「神奈川」という地名が離れていればまだしも、京急線「神奈川駅」は横浜駅からわずか1kmほどの距離に位置している。この近さからすると、むしろ横浜駅自体が「神奈川駅」として機能したり、あるいはかつて「神奈川県神奈川市」という大都市が存在した可能性も考えたくなる。県名をそのまま名乗る駅が、なぜこれほどまでに小さく、主要駅の陰に隠れるように存在しているのか。この地理的な「ねじれ」は、単なる地名の偶然ではなく、横浜という都市が発展を遂げる過程で、かつての「神奈川」という場所が辿った歴史を暗示しているのかもしれない。訪れる者を立ち止まらせ、その背景にある物語を紐解きたくなるような、そんな独特の魅力と疑問を「神奈川駅」は秘めている。
京急線「神奈川駅」の現状と利用者層
横浜駅のお隣に位置する「神奈川駅」は京急線の駅であり、前述の通り横浜駅からは約1kmという至近距離にある。横浜駅自体が広大な敷地を持つため、端から端まで歩けば10分以上かかることも珍しくない。その意味では、神奈川駅は横浜駅の延長線上にあるような小駅とも言える。
 京急線神奈川駅のホーム風景。隣接する東海道線や京浜東北線の線路と比べ、細長くこぢんまりとした駅の様子。
京急線神奈川駅のホーム風景。隣接する東海道線や京浜東北線の線路と比べ、細長くこぢんまりとした駅の様子。
この駅には各駅停車しか停車せず、京急線全体で見ても乗客数が最も少ない駅の一つとして知られている。ホームは人がすれ違うのがやっとというほどの細長さで、東海道線や京浜東北線の線路が並行するすぐ脇にある。朝のラッシュアワーの時間帯ですら、その細いホームが乗客で溢れることはなく、現在の利用状況に見合った規模であることが伺える。この「神奈川駅」の現状は、かつて港町として栄え、開港の歴史を刻んだ「神奈川」という地が、現在の横浜という巨大都市の中でどのように位置づけられているかを静かに物語っている。
結論
京急線「神奈川駅」は、県名を冠しながらも横浜駅のすぐ隣に位置する小さな駅として、日本の地理と歴史の興味深い側面を浮き彫りにしている。県庁所在地である横浜市とは異なる「神奈川」という地名が駅名に残る背景には、単なる偶然ではなく、この地域の複雑な発展の歴史が隠されている。かつて交通の要衝であった「神奈川宿」の面影を残しつつ、現代では横浜という巨大都市の陰に隠れるように存在するその姿は、訪れる者に静かな問いかけを投げかける。この小さな駅は、日本の都市が持つ歴史の重層性や、地名の持つ物語を再認識させてくれる貴重な存在と言えるだろう。
参考文献
- Yahoo!ニュース: 京急線“ナゾの途中駅”「神奈川」には何がある?
https://news.yahoo.co.jp/articles/2be0833d36de4199393a45bd249aebb0199cc5c5