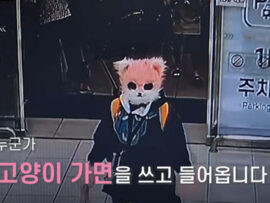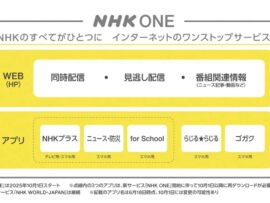日本人女性と長年にわたり婚姻関係を続けてきたスリランカ国籍の男性が、難民認定および在留資格に関する不認定・不許可処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高等裁判所は8月26日、原告側の控訴を棄却する判決を下しました。この判決は、安定した家族生活を築いていても、不法滞在という「違法状態」がその根底にある場合、在留特別許可を与える価値がないという厳しい司法判断を示しています。
 ナヴィーンさんと日本人妻なおみさん、そして代理人の浦城弁護士が記者会見に出席する様子。
ナヴィーンさんと日本人妻なおみさん、そして代理人の浦城弁護士が記者会見に出席する様子。
スリランカ人男性の日本への経緯と複雑な家族の形
原告はスリランカ国籍のナヴィーンさんと、その妻で日本国籍のなおみさんです。ナヴィーンさんは2004年、母国での政治活動が原因で対立政党関係者から暴行を受け、殺害予告まで受けたため、迫害を逃れて同年、日本語学校への留学目的で来日しました。しかし、留学斡旋業者による学費の着服が発覚し、2005年には学校に通えなくなります。その結果、同年12月に留学の在留資格を失い、オーバーステイ(不法残留)の状態に陥りましたが、迫害の恐れからスリランカへの帰国は困難でした。
オーバーステイのまま日本に居住を続けたナヴィーンさんは、2013年2月に初めて難民認定申請を行いますが、翌月には不認定とされ、退去強制令書が発付されます。一方、ナヴィーンさんは2005年にシングルマザーだったなおみさんと出会い、10年後の結婚を約束。子育てを優先しながら交際を続け、2016年に二人は結婚しました。
2017年には2回目の難民認定申請を行いますが、これも2022年6月に不認定となります。同時期に、日本人であるなおみさんとの婚姻を理由に進めていた在留特別許可申請も不許可処分となりました。これらの処分に対し、ナヴィーンさんは2022年11月、難民認定の義務付け、在留特別許可の義務付け、そして退去強制令書発付処分の無効確認などを求め、提訴。しかし、2024年12月には東京地方裁判所で請求が棄却されたため、今回の東京高裁への控訴に至っていました。
難民認定・在留資格問題に関する抗議活動が法務省前で行われている様子。
東京高裁の判断:「違法状態」を乗り越えられない婚姻関係
東京高裁の判決は、ナヴィーンさんの難民認定および在留資格に関する入国管理局と地裁の判断を支持するものでした。
難民認定に関しては、ナヴィーンさんを暴行した対立政党の有力者が2022年に起訴されている事実を挙げ、スリランカ政府が迫害を容認しておらず、ナヴィーンさんを効果的に保護する意思と能力があると判断。このため、入管法が定める「難民」には該当しないと結論付けました。また、ナヴィーンさんが2008年頃には難民認定申請制度の存在を知っていたにもかかわらず、実際に申請を行ったのが数年後であったことから、「迫害を逃れるために亡命する目的で日本に入国したという主張は信用性に乏しい」との厳しい見方を示しました。
在留資格に関しては、ナヴィーンさんがなおみさんの母親や息子とも同居し、「安定かつ成熟した婚姻関係を築いている」ことは認めたものの、その関係が「不法残留という違法状態の上に築かれたもの」であると指摘。このため、保護に値しないとし、在留特別許可を与えないとする入管の判断は裁量権の範囲内であったと判断しました。
弁護士が語る判決への不満と日本の難民・在留制度への疑問
判決後に行われた記者会見で、原告代理人の浦城知子弁護士は「判決について不満に思っている」と語りました。
迫害の恐れについて、浦城弁護士は、有力者が起訴されたからといってスリランカ政府による取り締まりが今後も確実に行われるとは限らないと指摘。また、難民申請が遅れたことに関しても、「難民として逃れてきた人が、すぐに制度について知れるわけではない。(知った後も)認定されるかわからない中で、日本で落ち着いて生活し、本国が安定したら帰国しようと考えるのは不自然なことではない」と、難民申請者の心理を代弁しました。
さらに、浦城弁護士は「オーバーステイ状態という一事をもって『在留特別許可をしなくても構わない』と判断するのは、結婚や夫婦関係、家族関係の価値をあまりに低く見ている」と強く批判。安定した家庭生活を築いているにもかかわらず、過去の不法滞在を理由にその価値が軽んじられる現状に対し、日本の難民・在留特別許可制度が抱える人道的な課題を浮き彫りにしました。
この判決は、国際的な人道支援の精神と国内の法秩序維持との間の複雑なバランス、そして外国人配偶者を持つ家庭が直面する法的課題を改めて社会に問いかけるものと言えるでしょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース (2025年8月27日). 日本の結婚生活長年続けたスリランカ人男性、難民認定・在留資格めぐる高裁判決は棄却「婚姻関係は違法状態の上に築かれたもの」. https://news.yahoo.co.jp/articles/f6c86d0e932bb737682a70b58820f6104b439f29