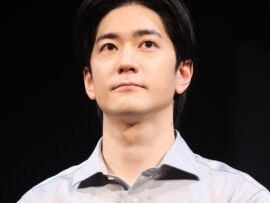この夏、筆者は「野球観戦がどれほど過酷になっているか」を自ら体感するため、高校野球、プロ野球、独立リーグに至るまで、多くの球場を巡りました。一般的に、酷暑の中で野球を語る際、焦点は選手たちの過酷な環境に当たりがちです。選手たちは連日炎天下でプレーし、それ以上に長い時間を太陽の下での練習に費やしています。7月半ばには「暑熱順化」が進み、ある程度の暑さには耐えられるようになります。しかし、観客は応援団を除き、冷房の効いた快適な場所から突如として35度を超える酷暑に身を置くことになります。このため、観客が受けるダメージは選手よりも大きい場合があるのです。この猛暑が、日本人が愛するレジャーである「野球観戦」の機会を奪っているのではないかという懸念のもと、各球場の実情を調査しました。
 夏の高校野球地方大会が開催される埼玉県大宮球場。観客席の一部が見える。
夏の高校野球地方大会が開催される埼玉県大宮球場。観客席の一部が見える。
酷暑下の野球観戦:観客が直面する過酷な現実
全国各地で6月下旬から始まる高校野球の地方大会は、優勝すれば全国大会への切符を手にします。例年であれば7月上旬までは最高気温が30度程度で比較的過ごしやすい日が多いのですが、今年は6月17日に茨城県で早くも熱中症警戒アラートが発令されるなど、西日本を中心に危険な暑さが訪れました。筆者は愛知県、京都府、兵庫県、岡山県、奈良県、大阪府、埼玉県、神奈川県の地方大会を訪れ、その実態を肌で感じました。
多くの地方大会では、熱中症対策の一環として試合開始時間を早める動きが見られました。例えば、愛知県では昨年から第1試合の開始時間を15分前倒ししています。筆者が第1試合を観戦した際、日差しは強烈だったものの、空気はまだ十分に温まっておらず、涼しい風が吹いて比較的過ごしやすい環境でした。
地方大会での体験:球場による環境格差と観客の工夫
球場の規模や設備によって、観戦環境には大きな差があります。岡山の倉敷マスカットスタジアムや神奈川の横浜スタジアムのような大規模な球場では、バックネット裏に屋根があるなど、日陰になるエリアが多く存在します。観客はこれらの日陰に集まり、比較的快適に観戦することが可能です。
しかし、大阪の万博記念公園野球場や奈良県のさとやくスタジアムのような小規模な球場では、屋根がほとんどなく、観客は陽光から逃れる場所が限られています。このような環境では、多くの観客が日傘を差すなどして何とか暑さをしのいでいますが、2時間以上の試合をこの中で見続けるのは非常に厳しいと言わざるを得ません。観客の快適性と安全を確保するための、より抜本的な暑さ対策が求められています。
野球観戦は単なるスポーツ観戦ではなく、日本の夏の風物詩とも言えるレジャーです。しかし、地球温暖化に伴う猛暑が常態化する中、観客が安心して楽しめる環境を提供することは、今後の野球界にとって喫緊の課題となるでしょう。選手だけでなく、観客への配慮も、日本の野球文化を守り育てる上で不可欠な要素と言えます。