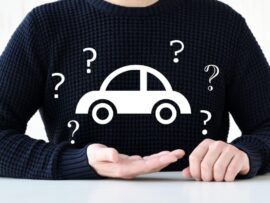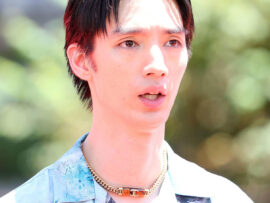文部科学省が2019年以来推進する「GIGAスクール構想」や「令和の日本型学校教育」といった教育政策は、デジタル技術とAIを軸にした「個別最適な学び」を主流と位置づけています。生徒一人ひとりに一台の端末を配布し、学習ログや行動データを蓄積することで、それぞれに最適化された「オーダーメイドな教育」の実現を目指すというものです。しかし、このような理想的な構想の陰で、保護者からは「子どもがネット記事を安易にコピペする」「AIが計算を代替するから計算力は重要ではないと言われた」といった不安の声が上がっています。本稿では、保護者の具体的な懸念に専門家の見解を交えながら、国が掲げる教育の理想と、教育現場が直面する現実との間のギャップを検証します。
「ネット検索頼み」のレポート作成が引き起こす問題
東京都内の公立小学校に通う高学年の男児の保護者であるAさんは、デジタル教育の思わぬ弊害に危機感を募らせています。Aさんによると、学校から配布されたタブレット端末を使った自主学習の課題が頻繁に出されており、生徒は自分でテーマを設定し、書籍やインターネット検索を駆使してレポートを作成・提出するとのことです。
Aさんはこう打ち明けます。「実際には、わざわざ書籍で調べる子は少なく、ほとんどがネット検索だけで提出しています。例えば、息子が大好きな『昆虫の生態』について調べようとした時も、インターネット検索の正しい方法を習っておらず、個人ブログの記事もファクトチェックされた新聞記事も同じ『ネット情報』として捉え、その違いがよく分かっていませんでした。結果として、いかにも『ネット情報』的な真偽不明なソースをもとにレポートを作成していました。以前の自由研究は、子どもが実際に図書館に足を運んで行うものでしたよね。それが、その扱い方についての教育がないままネット検索に置き換わってしまって本当に良いのか、不安でなりません。」
 教室でタブレット端末を操作する小学生。GIGAスクール構想におけるデジタル教育の現場風景。
教室でタブレット端末を操作する小学生。GIGAスクール構想におけるデジタル教育の現場風景。
このようなAさんの懸念を、教育政策に詳しい愛知教育大学の子安潤名誉教授に投げかけたところ、同様の課題は全国の公立学校で広く出されており、文部科学省が「モデルケース」として推進している実態が明らかになりました。子安氏は、「文部科学省はGIGAスクール構想の実現のため『GIGA StuDX推進チーム』を設置し、全国の小中学校、高校の現場で展開されているデジタル・AI教育の事例を紹介しています。最近増えているのが、『教科書で最近学んだテーマや地域の名所をネットで検索して、自分の感想を添えてレポートにまとめましょう』という課題です。Aさんのご子息の課題は決して珍しいケースではなく、全国的に広がっています」と解説します。
自分でテーマを設定し、調査し、レポートにまとめることが目的であるならば、必ずしもインターネット検索を唯一の手段とする必要はありません。さらに、ネット上にあふれる膨大な情報の中から「信頼に足る」情報を見極める技術が十分に教えられていない現状では、誤った情報を参照したり、ある主張をそのままコピー&ペーストしたりするリスクが急増します。
Aさんもまた、「今の小学生は皆、中学受験で忙しく、『ネットですぐに答えが出るもの』で課題を済ませようとする子どもが多いです。息子のクラスメイトは、『憲法』というテーマについて、ネットから引っ張ってきた情報で手早くレポートをまとめていたそうです」と、情報リテラシーの欠如による安易な学習態度への懸念を吐露します。
「個別最適な学び」の理念と現実のギャップ
学校の課題として「タブレット端末を使って、インターネット上の情報をまとめる」ことに、どのような大義名分があるのでしょうか。子安氏は、その背景に「『個別最適な学び』というコンセプトがある」と分析しています。このコンセプトは、子ども一人ひとりの能力や学習進度、興味関心に合わせて最適な学習内容や方法を提供するというものです。デジタル端末とAIの活用は、この「個別最適な学び」を実現するための強力なツールとされています。
しかし、実際の教育現場では、生徒が膨大なネット情報から信頼できるものを選択し、批判的に分析し、自身の言葉でまとめ上げるための具体的な指導が追いついていないのが現状です。「オーダーメイドな教育」という理想は掲げられているものの、そのための前提となる情報リテラシー教育や、主体的に深く考える力を育むためのサポート体制が十分に整備されていないため、多くの生徒が表層的な情報収集と複製に留まってしまっているのです。これは、デジタル技術導入の恩恵を最大限に引き出す上で、避けては通れない重要な課題と言えるでしょう。
結論
GIGAスクール構想に代表される日本のデジタル教育は、学習の個別化と効率化という大きな可能性を秘めています。しかし、その推進の過程で、情報リテラシーの不足や思考力の低下といった予期せぬ課題が浮上していることも事実です。特に、インターネット情報の真偽を見極める力や、得た情報を基に自身の考察を深める能力は、デジタル時代を生きる子どもたちにとって不可欠なスキルです。
文部科学省が掲げる「個別最適な学び」の理念を実現するためには、単にデジタル端末を導入するだけでなく、それらを活用して主体的な学びを促すための具体的な教育プログラム、そして教師が生徒を適切に導くための研修が不可欠です。今後、教育現場がデジタル技術の利点を享受しつつ、その「落とし穴」を回避していくためには、技術革新と並行して、本質的な「考える力」と「情報を見極める力」を育むバランスの取れた教育改革が強く求められます。日本ニュース24時間では、引き続き日本の教育改革の動向とその影響を注視していきます。